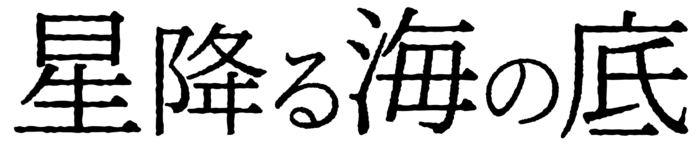アカツキとナユタ 2
その後、デネブ星は一旦アカツキが結晶を星の核に戻したことでひとまずは消失を免れた。
しかし、かつてこの星で生きていた人を含めた数々の生命体は全て絶滅し、今はただの恒星として存在している。
それからアカツキは、天帝に事後処理の報告を終えた後すぐに自室にこもったきり出てこなくなってしまっていた。
心配した天帝が侍女に用意させた食事にも手を付けず、「一人にしてほしい」の一点張りで部屋に入ってきた者をすぐに追い出してしまう。
普段から研究の為に何日も部屋にこもりがちであったアカツキではあるが、先日のナユタの件もあるため、シアンはアカツキを気にかけていた。あの場で、アカツキの一番辛かったであろう決断と行動を始終ずっと見守っていたのは、シアンだけなのだ。
「アカツキ」
シアンは、アカツキの部屋を訪れた。何度か声をかけ扉を叩くが、案の定中から返事が聞こえてくることはない。
ドアノブに手をかけると、どうやら鍵は開いているようだった。
「シアンだ。入るぞ」
中に入ると明かりは点いておらず、いつもと変わらない書類や本で散らかった床がうっすらと確認できる。シアンは目を凝らしてアカツキを探すと、彼は部屋のベッドに横になり、布団の中で丸まっているようだった。
ずっとそうしていたのだろうか。今朝、侍女が用意していった食事がサイドテーブルに置かれているが、手をつけられた形跡はない。
暫くすると布団の中がもぞもぞと動き出し、中からアカツキのくぐもった声が聞こえてきた。
「……入っていいなんて言ってないぞ」
「鍵開いてたぞ。それに、入るなとも言われてないしな」
「屁理屈を言うな。……侍女が開けっ放しで行ったんだろう」
それだけ言うと、アカツキは再び黙り込み、布団の中で動かなくなる。
シアンはため息をついた。あれだけのことがあったのだから、心に傷を負うのも無理はない、と彼の気持ちも理解はできる。だがしかし、彼はもう何日も食事を口にしていないらしい。流石にこのまま放っておくわけにはいかないだろう。
「アカツキ……辛いのはわかるが、せめて食事くらいはしてくれ」
「食べたくない」
「頼むから……お前が研究に夢中で何日も食事を摂らなかったことが何度もあるのを知っているがな、流石にこれ以上食べないでいると死ぬぞ」
本来星の精にとって食事は必須ではないが、消耗した呪力を回復させるにはヒトと同じく、食料から得られる生命力を呪力に変換する為に食事を摂るのと、十分な睡眠を摂ることだ。
アカツキは先日のデネブでの戦いでかなりの呪力を消耗したはず。それから多少眠ることくらいはできたかもしれないが、最初のあまりに弱々しい声を聞き、まだ体力は十分に戻っていないのだとシアンは察したのだ。
それから何度もシアンに厳しく言われ、観念したのかアカツキは再びもぞもぞと布団の中で動いた後顔だけを覗かせた。
ひどく泣きはらした顔だった。ナユタを壊す、と決断した時は気丈に振る舞っていたが、やはり相当辛かったのだろう。アカツキのその顔を見て、シアンは胸が痛んだ。
「……食べさせてくれたら、食べる」
「……ったく」
お決まりのアカツキの我儘だ。いつもなら「自分で食え」と一蹴しているところだが、今回ばかりは少しでも食べる気になってくれたのなら、とシアンはサイドテーブルに置かれている朝食に手を伸ばす。
「暫く食べていないのならまずはスープからの方がいいだろうと思ったが……すっかり冷めてしまってるな。温めてくるから少しだけ待ってろ」
「シアン」
食事の乗ったトレーを持ち一旦部屋を出ていこうとしたシアンを、アカツキの声が呼び止めた。
振り向くと、思いつめた表情のアカツキが布団から出てベッドの上に膝を抱えて座っている。
シアンが首を傾げ「どうした」と返すと、少しの沈黙の後、アカツキはゆっくりと口を開いた。
「ナユタの人生は……あれでよかったのだろうか、と……ずっと考えていたんだ」
ナユタは話してくれた。アカツキがこの研究を思いつかなければ、自分は生まれなかったと。たくさんの幸せや、自由を知ることはできなかったと。
それなら、アカツキも研究に研究を重ね彼に星の精としての生を与えた甲斐があったというものだと嬉しく思う。
だがそれと同時に、自分が見落としていたほんの些細なミスが、幸せだった彼の人生を強制的に終わらせてしまったことを、アカツキはどうしても悔やんでしまう。
「……苦しかっただろうに……辛かっただろうに……私のせいで……」
そう言ってアカツキは涙を零す。おそらく彼はこの数日間、布団の中に籠もってそのような自問自答を繰り返しては、泣き続けていたのだろう。
気が付けば、シアンはそんなアカツキを強く抱き締めてしまっていた。
「……シアン……?」
アカツキは驚いたようにシアンの名を呼ぶが、彼の腕の力が緩むことはない。
「お前だって、辛かったんだろ……」
「……!」
「お前がナユタと最後に何を話したのか、俺はわからない……が、ナユタはそれでも……幸せだったんじゃないか。星の精と星の核は違う。星の核は本来意思や器を持たない、それ故に星に縛り続けられたまま一生を終える。だけど、ナユタはお前のお陰で意思や器を得て、自由を知って……それがほんの短い間だったとしても、幸せだったんじゃないかと俺は思う」
もし仮に自分がナユタの立場であったなら、そう思うだろう。自由をくれたアカツキに感謝をし、そんなアカツキが創った星を自分の力で滅ぼしたくないから、自分を壊してくれと言うだろう。
シアンの言葉を聞いて、アカツキはナユタの最期の言葉を思い出していた。
彼は「ありがとう」と言った。彼を追い詰めてしまった自分に対して、最期まで感謝をしていた。
あの「ありがとう」に込められている意味は、暴走を止めてくれた事に関しての礼だとアカツキは思っていた。しかし、その前にナユタが頭の中に直接語りかけてきた言葉と、シアンの言葉を聞いて、あの「言葉」にはそれ以上の、もっと多くの意味が込められているのだということに気付いたのだ。
「お前がナユタのことを思い苦しむのを、きっとナユタは望んじゃいないさ。今のお前を見たら悲しむんじゃないか。お前と同じだ。自分のせいでアカツキを苦しめてしまっている、って」
「……っシアン……!私は……私は……!!」
アカツキはシアンの胸の中で、大声を上げて泣いた。そんなアカツキの背中を、シアンはまるで子供をあやすかのように優しく撫でる。
今は、思い切り泣けばいい。
そう言葉に出さずとも、彼に語りかけるように、シアンは目を閉じ彼を抱きしめ続けていた。
翌朝、アカツキは再び天帝に謁見を申し出た。
事件当時はとても暗い顔をしていたが、今のアカツキの表情は全て吹っ切れたかのような顔だった。
「暫く部屋にこもりきりであったから心配していたが……その表情、どうやら調子を取り戻せたようだな」
天帝は安心したように笑う。
「して、今日は何の話だ?」
「はい、今後のデネブ星について、ご相談したいのです」
「ん?デネブ星は先日、お前が結晶を元の核に戻して収束させただろう」
アカツキの話に、天帝は不思議そうに首を傾げた。しかしアカツキは目を閉じ、首を横に振って話を続ける。
「私は……私のあの研究のお陰で自由を手に入れ、幸せだったと言ってくれたナユタの意思を、今後に繋げていきたいのです」
「それは……」
天帝は更に不思議そうな表情になる。それはつまり、デネブの星の核を以前と同じく結晶化させ、ナユタのような星の精にするということ。
先の事件の事後処理報告の折、もう二度とあのような悲劇を生まないようにと、その研究は全て封印するとアカツキは話していたはずだ。
すると、アカツキはぽつりぽつりと、そのような決断に至った理由を話し始める。
「あの時、暴走中のナユタが私に語りかけてきたのです。自分は私のこの研究のお陰で、本来であれば一生手に入れることができなかった自由を手に入れ、そして幸せを知ったのだと。そして最期まで、私に感謝し続けていました。……ナユタはきっと、私にこの研究を封印してほしくないと、そう訴えていたような気がしてならないのです」
アカツキは責任感の強い男だ。それをよく知っていたナユタは、あのような事件が起きてしまえば必ず、自分に責任を感じてこの研究を危険視し、永久に封印してしまうだろうと思った。
しかし本来は星の核であるナユタにとって、アカツキのこの研究は本当に素晴らしく有り難いものだったのだ。
自由であるという楽しさを、幸せを、自分(ナユタ)の後にこの星を治めていくであろう「自分」にもまた、感じてほしかった。だから、アカツキにこの研究をなくしてほしくない。
ナユタはそれを己に伝えたかったのだろうとアカツキは気付いたのだ。
「勿論、またあのような事故が起きないよう、結晶化の研究については改良致します。もう原因は把握しておりますので……ですからどうか、ナユタの意思を……」
「成程、ナユタの意思、か……構わん、そういうことであれば好きにするがよい」
天帝の返答を聞き、アカツキは嬉しそうに顔をぱっと輝かせると「ありがとうございます」と頭を深く下げた。しかしその後、アカツキの表情は再び真剣なものへと戻る。
「それと、天帝様……もう二つ、お願いがございます」
「なんだ?」
アカツキは天帝の問いに答える前に一瞬、目を閉じた。そして再び開いた時、その瞳には全てを覚悟したように光が宿っていた。
「私をデネブの主から退任させてください」
「……なんだと……?」
アカツキの申し出に、天帝は驚いたように目を見開いた。
「天帝様やナユタ……そしてデネブの国民達が許して下さっても、己の好奇心で軽々しく命を創った結果、星や国の人々を気機に陥れてしまったという私の罪は消えません。故に、デネブの主を退きたいと思っています。今後のデネブの管理は、現在天の川銀河の統括者となっているシリウスに一任を」
「全く、まだ気にしておったのか」
天帝は呆れたようにため息をつく。
確かにナユタの暴走によってデネブで活動していた生命体は絶滅してしまったが、それでも最終的にはアカツキ自身がナユタを止め、デネブという星は消滅を免れたのだ。
この星はまだ潰える時ではない。天帝の定めている未来が天帝にそう告げていた。だから勅命を出し、シアンと共に戦うように命じたのだ。そしてアカツキは見事、シアンと共にそれを食い止めた。これで因果が狂うことはなくなる。天帝にとってはそれだけが非常に重要で、彼らのその働きで十分罪滅ぼしになっただろうと思いアカツキを許していたのだ。
だが、アカツキがそこまで責任を感じているというのであれば、無理強いをする必要もないか、と天帝は顎に手を当てながら考える。
「そこまで言うのであれば仕方がない。今後はデネブの管理の全てをシリウスに任せよう。後にシリウスに伝えておく。して、もう一つの願いとはなんだ?」
「はい。それに伴い、デネブ星の記憶と歴史から、私とナユタに関する記録を全て抹消する許可を頂きたいのです」
アカツキのもう一つの願いを聞き、天帝は先程よりも驚愕した表情でアカツキを見つめた。
アカツキの司る「記憶」という力。それは星の記憶や歴史を管理、監視するものであり、天帝の命によってその記録を抹消、改ざんすることもできる力である。力を使うことができるのはアカツキであるが、天帝の許可が下りなければ基本、アカツキの独断でその力を使うことは許されない。アカツキは普段は、管理と監視のみを仕事としている。
つまり、アカツキはデネブ星を手放すだけでなく、デネブ星から己の痕跡を全て消してしまいたいと訴えているのだ。
「アカツキ……お前はデネブを創った者だ。主を退くだけならまだしも、何もお前がデネブに関わっているという記録まで抹消するなど……そこまでする必要はないと我は思うのだが……それに、ナユタの記録も、などと……」
天帝は困惑した様子を隠せない。
無理もないだろう。星の創造主というのはその星、国、世界の王であるということ。
その星に住まう人々や星の精全てが創造主に傅き、敬う。星の精にとっては誉れともいえるべき立場なのだ。
アカツキがデネブの主を退いたとしても、その記録が星の記憶と歴史に刻まれていれば、アカツキの名は後世まで残る。
天司十星であるアカツキのことを、天帝は我が子のように思っている。そんなアカツキの誉が全て抹消されてしまうのを、天帝は気の毒に思ったのだ。
しかし、アカツキは目を閉じ静かに首を横に振る。
「大罪人として名が残り続けるのであれば、己の罪滅ぼしとしてそれもいいでしょう。ですが、星の子やその星のヒトは創造主を決してそう見ることはありませんから」
アカツキは、最後の生き残りだったあのナユタの側近のことを思い出していた。
自分がナユタを創ったことで、彼が暴走した経緯までは知らないにしろ、そのナユタが大切な仲間を、家族を、街も国も全て破壊してしまったのに、それでもナユタ――デネブの創造主であるアカツキを責めることはしなかった。
アカツキの回復力では彼の傷を癒やしきることができず最終的に助けられないことがわかった時も、アカツキは何も言わなかったのに、彼はそれを悟ったように、静かに、ゆっくりと訪れる自らの死を受け容れていた。
命乞いも、非難の言葉も、彼の口からは一言も出てこなかった。彼だけでなく、あの星に住む人々全員が同じ状況であったとしても、アカツキが彼らから罵倒されることは決してない。
創造主とその星に住む人々の関係は、絶対服従。それは、そうなるように天帝がこの世界に組み込んだ秩序なのだ。
だが、ナユタのことは……――
「あの側近は、ナユタのことも悪くは言いませんでした。ですが……私がこの研究で再びナユタと同じ存在を創れば、後に再びあの地に誕生するかもしれないヒトが自身の星の過去の歴史を紐解いた時……ナユタが起こした事故を知り、怯え内乱を引き起こす可能性もあります。私は……ナユタを創った者として、我が子の名誉を守りたい……これは、ただの私情です」
「そういうことであれば、記録を改ざんすればよい。何も抹消することはなかろう」
「……ナユタの生きてきた軌跡は、弄るに忍びないので……面倒くさい親ですね、私」
そう言ってアカツキは苦笑した。
それを聞いた天帝は、ふと何かを思い出し苦笑交じりに小さくため息をつく。
「……いや、お前のその気持ちは、我にもわからなくはないな」
天帝も今まで、数多くの天星や星の子達を生み出してきた。アカツキと同じく、天帝にとって彼らは我が子も同然の存在であり、皆等しく愛情を注ぎ育ててきた。
少し前、まだ天の川銀河を天帝が管理していた頃、天帝は、自分の創ったベガが生んだ星の子がこの宇宙を気機に陥れる程の大事故を起こしかけたため、彼女を封印した。そしてアカツキに彼女と彼女に関係する者の記録を一部改ざん、抹消するように命じた。苦渋の決断だった。
彼女のその事件に関する出来事をすべて知っているのは、天帝とアカツキ、そしてその事件に関与した当事者のみ、ということになっている。
関与した星の歴史には、彼女達の記録は断片的にしか残されていない。本来であればナユタのように世界を壊しかねない出来事を引き起こしたのだから、それを国民たちに悟られないよう、彼女の存在ごと記録を抹消すべきであったのだが、彼女をかわいがっていた天帝の良心がそのような決断を下すことをできなかった。
星の歴史には、彼女が確かにベガに繁栄をもたらしていたという事実だけが、今はしっかりと残されている。
アカツキも彼女のことを思い出していたようで、少し悲しげに目を伏せていた。
「……まあ、そうだな。お前がそこまで言うのであれば、我はもう止めはせん」
「天帝様……ありがとうございます」
「だが……あまり気に病んで皆に心配をかけるでないぞ。ナユタの意思を再びデネブ星へ繋いでいくのであれば、尚更な」
天帝に窘められ、アカツキは少々申し訳無さそうにはにかみながら深々と頭を下げた。
その後、アカツキは星の核結晶化の研究を更に進めて改良し、そしてデネブに再び星の精が誕生した。
デネブの歴史は、その星の精が誕生した段階から改めてのスタートとなる。どんなに過去を手繰り寄せようと、それ以前の記録は全て”なかったこと”になっている。
胸に赤い星の結晶を宿した星の子。赤毛の彼はその結晶の力で新たなデネブ国に繁栄をもたらし、守り続けている。
やがてその結晶はデネブの人々から「賢者の石」と呼ばれるようになり、長制度が導入された後初代長が彼の守る星の力を借りて錬金術を生み出した。
こうしてデネブは「錬金術の星」と呼ばれるようになり、星の核は何度か器替えを繰り返しながらも星の精として自由な人生を送り続けていた。
デネブ星の主から退いたアカツキは、そういった話を時折シリウスから聞かされるだけであり、その後は一切デネブ星とは関わらず、デネブ星へ訪れることもなかった。
「久しぶりだな、アカツキ」
「シリウス。随分と大変だったようだな、元気そうで何よりだ」
こうしてシリウスと直接対面するのは何百年ぶりだろうか。
今はアカツキも天帝から銀河を与えられた統括者となり、シリウスは天の川銀河の統括者をしつつ太陽の星の精となり、太陽系に属する星々の管理も兼ねている。更に局部銀河群の総統括も任され、彼が天宮にいることはとても少なくなっていた。
更に少し前、天の川銀河に突如現れた「ブレウス」という悪星の討伐命令を天帝から出されていたシリウスは、かの星相手に相当苦戦を強いられていたとフロー達からも聞かされていた。
が、つい先日ベガ、アルタイル、デネブの三国とクリスタルの英雄達の力を借りてようやくブレウスを討伐することに成功し、天帝に報告も兼ねて天宮へ戻ってきていたのだという。
「お前が消されかけたと聞いた時は、本当に肝が冷えたぞ。天帝様の焦りっぷりもすごかったしな。お前が消えてしまえば、この宇宙の何もかもが止まってしまうのだから」
「はは、それについては本当に面目ないな……だが、蘇芳のお陰で助かったよ。今後アルタイルには頭が上がらなそうだ」
シリウスは苦笑しながらそう語ると、ふと思い出したように手を叩いた。
「そうだ、暫くアカツキに会えていなかったから話すことができずにいたが、デネブの星の精が器替えをしてな、四代目に入ったぞ。……まあ、正式には五代目、だが」
「……そうか。どうやら改良はうまくいっていたみたいだな」
シリウスの報告を聞いたアカツキは目を細めて笑う。
デネブの星の核――賢者の石は、星の核である自身を守るために強固な器を創る。少しでも器に老朽化が見られれば星の核は危険を感じ、今の器を捨て新たな器を創り出す。そうして定期的に器替えを行い、デネブの星の精は今も問題なく幸せにすごしているのだという。
「四代目は俺が鴫、と名付けたんだが……彼は、今までデネブを守ってきた星の精の中で、一番ナユタに似ているよ」
「ナユタに……?」
今までデネブを守ってきた星の精達も皆、ナユタと同じ赤毛の男子だと聞いていた。
元々同じ星の核が創り出す器だからだろうか、目や鼻の形や性格等多少の違いはあれど、そこだけは必ず共通していた。
アカツキがデネブへ訪れなくなった理由の一つでもある。
顔や性格が違っていても、アカツキにとってその容姿だけで彼を思い出すには十分な要素であるからだ。
勿論、ナユタを亡くしたのはもう何千年も前の出来事であるから、流石にあの事件を思い出して気に病むこともなくなったのだが……。
「そう、か……」
アカツキは目を伏せ、短く答えた。
その空気の気まずさにやはりナユタのことは地雷だったか、とシリウスは言葉に詰まったように「あー……」と唸ってから、明るい声で話題を切り替えた。
「そうだ、今度天帝様がクリスタルの英雄達をこちらに招待して感謝の宴を催すそうなんだ。アカツキにも是非皆を紹介したいから、顔を見せてくれると嬉しい」
突然話題を切り替えたシリウスに、アカツキは自分が彼に気を使わせてしまったことに気付いた。そしてすぐに微笑むと
「わかった。……すまないな」
と、気を使ってくれたシリウスに謝罪をする。
「いや、私の方こそ配慮が足りていなかったな、すまない。……おっと、もうこんな時間か。これからまた天帝様のところへ行かなくてはならないから、また後でゆっくり話そう」
そう言ってシリウスはアカツキに軽く手を振ると、その場を後にした。
広い廊下に一人取り残されたアカツキは、先程の自分とシリウスのやりとりを呆然と思い出していた。
もうナユタのことは吹っ切れたと思っていたはずなのに――
そんなことを考えていると、前方から二人の男性の話し声が聞こえてきた。
楽しそうな話し声のうち、片方の声にアカツキはすぐに、聞き覚えのあるあの声だと気付く。
「俺、天宮に来るの初めてなんだ」
「そうなのかい?」
「星が消滅寸前まで追い詰められるほどの大きい戦いなんてこれまでなかったから、今まで天宮とのやり取りは全部文書でしてたんだ。あとはシリウス様が直接伝えに来てくれたりとか……ほら、俺達みたいな星の精ってあんまり星を不在にするわけにはいかないからさ。まあ今日は天帝様に呼ばれたから特別だけど」
前方から少しずつ近付いてくる声の主を、アカツキはその目でしっかりと捉えた。
赤毛の長髪と、同じように赤く輝く瞳の色。隣を並んで歩いている綺麗なタンザナイト色の髪を持つ青年へ向けているその笑顔は、かつて自分に向けられていた「彼」のそれと瓜二つである。
「……ナユタ……?」
思わず、アカツキは小さな声で呟いた。が、すぐに彼は別人だと理解した。
「鴫ってば、だからといってさっきからそわそわしすぎじゃないか」
もう一人の青年が、彼を「鴫」と呼ぶ。それで、彼はナユタではなく、先程シリウスが話していたデネブの五代目の星の精、鴫であることに気付いたのだ。
先程シリウスも天帝に用があると言っていたし、恐らく先のブレウス討伐の件で彼らも天帝に呼ばれたのだろう。
「……そう。そうだな。ナユタはもういないのだから……」
アカツキはふ、と息をつくように笑うと、そのまま前方に歩を進めていく。
天宮に来るのが初めてだからだろうか、周りを見るのと話をするのとで夢中らしい二人は、すれ違ったアカツキの存在に気付かなかったようだ。
そのまま二人の声は後方へ遠ざかっていく。
「……」
「……鴫?どうかしたのかい?」
少し遅れて誰かとすれ違った気配に気付いた鴫は、突然足を止めて後方を見つめていた。
彼の視線の先には、遠ざかっていく一人の天星の姿がある。
響も鴫に倣って後ろを振り返ると、彼が見つめている人物の後ろ姿を見て誰なのか理解したらしい。
「あの髪の色は……多分アカツキ様だね。いけない、すれ違ったのに気付かなかった」
その名の通り、まるで暁の空のような綺麗な髪色をしている天司十星の一人「記憶」を司る星の精、アカツキ。
実際に姿を見たことはなかったが、響達は以前から、仲間である天司十星達の話をシリウスから幾度か聞かされていたのだ。
シリウスは何故かアカツキのことは外見の特徴から詳しく色々と話してくれていたので、響はそれですぐに彼だと特定できたのである。
「……ああそうか、あの人が……」
鴫は彼とすれ違った時に一瞬、胸の中にある賢者の石がざわめいたのを感じたのだ。同時に不思議な感情が流れ込んできたのも……
「変だな……初めて見たのに、なんだかとても懐かしい感じがしたんだ……」
アカツキの後ろ姿が見えなくなるまで、鴫は不思議そうに彼を見つめ続けていた。だが、その感情の出処はやはりわからず首をひねるばかりの鴫に、響も不思議そうに問いかけた。
「鴫ではない先代が、昔どこかで会ったんじゃないのかい?」
「うーん……いや、石の記憶にはあの人の姿はなかったよ。シリウスがよく話してくれてたからそんな感じがするだけなのかも。後で挨拶に行こうな」
「うん、そうだね」
そう言って二人は笑い合う。
そして二人は、後に催された天帝の宴でシリウスに頼み込み、アカツキと対面することができた。
「初めてお目にかかります。デネブの星の精、鴫です」
緊張した面持ちで頭を下げる鴫は、やはりかつての彼にそっくりだ、とアカツキは思った。
「初めまして、アカツキだ。よろしく」
シリウスから幾度か話を聞かされていたと語る鴫は、ずっと会ってみたかったのだと言って嬉しそうにアカツキに握手を求めてきた。
アカツキは目を細めて笑うと、快くその手を握る。
――ああ、やはり……懐かしいな……
互いにそう思いながら、しかしその思いは内側に秘め、二人は他愛ない会話に花を咲かせるのだった。
end