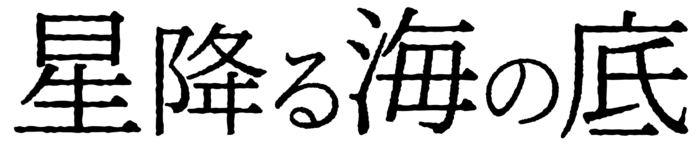アカツキとナユタ
天司十星のひとり、天帝から「記憶」の力を授かったアカツキが最初に創った星は、天の川のすぐ傍らで白鳥のように白く美しく輝く妖精国「デネブ星」だった。
アカツキは何よりも、己の知的好奇心のままに行動をするのが好きだった。
デネブ星は、そんなアカツキの知的好奇心から生まれた最初の特殊な星である。
「ふう……なんとかうまくいったみたいだ」
自身の掌の中で暁のように赤く輝く結晶を見つめながら、アカツキは息をつく。
この赤い結晶は、デネブの星の「核」である。
通常、アカツキ達が創り出す星は「生命」を司るフローライトの力を一つに結集し、それを核として形成される。その核こそが星のすべてなのだ。
核はその星の力の源として星の中心に在り続ける。意思をもたず、知恵も持たない。ただ機械のように星とその星に住む生命の歴史を記録していく存在。
アカツキはそんな星の核を星から切り離し、星の精として人格を与えるとどうなるのか、ということを思い付いた。そして研究に研究を重ね、ついにそれは実現した。
アカツキの掌の中で輝く赤い結晶は徐々に輝きを増していく。「星」にとって「核」はとても大切なものだ。これが壊されてしまえば、星そのものがなくなってしまう。この輝きは、星の核が自身を守る器を形成している光――星の核の防衛本能のようなものである。
やがて眩かった赤い輝きはゆっくりと収束していき、アカツキの腕の中に小さな赤子が現れた。すやすやと寝息をたて、赤毛のその子供は気持ちよさそうに眠っている。
「器も無事に造れたか。君はこの星が生んだ星の精であり、そしてこの星そのものでもある。名は……そうだな、私が創った一番最初の、多くの未知の可能性を秘めた星の精だ。那由多……ナユタ、と名付けよう」
そしてアカツキは、ナユタと名付けたその赤子の額に軽くキスを落とした。
ナユタは天真爛漫で人懐こく、とても活発な少年だった。
主であるアカツキを誰よりも強く慕い、時折親にするように甘え、そしてデネブ星に住む国民達を大切にし、国をより良くするために力を使って統治を行った。
彼はルピナスの「意思」とロキの「知恵」の力もきちんと取り入れ「人らしさ」を身に着けていた。元は星の核という特殊な星の精であるが、ぱっと見ただけでは他の星の精達と何も変わらない。
「アカツキ、今日も来てくれたのか!」
成長し、立派な青年の姿となったナユタは、デネブ国の様子を見に訪れたアカツキを嬉しそうに出迎えてくれた。
つい先日、アカツキとナユタは恋仲となった。
ナユタは以前からずっと、アカツキに対して恋慕の感情を抱いていたらしい。その気持ちは本人もよく理解できていなかったようなのだが、側近に相談してみたところ「それは恋なのではないか」と言われたというのだ。
素直な彼はすぐにその気持ちをアカツキに伝えた。「この子も、そのような感情を抱くのか」と、アカツキは内心驚いた。そして、彼から気持ちを伝えられたアカツキも、自分自身がナユタに対して同じ感情を抱いていることに気付いたのだ。
ナユタの気持ちを受け容れ、アカツキは以前よりもナユタのことを気にかけるようになった。
彼は普通の星の精とは違う、星の核から創られた特殊な星の精である。それはアカツキが興味本位で始めた研究によって創り出された最初の「作品」であること。これまで何事もなく元気に成長してきたナユタではあるが、今後何が起きるかわからない。
今までもよく気にかけてはいたが、「大切な存在」となった彼のちょっとした異変も見逃さないよう、彼を守り続けるために、アカツキは天宮から少し離れたこのデネブ星まで毎日足繁く通っているのである。
「ナユタ、今日も何も変わりないか?」
「うん、いつも通りだよ。たまに魔物が侵入したりするけど、うちの兵達がすぐ片付けてくれるし国は平和そのもの。星と俺を繋いでる柱も問題ないよ」
そう言ってナユタは満面の笑顔をアカツキに見せた。
「どうした、そんなに嬉しそうにして」
ナユタは笑顔でいるのが常だが、今日はいつもに増してニコニコとしている。思わずアカツキが問うと、ナユタは自分が無自覚でそのような顔になっていたことに気付いて「えっ」と小さな声を上げた後
「あはは、なんでかな……なんか、アカツキが俺のことを気にかけてくれるのが嬉しいんだ。想われてるんだなあって、そう思うのは自惚れかな」
と言って今度は照れくさそうに笑うのである。
そんな彼につられてアカツキも笑みが零れた。
「自惚れなどではないよ。私はナユタのことを何よりも大切に想っているのだから」
アカツキは手を伸ばし昔よくしてやったようにナユタの頭を撫でると、ナユタは気持ちよさそうに目を細めてそれを受け容れている。
あの頃はまだ小さかったナユタは、いつの間にか自分の背をゆうに越えてしまっていた。彼を創った親として、そして恋人として、アカツキはナユタの成長を実感し嬉しそうに微笑んだ。
「大切に想っているからこそ、私はふと、お前の実態を思い出しては心配で仕方なくなってしまうんだ。お前が、私の研究の成果の第一号である、ということが」
「それは随分前にアカツキから聞いたけど……でも、俺自身は全然なんともないけどな」
ナユタ自身も、自分が星の核であるということは既に聞かされていた。星の核であり、その核が結晶化したものが自分の心臓の代わりとして胸に存在している。脳内には常にこの星の記憶や人々の歴史が流れ込んでくるし、他の星の核が担っている役割を自分の中のこの結晶が常にこなしているのだ。
普通の星の精であれば、常にそのような膨大な情報量が頭に入ってくるなどという状況、とても耐えられるものではない。しかしナユタの体はその結晶が創り出したものであるため、並大抵のことは耐えられるようになっている。
星の核である結晶を守るために創られた体は、傷ついても驚異的な再生力で瞬時に回復し、星の力の源でもあるために呪力も無尽蔵。攻撃を受けても支障はない。まさに無敵の体なのだ。
「だから心配しなくても大丈夫だって。なんてったって、俺のことは天才アカツキ様が創ってくれたんだからな!」
そう言って笑うナユタの笑顔を見て、アカツキもつられて微笑んでしまう。そして、不思議と胸の内でもやもやとしていた不安が消え去っていくのを感じていた。
――そうだ、この子は私が創った星の子なのだから、大丈夫……
アカツキは目を閉じてそう自分に言い聞かせる。すると、そんなアカツキの手に何か温かいものが触れた。少し驚いて目を開けると、それはナユタの手だということがわかる。
「昼飯、食った?俺まだだから腹減っちゃって……アカツキもまだだったらどこか食べに行こう」
アカツキの手を握り、今にもどこかへ連れて行かんとナユタはそのまま手を引いていこうとする。
「あ、ああ……そういえば私もまだだった。そうだな、ナユタの好きな店にでも連れて行ってくれ」
「それなら、この間新しくできたレストランがあるんだ。結構評判いいみたいだから気になってたんだ、そこへ行こう!」
ナユタの手の温もりを感じ、いつまでもこんな幸せな時間が続いて欲しい……と、アカツキは心の中でそう祈るのであった。
あの時のなんともいえない不安は、きっとこの事件の前触れだったのだろう。
毎日欠かさずデネブ星へ通っていたアカツキであったが、その日アカツキは三徹した結果、天宮の廊下で行き倒れ爆睡しているところをシアンに発見された。
徹夜が続いたアカツキがこのように天宮内で行き倒れているということも最早珍しくはないので、シアンはいつものようにアカツキを彼の部屋に運び込み、そのまま寝かせてやっていた。
アカツキは夢を見ていた。
自分の創ったデネブ星が、壊れていく夢。
アカツキは荒廃と化したデネブの街を走りながら、必死にナユタの名を呼び彼を探す。
火が燻る建物。瓦礫の下敷きになり息絶えている人々。
一体誰が、どうして、ナユタが守ってきた、ナユタの大切なこの国をこんなにしたのは、一体……
その時、アカツキは強い星の力を感じた。
自分でさえ押し潰されそうなほどの、とてつもない力がこちらに迫ってきている。
――……まさか……!!
「ナユタ!!」
アカツキは叫び、そして同時に目を覚ました。
視界に入ったのは先程の荒廃したデネブの街ではなく、見慣れた自分の部屋の天井だ。
「……ああ、またシアンが運んでくれたのか……」
確か、資料室へ本を探しに行こうとしていたところまでは覚えているのだ。その後の記憶がないので、おそらくそこで力尽きたのだろう。
それにしても、嫌な夢だ。
アカツキの体は嫌な汗で濡れていた。一度風呂にでも入ろう、と思ったその時、アカツキの部屋の扉を叩く音が聞こえた。
「誰だ」
「シアンだ。入るぞ」
扉を開けて入ってきたのは、倒れていたアカツキを部屋まで運んでくれたシアンだった。手に水を張った洗面器と手拭いを持っている。
「随分とうなされているようだったから……酷い汗だ。ひとまずシャワーでも浴びて着替えろ」
「ん……そうする」
アカツキは手渡された手拭いで顔を拭った。ひんやりとした感触が心地いい。
「着替えたらもう一度ちゃんと寝ろ。何日寝てないのか知らないが、いくら天星が半不死とはいえ体を壊すぞ」
「……ちなみに、私はお前に運ばれてから何日寝ていた?」
「丸二日だ。よっぽど疲れが溜まってたんだろ」
そういえば、毎日の天宮での執務に自身が趣味でやっている研究、それからデネブへ通うという生活を続けていて、明らかに時間が足りないのを感じていたのだ。更にここ最近は多くの星で戦争が多発しており、死者が絶えない。「記憶」を司るアカツキは記憶を人々の「人生」として管理もしている。「死」を司るアヌビスとの仕事も多忙を極めていた。
「二日も仕事を休んでしまったからな、アヌビスは怒っているかな」
「呆れてため息を付いてたぞ。仕事は天帝様とこなしていたようだから、問題はなさそうだったが……」
シアンが再び手拭いを絞りながら説教混じりに話していると、突然部屋の外が騒がしくなった。
誰かの足音がこちらへ向かってくる、とアカツキが思った瞬間、勢いよく自室の扉が開かれた。
「おい!アカツキは起きたか!?」
入ってきたのはアヌビスだった。肩で息をし、慌ててこちらへやってきたのだろう。あのいつも冷静なアヌビスが珍しくここまで取り乱すということは――
「何かあったのか……?」
アカツキは自分の胸の中で嫌な予感がざわめくのを感じながら、恐る恐る彼に尋ねる。
これが、つい先程まで見ていた夢であればどんなによかっただろうか。
アヌビスの話を聞いたアカツキは、急いでデネブへ向かっていた。
――デネブ星の死の気配が強まっている。
敵襲か?内乱か?
二日前にデネブを訪れた時は、ナユタの周りにいる側近達も普段と変わらず、平和に仕事をこなしていた。それに、誰かがよくないことを企てていたとしても、人々の歴史を自身の核に記録し続けているナユタがすぐにそれに気付き処理してきた。内乱という可能性は低いだろう。
「となれば、敵襲……?」
デネブは天の川のすぐ近くに存在している星である。
天の川は、アヌビスが送り出した死者の魂が集う場所であり、そこでフローの生の力が魂を拾い上げ、再びヒトとしての生を受ける、「百の巡り」が行われているのだ。故に天帝と三神星の三人以外が近付くことを許されておらず、近辺は特殊な磁場が発生している。
デネブは夏の大三角――ベガ、アルタイルとトライアングルで並ぶことによってまた別の地場を発生させ天の川の磁場の影響は受けないようになっているのだが、時折他の小惑星等に住む者達が磁場の影響を受け、他の星に襲いかかるという奇行に走ることがある。
天の川のすぐ近くに存在するデネブは、頻繁にそれらの襲撃を受けることがあった。故にデネブの宮殿には戦闘に長けた兵達も数多く生活しているのだ。
とはいえ、今まではちょっとした小競り合いで済む程度の襲撃。アヌビスがあそこまで血相を変えるほどの死者の数が出ているということは、ただの敵襲ではないのだろう。
「ナユタ……皆……無事でいてくれ……!」
そう祈り続けていたアカツキであったが、デネブに降り立って目に映った光景は、まさに先程まで夢に見ていたあの地獄のような光景だった。
街の建物は全て大きく破壊され、たくさんの人々が倒れている。皆、おそらくもう息はないだろう。
宮殿からも至るところから煙が上がっている。
「……どうして、こんなことに……」
アカツキが絶句していると、近くで人の呻き声が聞こえた。
「う、うう……」
「!誰かそこにいるのか……!」
声の聞こえた方へ駆け寄ると、いつもナユタの傍に仕えている側近がひとり、酷い怪我を負って壁に寄りかかっていた。
「あ、アカツキ……さま……」
「待っていろ、すぐに回復させる……!」
アカツキは怪我をしている彼の体に回復の呪術をかけるが、彼の怪我は思っていたより酷く、回復を専門としない自分の呪術では彼を救うことはできない、と察した。
しかし、これはおそらく自分達と同じ、呪力を用いた力で受けたものだ。呪力を用いるということは、この国を襲ったのは星の精かあるいは別の精霊の類だろう。
「喋れるか?すまない、一体何が起きたのか……敵の数、それから現在どこへいるのか、分かる範囲で良い、教えてくれ」
アカツキが尋ねると、彼は何やら言いにくそうに口を閉ざしていたが、次第にぽつりぽつりと、これまでにあった出来事を話し始めた。
「……ナユタ様、です……」
「!ナユタが……!?何故…!」
彼の答えに、アカツキは思わず叫んでしまった。
もしや、あの夢で見た、目が覚める直前に感じたとてつもないほどの星の力――あれは……
「……二日、前……ナユタ様が体の不調を訴えたので、早めに床についたのですが……翌日も、一向に良くならず……アカツキ様を呼びに行こうと、していたところ……ナユタ様の力が、暴走したのです……」
「……!」
「我々で、なんとかナユタ様をお止めしようとしたのですが……暴走したナユタ様の力に全く歯が立たず……ナユタ様は力を抑え込めないまま宮殿内、そして街中で暴れ……今はもう、どこへいらっしゃるのか……」
ナユタの星の力は感じる。おそらくまだデネブの外には出ていない。
気配を感じ取りながら、アカツキは彼の回復を終え、その場を立つ。
デネブは大きな星ではあるが、気配を感じ取れるということはまだそれほど遠くには行っていないということだろう。
すると、アカツキの傍の虚空が突然眩く光り始めた。これは星の精が星と星の間を行き来するために使う、転移術の光だということにアカツキはすぐに気付く。
案の定、消えた光の中から現れたのはシアンだった。
「シアンか……お前が来たということは……」
「天帝様からの勅命だ。ナユタの力が唐突に大きくなったことによって一部の力の均衡が崩れようとしている。お前と共にそれを食い止めろと……しかし、これは一体……」
シアンは崩壊したデネブの街を見渡し、唇を噛んだ。
あれほど美しかったデネブの国が、とてつもない星の力によってここまで壊されてしまったのだ。
「生きているのはそこの……いや」
生存確認をしようと、アカツキのすぐ傍で重傷を負っている兵をちらりと一瞥したシアンだったが、すぐに口を噤んだ。だが、彼はシアンが何を言おうとしたのか理解しているようである。
「シアン、様……おそらく、今この国で生きているのは私のみ、かと……宮殿の私達の同僚も、街の人達も……皆、もう……」
そう話す彼の呼吸も次第に荒くなっていく。やはり、アカツキの回復術だけでは彼を助けるまでには至らなかったのだ。
天帝から勅命が下った時、人の命の選定をする権利を得るシアンも、彼の命がもう間もなく尽きるということが視えていた。だから先程生存者の確認をしようとして、口を噤んでしまったのだ。
「……すまない……」
「……はは、あやま、らないで……くださ……はやく、ナユタ様を……」
悔しさを滲ませながら謝罪するアカツキを見、彼は微かに笑った。そして最後の力を振り絞って言葉を紡ぐとゆっくりと目を閉じ、彼はそれきり動かなくなってしまった。
「……デネブ星、ヒトの生命反応なし。天帝様がロキを寄越さず俺とお前だけを選出したのは、こういうことだったのか……」
「……っ!」
シアンの言葉を聞き、アカツキは勢いよくその場から走り出した。慌ててシアンもその後を追う。
「待てアカツキ!敵を把握しているのか!?場所は!?」
「敵は……ナユタだ」
「!なんだって!?」
確かに天帝は、ナユタの力によってこの宇宙の一部の因果が狂おうとしていると言っていた。しかしまさか、ナユタが自身の街を、国を、星をこんなにしてしまったなど、シアンは信じられなかった。
「場所はわからない。さっきの側近が言うには、力を暴走させたナユタは宮殿と街中で暴れた後どこかへ向かったらしい。とりあえず今はナユタの気配を追ってみている」
「しかし、なんだってこんなことに……ナユタは星の核そのものだろう?核が力を暴走させるなんて、聞いたことがないぞ」
シアンの言うとおりだ。天帝がこの宇宙という世界を創造してから現在まで、天帝や自分達天司十星、そして他の星を生み出す権利を持った星の精達がたくさんの星を生み出してきた。
フローの生命エネルギーを大元として創られる星達は、その核に膨大な力を抱えてはいるが、決して自分を壊したりしないよう、その力を制御するようにフローの力によって厳重に守られている。
――そのはずだった。
「……多分……私が核をいじってしまったせいだ」
アカツキは唇を噛み締め、呟いた。
「私が核を結晶化してしまったことで、核に元々施されていた複雑なメカニズムが狂ってしまったんだろう……これは全て、それに気付かなかった私の過失だ」
この計画に関して、時前に多くの下調べをしたはずだった。フローやロキにも相談したり、何度も試行錯誤を重ね、これなら問題ないという確信を得てから実行したはずだった。
しかし何事にも「完璧」は存在しない。
アカツキのこの計画には、一つだけ小さな欠陥があったのだ。アカツキはそれを見落としてしまっていた。寧ろ、ナユタが誕生してから今まで何事も起こらなかったのが奇跡だった、というより他ない。
「……」
アカツキの心境を察し、シアンはかける言葉を失ってしまう。
つまり、アカツキは自身の過失のせいで自身の大切な人を苦しめてしまった。そしてその大切な人が大切に思い、守ってきたこの国を、自身で破壊させてしまったのだ。
もし仮にナユタが正気を取り戻した時、果たしてナユタはこの変わり果てた己の国を見て何を思うだろうか。
そう考えただけで、アカツキの胸は張り裂けそうなほどに痛んだ。
「!近い!」
街から少し離れた森に差し掛かった時、アカツキは巨大な星の力を感じ、叫ぶ。
同じくシアンも、天司十星である自身が圧倒されそうなほどの大きな力を感じていた。普段のナユタから感じ取れる力の数千倍以上に肥大化した力が、すぐ近くにいる。
ここをナユタが通ったのだろう、あれだけ鬱蒼と生い茂っていた森の木々は、まるで山火事にでも遭ったかのように全て燃え尽くされてしまっている。
そしてそれはすぐに目の前に現れた。
「……っこれは……」
アカツキは思わず息を呑んだ。
この森の中心には、巨大な湖があったはずだった。
とても静かで綺麗な湖で、アカツキが何度もナユタと二人で訪れた場所だった。
その湖の中に、苦しみもがくナユタがいる。湖の水はナユタが暴走させている力によって全て蒸発してしまっていたのだ。
アカツキの持つ力は「火」の属性。アカツキは当時己の力を結晶に込めており、ナユタが暴走させているのは星の持つ無尽蔵の呪力で肥大化した火の力なのだろう。
「う……ぐ、あぁ……っ!」
「ナユタ!まずい、このままではデネブが丸ごと焼け消える!早く止めなければ!」
ナユタの様子を把握したシアンはすぐにナユタに近付こうとするが、同時にアカツキに勢いよく腕を引かれる。すると今までシアンがいた場所に巨大な火の刃が走った。あのままそこにいたら、間違いなくシアンはその刃の餌食になっていただろう。
「す、すまないアカツキ、助かった!」
「迂闊に近づかない方がいい!あれは星の核……己が壊されないよう防衛機能だけはまだ正常に稼働しているらしい……厄介だな……」
つまり、ナユタを止めようと近付いたり攻撃をしかけたりしたものなら、星の防衛機能が働いて暴走し数千倍にも跳ね上がったナユタの星の力がこちらに襲いかかってくるのだ。手も足も出ない、というのは、まさにこのことを言うのだろう。
とはいえ、このまま見ているだけではいられないのだ。暴走するナユタの力は収まる気配がなく、更に威力を増していく。アカツキとシアンは、ぐらりと地面が大きく揺れるのを感じた。
「っだめだ、アカツキ……このままではこの星はスーパーノヴァの段階に入るぞ!そうなるともうデネブという星は永久になくなってしまう……天帝様の勅命はそれを止めることだ、どうする……!」
シアンが叫ぶが、アカツキは険しい顔で何かをぶつぶつと呟いていた。
「どうすればいい……一時的に防衛機能を無効化させることはできる。だが、この暴走を止めるには……くっだめだ、やはり再構築しかないのか……!」
アカツキは切羽詰まったように叫ぶ。
アカツキが見落としていた欠陥は本当にごく僅かな、たった一つの欠陥だったのだ。しかし、それを修復するには核を結晶化する前の段階まで戻さなければならない。
つまり、ナユタの中の結晶を破壊するしかない、ということだ。
それは同時に、ナユタの死を意味する。ナユタを止めるためには、この星を救うためには、ナユタを破壊するしか方法がないのだ。
そしてその方法も、ナユタを創ったアカツキにしかできない。
(愛する者の命を、自らの手で奪わねばならないということか……好奇心で命を弄んだ私に対する罰なのだな、これは……)
「アカツキ、危ない!っぐあ……っ!」
「!シアン……!!」
アカツキはナユタの攻撃が目前に迫っていることに気付いていなかった。
急いでシアンがアカツキを庇うが、シアンは背に攻撃を浴びてしまう。
「シアン!シアン、大丈夫か……!すまない、私のせいで……!」
「っこれくらい、どうってことないさ……いいから、ひとまずここから離れて体勢を立て直そう。あの状態ならスーパーノヴァに入るまでにはまだ多少の時間がある。作戦を立て直すんだ」
「……わかった……」
ナユタを失いたくない。しかしこのままでは、デネブという星が丸ごと消えてしまう。
人命は絶えてしまったが、星さえ残っていればまた新たな生命が生まれ、そこからまた今までのように星が繁栄を取り戻す可能性だってあるのだ。その可能性すらなくしてしまうわけにはいかない。
後ろ髪を引かれる思いで踵を返そうとすると、アカツキの頭の中に聞き慣れた、愛しい人の声が響いた。
『――アカツキ……!』
「……ナユタ……?」
アカツキは反射的に後ろを振り返る。
そこには未だ力の暴走に苦しみ我を失っているナユタの姿がある。しかし、頭の中に響いてくる彼の声は直に聞こえてくる呻き声とは別に、はっきりと、そして妙に晴れやかに聞こえるのだ。
まるで、何もかも吹っ切れたかのように。
「……アカツキ?」
「……ナユタの声が……聞こえるんだ……」
どうやらシアンには彼の声は聞こえないらしい。アカツキを見つめ、不思議そうに首を傾げている。
星の精達は「意思」を司るルピナスの力によって、声に出さずともある程度脳内で意思疎通を取ることができるようになっている。おそらくこれは、ナユタに残された最後の理性がアカツキに送っている言伝なのだろう。
『アカツキ……ごめん、俺、アカツキが創ってくれたこの星をこんなにしちまった……国の人達も皆……俺のせいで……本当に、ごめん……』
「何を言っているんだ……!お前は何も悪くない!悪いのは……悪いのは、私だ……全部、これは全部、私自身が招いたことなんだ……!」
星の核に意思を持たせたらどうなるだろうという己の些細な好奇心から生まれたナユタ。
その段階でほんの僅かな、しかし重大な欠陥に気づけなかったというミス。
そして、ナユタが体の不調を訴えていたという二日前に、自身は不摂生な生活がたたって呑気に眠り続けてしまっていたこと。
きっとその二日前のナユタの不調に気が付いていれば、このような最悪な事態を回避することもできたかもしれない。
しかし、ナユタはそんなアカツキの思いを全て見透かしたかのように笑い飛ばした。
『はは、何言ってんだよ。だってアカツキがその研究を思いつかなかったら、俺はこうして生まれることはなかったし、星に住む皆と楽しく過ごすこともできなかっただろうし……何より、アカツキを好きになることもできなかったんだ。俺はアカツキのお陰で自由を手に入れて、幸せだったんだ……だからさ……』
その声色から、ナユタが今どんな表情をしているのかアカツキにはすぐにわかった。そして、何を言おうとしているのかも……
『俺、アカツキが創ったこの星を失くしたくない。だから、俺を壊してくれ、アカツキ』
「……っ」
ナユタのその言葉は、アカツキが予想していた通りだった。
アカツキが創ってくれた自分を、自分の星を、国を守りたい。それ故に、今この星の脅威となっている自身を破壊してくれと言うのだ。
実際、このデネブ星の消失を防ぐにはもうその方法しか残されていない。
「……だが、私は、お前を……」
――失いたくない……
そう呟こうとした瞬間、今まで激しかったナユタの力が一瞬静かになった。そしてまるで春風のように暖かい風がアカツキの体を包み込む。
まるで、ナユタが抱きしめて、口付けてくれたかのような――
『頼む、アカツキ……俺の、最期の願いだ。この星を……アカツキの星を、守りたい……』
そしてナユタの声は風が過ぎ去るかの如く、遠のいていった。
「……」
「……アカツキ……?ナユタが何か言ったのか……?」
シアンがアカツキの顔を覗き込むと、アカツキは静かに涙を零していた。あの、いつでも強気で気丈に振る舞い、弱った表情を決して誰かに見せようとしないアカツキが泣いているのだ。
シアンが驚いた表情で自分を見ていることに気付いたアカツキは慌てて涙を拭うと、すぐにいつもの気丈な表情に戻る。
「シアン、この星を守るぞ。まだ体力に余裕があるのであれば、援護してほしい」
「わ、わかった……」
アカツキは己の胸の前で両手を向かい合わせる。すると向かい合わせた両手の中央に光の球が創られた。アカツキがそのまま両腕を広げると、その球は眩い光を放ちながら一本の槍に形を変える。
「ナユタの器は、私の持つ力……変化と創造の力で構成されている。星の核には己が破壊されないよう、その力を最大限に活かしてどれだけ器に傷をつけられても驚異的な再生能力で傷を修復する。それがナユタの体の、不死身の由来だ」
「それは前も聞かされたが……しかしそれでは、いくらナユタを破壊しても埒が明かないんじゃないのか……?」
シアンが問うと、アカツキはその問いに不敵な笑みで返した。先程創った槍の先でコツコツと地面を突き、いまだ苦しみ続けるナユタと向き合う。
「私を誰だと思っている?天司十星一天才のアカツキ様だ。自分で創ったものの始末くらいできなくてどうする」
そう言うと、アカツキは槍を構え勢いよくナユタへ向かって走り出した。
案の定ナユタの中の結晶が防衛機能を稼働させ、こちらへ向かってくるアカツキへ攻撃をする。
攻撃がアカツキにぶつかろうとしたその瞬間、シアンの力によってナユタの力は霧散した。
「全く、そういうことか……俺の千里眼が完全に「現在」しか視ることができないものだったらどうするつもりだったんだ……」
アカツキの少し後方でため息をつきながら、シアンはぼやいた。
シアンは秩序を司る星の精。秩序を乱すものを監視する為にこの世の全ての「現在」を視る千里眼を持っている。
千里眼には現在を視るものの他に、未来視や過去視の類も存在するが、シアンが持っているのは「現在」を視るもののみ。だが、秩序を乱す可能性のあるものが近ければ近いほどシアンの千里眼の力は強力になり、多少の未来視も可能となるのだ。
どこから飛んでくるか予測不能な星の防衛機能による攻撃を、シアンが未来視で視て攻撃を相殺する。その合間を縫うように、アカツキは少しずつナユタに近付いていった。
同時に威力を増していくナユタの星の力の圧力を、アカツキは手に持っていた槍で薙ぎ払っていく。
「ニグレドの槍だ。もうお前の力は私には効かないぞ、ナユタ」
ニグレド――錬金術の賢者の石錬成の第一段階。腐蝕、死の段階といわれている。
アカツキが今手に持っているその槍はナユタの核の結晶と同じ性質のもので現在はニグレドの段階であり、触れたものを死の状態へ戻す力を持っている。
ナユタの攻撃はアカツキの力が暴走したもの。ニグレドの力でそれらは全て無効化してしまうのだ。
つまり、この槍でナユタの中の結晶を貫けば……
「ナユタ!!」
目前まで迫ったアカツキに向かって、既に理性などとうに失くしたナユタが自ら襲いかかろうとする。しかしアカツキはそれを槍で軽くいなし、そのまま彼を地面に押し倒してその上に馬乗りになった。
そして……――
「……っ……」
槍は、彼の左胸を一突きに貫いた。
同時、今まで周りを取り巻いていた強い星の力も瞬時に霧散する。
「は……っはぁ……は……ナユタ……」
槍をナユタの胸に突き刺したまま、アカツキは荒い呼吸を繰り返す。
ナユタは口から血を流し、徐々に光を失っていく瞳でずっと、アカツキを見つめていた。そして、微かに唇を動かし、彼は呟いたのだ。
「……あ……りが、とう……アカ、ツキ……あいしてる……」
アカツキは目を見開いた。そして彼の名を呼ぼうとした瞬間、ナユタの体は弾けるように大量の光の粒となって消える。
残されたのは、アカツキの槍によって砕かれ黒に変色した賢者の石だけだった。