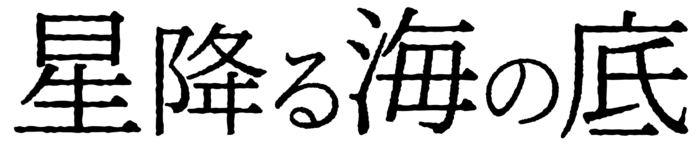夜明けに眠る欠片
確かに、シリウスの言う通りだった。
初めて見た。“彼”のことは初めて見たはずなのに、視界にその赤をとらえた時、胸の奥から熱いものがこみ上げてくるのを感じた。これは間違いなく「懐かしい」という感情だ。
「……ナユタ……?」
己の唇が無意識に紡いだ、遥か昔に封印したはずの彼の名を慌てて呑み込む。
彼の隣にいるのは、きっとデネブの妖精長なのだろう。二人は初めて訪れた天宮にわくわくしているのか、向かいに立ち尽くしている自分のことに気付くことなく、そのキラキラした眼差しをあちこちに向けている。
そうだ。気付かなくていい。その為に封印という名の消去をしたのだから。
あの眼差しを見れば、“彼”が過去に自らの星で起こしたこと、起きたことを思い出した時、彼は間違いなく傷付くだろう。
それだけは、そんな思いだけは絶対にさせたくない。させてはいけない。
ふ、と自嘲気味に笑うと、談笑に夢中になっている二人の横を風のようにすり抜けていった。
「……」
「……?どうしたの、鴫」
急に感じた懐かしい風に、鴫は思わず足を止めた。
いや、ただ懐かしいというだけではない。この胸に燃えている賢者の石が、星の核が、自分に何かを訴えかけているようにざわめいているのだ。
足を止め、振り返った先には既に自分達から遠のいて小さくなってしまった人影があった。とても珍しい、まるで暁の空のような美しい髪のひとだった。
「あの髪色は…多分、天司十星のアカツキ様だね。いけない、すれ違ったのに気付かなかった」
自分の隣で少し焦ったようにそう話すのは、自分の星を自分と共に守ってくれている、デネブ国妖精長の響。
真面目で几帳面なところがあるので、自分より遥かに身分が上の人物とすれ違ったのに全く気付かず、挨拶ができなかったことを気にしているようだった。
「アカツキ……か。あのひとが……」
鴫は、彼の名前だけは聞いたことがあった。
シリウスと同じ、天帝に創られた最初の十人の天星の内の一人「記憶」を司る星の精なのだという。
任務以外であまり星に降りることがない上に、彼が請け負った任務の関係者は大体が罪人のため彼に断罪されてしまっている。そのことから彼の素性は世間にあまりよく知られておらず、謎の多い天星ということで名が知れ渡っていた。
だが……――
「なんでだろう……俺、あのひとのこと何も知らないはずなのに……なんだかすごく、懐かしい感じがしたんだ……」
いまだざわめき続ける胸を抑えながら、もう誰もいなくなった廊下の奥を見つめ、鴫は夢でも見ているかのように呟くのだった。
どうしても彼のことが気になった鴫は、それからシリウスにかけあってもらい、なんとかアカツキと対面する機会を与えられた。
実際に対面してみると思っていたより気さくなひとだった。
罪人を容赦なく断罪すると聞いていたから、てっきりアヌビスのような人物かと思っていたのだけど。というのを思わず口に出してしまった鴫はアカツキに笑われ
「アレらは私達にとっての敵だからな。天星……特に天司十星は敵に情けをかけるようなことはしてはならないのさ」
と返された。
確かに、普段は穏やかなシリウスも強敵を前にするとどんな相手であろうが容赦はしない。天司十星とはそうあるべきだ、と遥か昔から天帝に教え込まれてきたのだろう。天星と自分達星の子の見ている世界は違う、とも言われているし。
ひとまずそこでは、響がすれ違ったことに気付かず挨拶ができなかったことの非礼を詫び、アカツキは
「なんだ、そんなことを気にしていたのか」
と苦笑し、別に全く気にしていないさ、と付け加えて二人に手を伸ばし、握手を求めた。
「また機会があれば。よろしく」
そして握ったアカツキの手の温もりに、鴫の胸はやはりひどくざわめくのだった。
◆◆◆
それから少し経ったある日、響は宮殿の書庫の書物を読んでいてふと気付いたことがあった。
響は錬金術に関する才能はずば抜けているのだが、それ以外の分野――特に歴史に関してはとても疎かった。
幼い頃はずっと家に引きこもっていたし、その間勉学は母親の泡沫が教えていたのだが、その泡沫も主に錬金術学を専門としていたために歴史に関しては必要最低限のことしか教えられなかったらしい。下手をすればこの世のありとあらゆることを知っている隣国アルタイルの妖精長、凪よりも自国の歴史を理解できていない可能性がある。
そのため、響は長となった後改めてこの星のことをちゃんと知ろうと思い、宮殿の書庫の歴史書を片っ端から読み漁っていたのだ。そしてある疑問に気付く。
「……この星……誰が創ったんだ……?」
普通、デネブのような妖精国、また魔力を持ち星の精を主と仰いでいる人間界では、大概の歴史書にはどのような星の精が星を創ったのか、そこは必ず明らかにされている。
例えばアルタイルは天司十星のルピナスが創ったと言われており、もうひとつの隣国であるベガは天帝が手掛けた数少ない星であると言われている。
だがデネブだけ、創造主の名がどの本にも記載されていないのだ。
「……うちはベガやアルタイルに比べると若い星ではあるけれど……となれば、歴史を逆算するとこの天の川銀河の統括者が天帝様からシリウス様に移った後に創られたことになる。でも……それなら創造主はシリウス様になるはず……ではないのかな」
響は本の文字を指で追いながら首をひねる。
天の川銀河をまだ天帝が統括していた時代。その頃の天の川銀河やその近辺の銀河は、さながら天星達が星を創る練習場のようなものだったとシリウスから聞いたことがある。ひとつの銀河を統括する者がその銀河内で星を創ることが原則とされているが、そういうことであれば、シリウスに統括権が移った後に創られたらしいこの星の創造主はシリウスとなるのが自然だろう。だが、そういったことが書かれている文献はひとつもない。
「……鴫なら……賢者の石なら知ってるのかな」
一度疑問に感じると、それは解決するまで響の頭につきまとう。
賢者の石――星の歴史と記憶を誕生から現在まで休むことなく刻み続けている星の核であれば、と響は思った。
すると同時に書庫の扉が開く音が聞こえ、聞き慣れた心地よい声が耳に届く。
「響ー?いるか?」
「鴫。僕はここだよ」
本棚にかけられた大きな梯子に腰掛けていた響は、慣れた動きで梯子から降りると鴫のもとに駆け寄る。
「また上でそのまま本読んでたのか?危ないから降りろって言ってるのに……」
「あはは、いくつも読んでると片付けに行くのが面倒になっちゃってね……高い場所にあるのは特に」
「ったく、変なところズボラだよなあ……ほらこれ、凪に前頼んでたお茶」
そう言って鴫が小さな包みを響に渡した。
「わあ、もう用意してくれたんだ、凪はまめだなあ……丁度いい時間だし、休憩しようか。鴫に訊きたいこともあったし」
読みかけの本と鴫から受け取った包みを抱え、響は書庫を足早に出る。鴫はそんな響の後を慌てて追いながら彼の言葉に首を傾げた。
「デネブ星の創造主、か……そういわれると、全然聞いたことがないな……」
ティーカップの中で広がる見たことのない花を見つめながら、鴫は響の疑問にぽつりと答えた。
「えっ、鴫も知らないのかい?デネブ上層部の企業秘密とかじゃなくて?」
「う、うん……特に秘密にしていたわけじゃなくて、俺も全然知らないんだ。星の歴史にも残っていなくて」
誕生の時まで歴史を手繰り寄せても、己を創った人物の姿は名前すら出てこない。昔、先代が疑問に思ってシリウスに尋ねたことがあったらしいのだが、彼は「少なくとも、君を創ったのは私ではないよ、と答えることしかできない」と少し困ったように話した記録が残っていた。
誰も知らない。どの書物にも残されていない。星の歴史からも、まるでその部分だけが存在していないかのようになくなっている。
そして、シリウスの言葉の意味……――
「……これって……七海と鶲の時みたいだ」
「え、それって、ベガとアルタイルの過去のやつだよな……?」
響の呟きに、鴫はきょとんと彼を見つめる。
七海と鶲とは、少し前にベガとアルタイル間で起きた事件の関係者だ。
七海はベガの初代星の精、鶲はアルタイルの初代星の精であり、二人は互いに愛し合っている仲であった。
しかし、七海の持つ五行術の力が七海の心に強く影響するという性質を持つため、七海は生まれたときから鶲に出逢うまでは心を持たなかった。だが鶲と出逢った後に心を芽生えさせてしまい、五行術は七海の万華鏡のように移り変わる心の影響を受け、星を繁栄に導く良い力から、宇宙をも滅ぼしてしまう程の負の力に変わってしまう。最終的に宇宙を脅かす存在となってしまった七海は自ら天帝に封印される道を選び、そして鶲はそんな七海を助けようとして禁術を使い、天帝から制裁を受け消失。後に七海もひっそりと消失した。
天帝は自身の孫娘が引き起こしてしまった世界の危機という事実が後の世に残らないようにと、この世に存在する最高位の術をもってそれらを消去したのだ。
それが天司十星、アカツキが持つ「記憶」の力である。
その力は、星の記憶や歴史を管理、監視するものであり、天帝の許可さえあればそれらを改ざん、消去することもできる。元々は天帝が持っていた力なのだが、自身の役割の負担を減らすためその力をアカツキに分け与え、現在は彼が役割としてその力を司っている。
しかしこの力の最大の弱点は「星の記憶と歴史をいじること」しかできないために、手を加えられたものの存在そのものを消去したりすることはできない。まるで歴史書のそのページのみを破り捨ててしまうようなもののため「そこに何かがあった」という跡だけは残るのだ。
現に鶲はアカツキの力で記憶と歴史を消去された後も念としてつい最近までずっとアルタイルに留まり続けていたし、七海も、七海の記憶を持ったベガの次代星の精、奏として生まれ変わっている。
根本から消し去ることもできなくはないのだろうが、おそらくそれは禁忌となるのだろう。
「デネブの創造主のことも……なんだかアカツキ様の力でそこだけぽっかりとなくなって穴が空いてしまっているみたいで……気になるな、って」
「うーん、今まで全然気にしたことなかったけど、そう言われてみれば確かになあ……」
鴫も小さく唸りながら首をひねる。そして同時、自分がアカツキに近付いた時に感じた石のざわめきを思い出した。あの時、アカツキの部屋で見たものは数々の実験器具や大量に積まれた書物ばかりだったが、よく思い出せばあれらのほとんどは錬金術に関するものばかりだった。石はそれに反応したのだろうか、と思ったりもしたが、同時に感じたなんとも言い難い懐かしさは、それでは説明がつかないだろう。
(賢者の石は、俺に何を伝えようとしてるんだ……?」
今まで、石が感じたことが理解できないなんてことは一度もなかった。石は自分自身であるし、心と同じようなものだ。それなのにあの時はまるで、自分の中に自分ではないもうひとりの何かがいるようだった。その「何か」が、心をあんなにざわつかせたのだろう。
「……あのひとと、もう一度話をしてみたいな……」
ぽつりと、鴫は天井を見上げながら呟く。けれど、自分はなかなか星を離れることができない星の精であり、そしてアカツキも別の銀河の統括をしている天司十星の一人である。多忙であることは間違いないし、あの時のように再び会って話をするのは難しいだろう。
「もし、この星を創ったのがアカツキ様だったら……ふふ、あの方ね、多分錬金術が大好きなお方だと思うんだ。錬金術のこと、色々話してみたい」
「あっ響も気付いてたか?アカツキ様の部屋にあったやつ!」
それから二人は、せっかくいれたお茶が冷めてしまうほどアカツキの話題に花を咲かせるのだった。
鴫の望みは、案外すぐに叶えられた。
――といっても、良い状況での再会ではなかったが。
◆◆◆
その日、鴫はいつものように今日の分のやるべきことを終え、この後は何をしようか、などと鼻歌を歌いながら宮殿の廊下を歩いていた。
「響もそろそろ仕事が終わってる頃だよな……うーん、今日はいい天気だし、弁当でも作って響と散歩にでも行こうかな」
そうと決まれば!と響の執務室へ足を向けようとしたその時、大広間へ続いている廊下の方が何やら騒がしいことに気付いた。
大広間は宮殿の出入り口のすぐ近くであるから騒がしいのはいつものことなのだが、これはいつもの喧騒とは違う、焦燥と動揺が混ざったような空気だ。戦闘部隊が多く集まるこの宮殿の中でこれほどの動揺が広がるなんて、と鴫は不思議に思い自然と足がそちらへ向かっていく。何しろブレウスの襲撃の時でさえ冷静に状況判断をし、動くことができていた重臣達だ。一体何があったというのか。
すると、近くで誰かと話をしていた樹が鴫の存在に気付いた。やはり彼からも普段とは違う焦燥感を読み取れる。鴫は自分の胸にも何やら嫌な予感が過るのを覚えながら樹の元へと向かった。
「どうかしたのか?何か騒がしいみたいだけど」
「し、鴫様……!それが……」
――宮殿の禁書庫に不審者による侵入があった
樹から報告を受け、鴫は急いで例の書庫に向かっていた。何故こんなに焦っているかというと、禁書庫は文字通り、普通の人は入ることができない書庫である。宮殿内の重臣達、また国が抱えている錬金術研究所の特別な研究員であれば鴫が響の許可を得ることで入ることが可能になるが、それ以外の者には決して入ることが許されない。
その書庫には国の機密事項が記載された書物のみならず、「あるもの」が記された書物も眠っているのだ。
「あ、鴫!」
禁書庫の前に辿り着くと、そこには既に他の重臣から事情を聞いたのであろう響がいた。
「響も聞いたのか?」
「うん、葉月から。禁書庫に侵入者があったって……これから中を調べるところ」
響はそう言うと、目の前の扉に手を翳す。すると光の魔法陣が扉に浮かび上がり、その魔法陣の色がわずかに変わって消えた。これがこの禁書庫にかけられている鍵の役割を果たしている。
「でも、こんなに厳重な封印術をかけてるのに一体どうやって入ったんだろう」
響は不思議そうに首を傾げながら、書庫の重い扉を開く。
確かに、彼の言うとおりである。
錬金術……特に魔術錬金術を取り扱っている国には必ずといっていいほど存在する「あるもの」を、星の精か長しか解くことのできない封印術をかけた書庫に厳重保管する必要がある。それが天帝からいいつけられている掟であり、どの国も天帝からそれぞれ異なる禁書庫の鍵となる封印術を教わっている。だからたとえ他の国の星の精や長が自分達の国の封印術で他国のその鍵を開けようとしても、鍵と鍵穴が異なる為に開けることはできない。
「鴫は最近、誰かにここに入る許可を出したことは?」
「ないよ。ここに入れる身分の人達は、ここに何があるかわかってるし……それに手を出すことが禁忌だってこともよく理解してるから、余程でない限りここに入る為の申請を出してくる人はいない」
そもそもそんな不届き者であれば、自分達に許可を求めるなんてことをしないだろう。そんなことをすればその後の問題が発覚した時に真っ先に疑われてしまう。
そんな、絶対侵入不可能な場所に何者かの侵入があった為に、宮殿の者達はあれだけ動揺していたのだ。
ひとまず書庫の中に足を踏み入れてみた鴫は、書庫内に異様な空気が漂っていることに気付く。
「俺が先に行く。響は後ろ、見張ってて」
小声で響に後方を任せると、鴫は物音を立てないよう、静かに本棚の間をしっかり確認しながら前へ足を進めていく。
いつもどおりの少し重々しい空気ではあるが、それに混じっている感じたことのない魔力。魔力源は一人ではない。複数犯か…?と鴫はゆっくりと書庫の一番奥の本棚へ近付いていく。そして……――
「……っ!」
その奥の本棚の前に辿り着いた鴫は、そこに広がっている光景に思わず息を呑んだ。
「っ鴫……これは……」
鴫の様子に気付いた響もすぐに現場を確認し、目の前の惨状に言葉を失ってしまう。
そこには何人もの死体が折り重なって倒れていた。そしてその背後にある本棚から、鴫が一番心配していた「あるもの」が全て消え去っていたのである。
まるでミステリー小説か何かのようだと思った。
外から入ることもできなければ、中から出ることもできない完全密室の書庫の中で倒れて息絶えていた人達。そして消えてしまっていた「あるもの」
「……あ、鴫。お疲れ様、何かわかったかい?」
書庫に残されていた遺体の解剖に立ち会っていた鴫が響の執務室を訪れたのは、もう既に夜も更けた頃のことだった。戻った鴫は尚も相変わらず不思議そうに眉間に皺を寄せていて、この分だとおそらく何もわからなかったのだろうな、と響は察した。案の定鴫は
「何もわからない……というより、寧ろ謎が深まった」
と響に伝えた。
鴫の話によると、遺体の数は全部で六体。全てここ、デネブ国の住人ではなく、皆それぞれ別の星国の者達だったのだという。そしてその人種も、人間であったり妖精であったり様々だった。
だが、一つだけ彼らに共通点があった。それは、彼らの死因は「失血死」だということ。解剖の結果、全員体内に一滴の血も残っていなかったというのだ。しかしこれもまた不思議なことで、失血死にも関わらず現場にはひとつの血痕も残っていなかった。まるで、何かに血を吸い出されたかのような……そんな不思議な遺体だったという。
「うわあ……なんだか地球に伝わってるヴァンパイア伝説みたいな事件だね」
「本当に吸血鬼の仕業ならまだマシだけどなあ……」
鴫の話を聞いて目をキラキラ輝かせている響を見、鴫は苦笑した。
「この事件、思ったより厄介な事件になると思う」
「……そう、だよね……」
鴫の言葉に、響は瞬時に表情を曇らせた。
遺体の後方の本棚は、主に魔術錬金術による「禁忌の錬金術書」が保管されている場所だった。そしてごっそり抜けていたのは、禁忌とされている錬金術の中でも最高位に値するもの。
「賢者の石錬成の錬金術書……これに関するものだけが全部、なくなってた」
賢者の石といえば、デネブの星の核である鴫のことだが、これはこの国の上層部だけが知っている機密事項となっている。しかし昔は今ほど厳しくデネブの星の精の正体を隠していたわけではなかったから、デネブの星の精の特徴が断片的に外部へ漏れ、そこから世界の錬金術師達へ「賢者の石」という夢のような物質が存在する、という噂が広がってしまった。
デネブの星の精は何者かの手で星の核が結晶化させられており、その結晶が自身を守るために器を形成することで存在している。呪力源は星の核故に無尽蔵であり、強力な変化と創造の力を持つため錬金術界における常識「等価交換の原則」を無視して錬成を行うこともできる。
そしてその器は星の核を守るために存在しているので、少しでも傷を負おうものなら驚異的な再生力でたちどころに直してしまうし、器が老朽化すると器を新たに作り変える。これまでデネブの星の精が器替えを行ってきて、鴫は四代目の星の精になる。
それが、世間に広まっている賢者の石の「不老不死の妙薬」の元ネタとなってしまっているらしい。
実際は、鴫にヒトの命を不老不死にできる力が備わっているかといえば、そんなことはない。
しかし噂だけがどんどん独り歩きしていき、賢者の石とは「願いをなんでも叶えてくれる万能の鉱物」という、錬金術師であれば誰もが喉から手が出るほどの欲しい伝説の物質となってしまった。
本来の賢者の石の正体を知っているデネブ国の上層部の者達からしてみれば「星の核をヒトが作るなんてできるわけがない」と理解しているから、そのような夢物語には一切耳を貸さない。
だが、そうではない錬金術師達はとにかくその賢者の石を作ろうとひたすらに研究に研究を重ねた。そしてとうとう、魔術による錬金術で賢者の石を錬成する方法が生み出される。
その方法は主に「変化と創造の力を持つ者の血」を錬成の材料とするといったもの。その必要量は一人や二人ではなく、その人一人が持つ魔力量にもよるが大体は数百人から、多くて数千人分の血を必要とする。
それだけ多くの犠牲が必要となるため現実的ではなく、またそれは天帝の定めた秩序を乱してしまう可能性が高いことから禁忌とされ、論理的な方法はあっても成功した者は誰一人としていない。実際に試した者も、天司十星達によって尽く断罪されている。
「あるもの」とはその、賢者の石の錬成法が記された書物のことである。これが魔術錬金術を取り扱う国にとって外に出してはならないものであり、こういった書庫に入れないような者達は賢者の石を錬成する方法を全く知らない。知っている者も、口外できないよう特殊な術を施される。
「被害者の身元が特定できないから定かではないけど、血が全部抜かれてるってとこから考えるとあの人達は全員、変化と創造の力を持ってる人だったんだろうな。だけど……なんで敢えて他国の人達をうちの禁書庫に連れてきて殺したんだろう……しかも、術書も奪ってる。方法を知らなかったのなら他国の人達を攫ってくるなんて方法思いつかないだろうし、知ってるならわざわざうちの術書を奪っていく意味がわからない」
鴫は腕を組んで首をひねる。
「星の記録から犯人を割り出せないのかい?他国の者であっても、ここへ一度入国してしまえば存在は君に刻まれるだろ?」
「うん、そのはずなんだけど……」
鴫は苦い顔をした。確かに響の言う通り、一度この星に足を踏み入れた者はデネブの者だけでなくとも星の核である鴫の中にその存在は自動的に記録される。しかし今回の事件に関しては、禁書庫に足を踏み入れた者の記録が何一つとして残っていなかった。
「ん……?そういえば、禁書庫に侵入者があったって最初に気付いたのは誰だ?」
鴫はふと、疑問点に気付く。これだけ何の痕跡も残さない者の侵入に気付くのは容易ではないはず。禁書庫に入るには鴫か響の許可が必要になるし、外から中の様子に気付くのも難しい。
二人共入室申請を受けていないのであれば、最初に異常に気付いた者が怪しいと鴫は思ったのだが、それに対して響が予想外の答えを返した。
「ああ、シアン様が樹に教えてくれたみたい。今は一度天宮に戻られてるけど、天帝様の勅命が下り次第またこちらへ来られるそうだよ」
「へ?ほんとに?」
まさかの天司十星の名が出たことで、鴫は驚きのあまり一瞬呆然としてしまった。
シアンといえば天司十星の内の一人で、彼は「秩序と正義」を司っている。彼は天帝が定めた宇宙の秩序を守り正すことを役割としており、現在視の千里眼を使ってこの宇宙の全てを監視している。そして秩序を脅かす者が現れれば速やかに天帝へ報告し、その者を排除しに向かう。所謂、宇宙界の警察のような存在だ。
これまでブレウスの襲撃以外大した問題が起きなかったデネブ国に、ついに天司十星のシアンが絡む程の重大事件が起きてしまった、という事実に鴫は少しショックを受けていた。
問題を起こしたのがデネブの者でないにしろ、その何者かにデネブの禁術書が奪われたのだ。そしてその禁術書に記されているのは、宇宙の秩序を狂わせてしまう魔術の類。彼が動くのは当然のことだろう。
一番の懸念は、シアンが関与した魔術錬金術を扱う国での事件では、必ずと言っていいほど多くの死者が出ること。話に聞いただけではあるが、実際にデネブと交流していた魔術錬金術国家のいくつかもシアンが関与するレベルの事件を起こしたことがあり、酷いところでは星の全人口の約半数もの命が失われたというところもある。
それ故に「死」を司るアヌビスより、シアンの方が「死神」だと言う者も多い。
だが実際にそれだけの死者が出るきっかけを作ったのは他ならぬ犯人に過ぎず、彼は秩序にしたがって犯人を追い詰め、それを断罪しているだけ。「死神」というのは単なる言いがかりに過ぎない。
しかし犯人を捕らえることは容易ではなく、勿論それまでに犯人によってさらなる被害が出てしまうわけで……具体的に言えば、魔術錬金術を扱う国での事件の大半は賢者の石絡みだ。その錬成に大量の人命が必要になるのだから、犯人を追い詰めるまでに多かれ少なかれ犠牲者が出てしまう。そしてそれは秩序によって定められているために、天司十星はそこまでは強く関与することを許されていない。
つまり、その犯人の行動によって犠牲になることが未来で定められている者は、その死から逃れることはできないのだ。
「……」
「鴫……」
シアンの名を聞いてから途端に険しい表情になってしまった鴫の心境を響も察し、何も言えなくなってしまう。
鴫が心配している問題。それはこの国の長である響も、長になった後に鴫からよく聞かされたことであるからわかっている。
宇宙の秩序が絡む程の重大事件が国で起きた場合、その国の星の精と長は何よりも人命を第一に配慮しなければならない。派遣される天司十星は秩序の定めによってヒトの命の選別を行う。その「定め」を少しでも変え、多くの人の命を救える未来に導けるのは、星の子とヒトである長の裁量にかかっているのだ。
「鴫、僕も頑張るから、一緒にこの国を……この国の人達を守ろう」
「響……」
鴫の手を取った響が、鴫の瞳を真っ直ぐに見つめ、まるで誓いを立てるように穏やかな声で話しかけた。
「シアン様がここへ来ることの意味……これから何が起きるのか、僕もちゃんとわかってるし、そのための覚悟だってしなきゃならない。少しだけ怖いけど……だけど、僕は長だからね。この国の人達の為に、一緒に頑張ろう」
そう話しながら、響は鴫の手を取る指に力を込めた。しかし、その指が少しだけ震えていることに鴫は気付く。
そうだ。星の精である自分だって怖いのだから、響の恐怖が「少しだけ」なはずがない。
シアンが動くということは、ブレウス襲撃の時以上に危険なことが起きるかもしれないということ。
あの時、たくさんの国民達が封印され、そして目の前で鴫が敵に攫われ、響はひどく傷付いた。
だがあのときの経験があったからこそ、大切な人達を失ってしまう辛さを知り…そして今度は必ず守り抜かなければならないと響は思ったのだろう。
「……そう、だよな!俺達が頑張らなきゃ……今度こそ、国の人達を守ろう!一緒に!」
「!うん……!」
響が握っていた鴫の手が、響の手を強く握り返す。そしてようやく奮起した鴫の目を見て、響は安心したように笑うのだった。
と、その時、二人の後方から小さな拍手が聞こえてくる。
「!?」
「おっとすまない、お邪魔だったかな。でもあまりにもいい決心だったからつい、僕も感動してしまったよ」
二人が音のした方を振り向くと、いつの間にか響の執務室の出入り口に三人の男が立っていた。
一人は先に以上を知らせに来てくれたシアン、もう一人、拍手をしていた男は二人も初めて見るが、その後方に隠れるように立っていた三人目は、先日二人が会って話をした天司十星、アカツキだった。