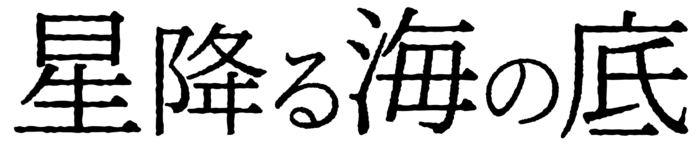夜明けに眠る欠片 2
「僕は天司十星のロキ。「知恵」の力を役割として司っている。今回の事件では参謀的なポジションでやらせてもらうよ、よろしく」
シャラン、と持っている杖を揺らし、先程おどけたようなことを言いながら拍手をしていた男は「ロキ」と自己紹介をした。
二人とも、その名前と彼の司っている役割についてだけは知っていた。ロキもアカツキと同じく、あまり世間では素性をよく知られていない謎の多い天司十星である。
「デネブ国星の精、鴫です。よろしくお願いします」
「僕はデネブ国妖精長、響と申します。よろしくお願いします」
少し緊張した面持ちで二人が頭を下げると、またも「まあまあ、そう固くならないでくれたまえ」と軽い口調でロキが言った。
「俺は天司十星の「秩序と正義」を司るシアンだ。よろしく頼む」
続けてシアンが簡潔に自己紹介をしてから、後方に立っているアカツキに目配せをする。するとアカツキは何やら少し落ち着かなそうな様子で目線をキョロキョロと動かし、
「私は……ついこの間彼らと話をしたから……」
と短く答える。アカツキのその様子にロキとシアンは何やら心当たりがあるようで、仕方がないとでも言いたげに眉を寄せながらもひとまず本題に入ることにした。
「とりあえず、天帝様とシアンから事情を聞いたけれど、もう少し詳細を知っておきたい。君達の方で調べてわかったことなどあったら、全部教えてくれないかな」
「あ、はい」
天宮で会った時とは全く違うアカツキの様子を不思議に思いつつも、鴫はこれまでに把握している事件の概要を全てロキに話した。
「成程……確かにこれは、賢者の石絡みで間違いなさそうだ。勿論被害者の身元を確認してみないことには100%とは言い切れないけれど」
「ああ。だが、状況から見てほぼ間違いないだろう。奪ったのがデネブの禁術書ということは、犯人は余程本気で賢者の石を完成させたいと見える」
ロキとシアンの話を聞いていた鴫と響は、不思議そうに顔を見合わせ、首をかしげる。
「あの……うちの禁術書ってそんなにすごいものなんですか……?」
鴫がおそるおそる二人に尋ねる。賢者の石の錬成法が書かれた書物なんて、魔術錬金術を扱う国であれば最低でも一冊は必ずといっていいほど存在している。
賢者の石の錬成法についての情報共有は星の精の間内であれば問題ないため、鴫は他国の錬成法も伝え聞いただけではあるが把握している。材料に多少の違いはあれど、どの国も共通しているのは「変化と創造の力を持つ者の血が必要」ということであり、それがなければ賢者の石の錬成はかなわない。
だから鴫は、何故敢えて犯人が自分の星の禁術書を狙ったのかがわからなかった。ただ賢者の石を錬成したいのであれば、それこそ自分の住む国の禁術書だって構わないはずだ。
すると、今まで後方でずっと一同の様子を見ていたアカツキがゆっくりと重い口を開いた。
「この国の錬金術技術はこの宇宙の中でも随一を誇る。故に禁術書の内容もな。この国のものは他のどの国のものと比べてもよく研究されている。あの術書に書かれている内容の通りにすれば……『賢者の石に近い賢者の石』の錬成成功率は非常に高いだろう……非常に癪だがな」
「は、はあ……」
最後に付け足された言葉と表情から、アカツキがそれに対して複雑な思いを抱いているのを鴫と響は感じ取った。その複雑な感情の意味を深く窺い知ることはできないが、ひとまず、少し前に二人が思っていた、彼はきっと錬金術が大好きに違いないという憶測はどうやら正解だったようである。
「僕も一応デネブの例の禁術書については目を通しましたが、あの書に書かれている内容は、他の国のものとはレベルが違う、ということなんですね?」
「ああ。並大抵の錬金術師ではまず理解ができないだろう。構成、理論、全てにおいて一切の矛盾も問題もない。流石……始祖の国だとしか言いようがない」
響の問いにも、アカツキはどこか悔しそうに返す。
鴫と響はなぜ彼がこんなにも悔しさと辛さを滲ませたような表情で話すのかが気になったが、状況が状況である、今はそれを問う時ではないだろう。それに、このことは自分達から触れてはいけないことのような気がする。
「その時」がきてくれるかどうかはわからないが、彼の方から話してくれることを待つのが懸命かもしれない。鴫はなんとなくだが、そう思っていた。
すると突然、鴫から受け取った資料をロキが適当にかき集め始める。
「よし、状況は大体把握した。僕達はこれから調査に入るから、国内や宮殿内を自由に動き回らせてもらうことになるけど、それは了承してくれ」
「あ、はい、それは構わないですけど…ってもうこんな時間なのに調査に!?や、休んで下さい!部屋もすぐに用意するので……!」
鴫がそう慌てるのも無理はない。時刻は既に日付を跨ぎ、殆どの者は床についている頃である。シアンに至っては昼頃こちらへ一度来ていたようであるし、つまりは三人ともこのまま寝ずに調査を開始しようとしているのだ。
しかし、そんな鴫を見てロキは笑うと
「ああ、天宮とこちらでは時差があるからね。ここへ来る前に少し休んできたから大丈夫さ。そもそも僕達天星と君達では器のつくりが違うからこれくらいは……あ、でも部屋は用意しておいてくれるとありがたいな」
そう言ってまとめた資料をアカツキに渡した後「それじゃよろしく」と短く言い残し、杖の先端で軽く床をひと突きする。コツン、と小気味良い音が部屋に響いたと同時、ロキはその場から姿を消した。
「え……!?」
「ろ、ロキ様……!?」
突然目の前からロキが消えたことに驚く鴫と響だったが、取り残されたシアンとアカツキは慣れているようで別段驚いている様子はない。
そして渡された資料に目を通しながら
「ロキの幻術だ。ロキは普段、自分の姿を幻術で気配から全て隠して調査をしている。気をつけろよ、ああなったロキはどこへでも入り込めるからな。隠れてやましい行動などは謹んだ方が良い。全部私らにもロキを通して筒抜けるぞ」
と、アカツキは意味ありげに笑い話す。どうやら鴫と響の仲が相当良いことからアカツキは二人の関係を察したようで、それに気付いた鴫は「は、はい……」と赤くなって小さく呟いた。(実際はまだ手を繋ぐ以上の関係にすらなれていない、鴫の片想いなのだが)
「じゃあ、俺達も始めよう。アカツキは遺体の身元確認を。俺は禁書庫の様子を調べてくる。すまないが二人共、案内してもらえないか。それが終わったらお前達は休んでいい」
「わかりました」
シアンに促され、鴫はアカツキを響に任せると、自身はシアンを禁書庫へ連れて行く。その道すがら、鴫はシアンがやたらと自分のことを見つめていることに気付いた。殺気とかそういったものではないが、刺すような視線を背後に感じ、鴫は思わず尋ねてしまう。
「あの~……俺に何か付いてます?」
「!っあ、いや、なんでもない、すまん……」
鴫に指摘され、シアンは慌てて鴫から目を逸らした。どうやら鴫に指摘されるまで自分が無意識に鴫のことを凝視してしまっていたことに気付いていなかったらしく、とても申し訳無さそうに何度も謝罪され鴫も
「いや、もういいですって!」と慌てて彼を止めた。
巷ではアヌビスと同じように「死神」と呼ばれ恐れられている断罪者であるが、彼のこういったところを見るにとても真面目な人物なのだろう。
天帝の定めた秩序を守り通すために、天帝の勅命は従順にこなす。それがどんなに、ヒトにとって非道な行いになろうとも、
天帝は神だ。髪は人の心がわからない、とよく耳にするがまさにそれだ。
神である自分の定めを乱すものは容赦なく排除する。そこにヒトの意思や情などは関係ない。
シアンはその天帝の手足となって働いているだけであり、本来なら天帝が受けるべき非難を彼が代わりに全て受け止めているようなものである。
そうでなければ、いまだに鴫を不快にさせてしまったのではないかとすまなそうに顔を歪めているようなひとが、恐れられるわけがない。
「……よく似ているな、と思っていた」
「え?」
「!あ、いや、すまん……忘れてくれ……」
おまけに誤魔化すのも下手ときたものだ。彼の態度から見るに、初対面であるはずの鴫のことを知っているのは間違いなさそうである。
確かにデネブは他にない、星の核が星の精という特殊な星国であるから、天宮の者達からしてみれば知名度は高いほうなのかもしれない。そうでなくても、先日宇宙を滅ぼさんとしていた悪星ブレウスの討伐に協力した星である。ここより遠く離れた銀河に存在する星の精霊達ならともかく、天宮に住む者であれば鴫の名くらいは耳にするだろう。
だが、「似ている」とは、一体……?
「俺みたいなひとが、天宮や他の星にもいるんですか?」
「っああ、まあ……そんなものだ……」
「まあ、世界には自分と同じ顔をした人が三人はいるって言いますしね」
そう言ってへらっと笑い、鴫は謁見の間の奥にある泉にシアンを連れてきた。
この泉から宙を貫くように伸びている光の柱――これがデネブ星の力の源である「錬成の柱」だ。
禁書庫はこの柱の奥に隠されるように存在している、扉の先にあるのだ。
「ちょっと待ってて下さい。えっと、ここの解呪錬金術のパスワードは……」
元々この扉には鍵の類がなく、鴫と響が二人で考えた解呪錬金術を改めて鍵としてかけていた。そして扉の向こうには地下へ続く階段があり、厳重な封印術がかけられている禁書庫の扉の前に辿り着くのである。
シアンは錬金術について明るくはないが、解呪錬金術が非常にレベルの高い錬金術であるということはアカツキから聞かされていた。
解呪錬金術とはつまり封印術と同じ鍵なのだが、それを組み込むのみならず解くためのパスワードになる錬金術にのみ反応するように、繊細な術式を考え施さなければならない。
これだけ高度なセキュリティをヒトである長と考え作り上げてしまうのだから、やはりこの星の子は「彼」の最高傑作なのだろう、とシアンは考えていた。
「……そういえばお前、アカツキと会っていたのか」
美しく輝く錬成の柱を見つめながら、シアンがまるで独り言のように鴫に話す。
突然のアカツキの話題に鴫は少し驚いてきょとんとした表情を見せたが、すぐに魔術錬成の錬成陣を描きながら
「あ、はい。ブレウス討伐後の報告で天宮を訪れた時に。……最初はすれ違っただけだったんですけど、なんだかとても、話してみたいと思って」
と返した。
その時シアンが非常に驚愕した表情で鴫を見たが、彼に背を向けて錬成陣を描いている鴫はそれに気付かなかった。
(まさか……だが、アカツキの消去術で消去した記憶は、一度使えばアカツキ自身の手でなければ戻せないはず……アカツキが手を抜いていたのか?それとも……)
そしてシアンがもうひとつ、鴫に質問を投げかけようとしたが、これ以上の詮索は良くないと思い留まり、出かかった言葉を呑み込む。
(アカツキが決死の覚悟で消したものだ。それに俺が首を突っ込んで良いわけがない)
「よっし、解呪完了」
シアンが一人思い悩んでいるのもつゆ知らず、鴫は扉に施していた解呪錬金術に対応する錬成陣を完成させた。扉の目の前に描かれた光の錬成陣は一瞬だけ明るく輝くと、すぐに音もなく消えていった。そして鴫が扉のドアノブに手をかけると、扉は少し重々しい音を立てて難なく開く。
「ここの封印術の鍵は天帝様から聞いている。案内はここまでで構わない」
鴫に案内され禁書庫の前に辿り着いたシアンは、静かに扉の前に手を翳す。すると先刻響が展開させていたものと全く同じ魔法陣が現れ、シアンはそれを順に解いていく。
そこまでできるのなら、この先鴫の協力はもう必要ないだろう。
「わかりました。あ、さっきの解呪錬金術の扉はここから出て扉を閉めた時にまたかかるようになってるので、もし万が一間違ってかかってしまったら遠慮なく俺を呼んで下さい」
「ああ、わかった。ありがとう」
シアンが例を言うと、鴫は満面の笑顔を見せすぐに踵を返して来た道を戻っていった。
ああ、あの笑顔はやはり「あの子」と瓜二つだ。
「……やはり、アカツキをこの任務に同行させるべきでは……いや、それともこれは、天帝様のお考えあっての人選だったのか……」
錬金術、特に賢者の石が絡む勅命任務には高確率でアカツキが選出されるが、ロキも錬金術に関しての知識はそれなりにあるし、アカツキがいないと少し調査の効率が悪くなるだけで問題を全く解決できなくなるわけではないのだ。何より、アカツキはこの星と因縁がある。
それを知っていて敢えてアカツキを指名した天帝。そしてそれを断らず受け入れたアカツキ。
「……アカツキも、この件に関してはいい加減けじめをつけようとしているのだろうか……」
シアンのその小さな呟きは、暗闇に染まる書庫の中に静かに溶けていった。
翌朝、鴫と響は朝食を済ませるとすぐにロキ達の部屋へ向かった。
ロキから夜の間にわかったことの報告がある、と呼ばれたのである。
「失礼します」
鴫がロキ達に用意した部屋の扉を叩くと、中から「どうぞ」とロキの声がする。扉を開くと、昨日はベッドと必要最低限の家具しか追いてなかった三人用の客室が、まるで住み始めて数ヶ月、といったレベルで散らかっていた。
主に部屋を埋め尽くしているのは大量の書類と本達。それらに囲まれシアンは困ったようにため息を付きながらベッドに腰掛けているが、ロキとアカツキは慣れているのか、机の上に書類を何枚も広げて何やら話し合っている。
部屋のあまりの変貌に鴫と響が唖然としていると、気付いたシアンがなんとかロキ達がいる机までの道を作ってくれた。
「一晩でこんなに散らかしてすまないな。こいつら、散らかし魔で」
「ああ、あまり書類を動かさないでおくれよ。どこに何を置いたかわからなくなってしまうから」
本の山を持ち上げ端に移動させるシアンに、ロキが机の上の書類から目は離さず声をかける。シアンは再びため息をつきながら本をその場に下ろした。
「この通りでな、片付けもままならん。とりあえずここに来てくれ」
シアンに促されるようにしてなんとか机に辿り着いた二人は、ロキとアカツキが机の上に広げている書類を見、感嘆の声を漏らした。
「すごい……!一晩でもうこんなに調べ上げたんですか……!」
被害者の身元が詳細にまとめられたものから、このデネブが持っている力と、そのどの力を攻撃や防衛に働かせているのか……。長となった時の響でさえこの星のことを知るのに数ヶ月はかかったのに、ロキ達は一晩で、しかも響達も知らないようなことまで調べ上げていたのである。
「まあ、僕達にかかればこのくらいはね。ねえ、アカツキ」
「……ああ」
ロキにかけられた何やら含みのある言葉に、アカツキは短く返す。そして響の目の前に置いてある書類をまとめて束にすると、そのまま響に手渡した。
「被害者の詳細をまとめてある。彼らに心当たりはないか?」
アカツキにそう訊ねられ、響は書類の一枚一枚にじっくり目を通していく。その横から覗き込むように鴫も書類の内容を確認する。
「ミラ国、イリス、緋国、ランドミュー、フィーナ、トリス……うーん一応緋国とトリスとは交流したことがあるね。交流したことがあるだけで、僕はこの人達を知らないけど……鴫はどうだい?」
「他の四国も、錬金術ができたばかりの頃にその時代の星の精がデネブに来たことがあるから、一応この六国全て交流記録はある。それも今は全部錬金術国家になってるはずだ。だけど……俺もこの人達のことは知らないな……」
書類を眺め、低く唸りながらアカツキの問いに答える二人を見、アカツキは「そうか」と短く返した後、一息ついてからすぐにもう一枚の紙を二人に手渡した。
「彼らの共通点は、出身国が「デネブから直接錬金術の技術を輸入した錬金術国家」であり、勿論彼らは全員、変化と創造の力を持っている。そして……その全員が、常人とは比べ物にならないレベルの力を持っていた」
「……!」
鴫と響は息を呑む。
犠牲となった彼らは、ただ変化と創造の力を持っていだけではない。ひとりひとりがそれぞれ大きな力を持っていたという事実。そして奪われた禁術書との関係を考えれば、これは間違いなく犯人は賢者の石を錬成するために彼らを攫ったということ。
「普通の賢者の石であれば、一人で一個は余裕で錬成できるだろう。それ程までに強い力だ」
「普通の、賢者の石……?」
アカツキの言葉に、鴫は首を傾げる。鴫のその仕草で彼が何を疑問に感じているのかアカツキはすぐに理解したらしく、くつくつと喉の奥を鳴らすように笑った。
「ああ、普通の、だ。そこかしこの錬金術国家が保有している禁術書に書かれた賢者の石……その程度のものなら錬成が可能だということだ。いいか、ヒトがこうして研究に研究を重ねて編み出した賢者の石の錬成法は決して間違ってはいない。書かれた通りの材料、そして正しい手順で錬成すれば、「本物のまがい物」くらいは作れる」
そういえば、アカツキはここに到着したばかりの時「賢者の石に近い賢者の石」という不思議なワードを口にしていたことを響は思い出した。そして、先程の言葉。そこから導き出されるアカツキ達の仮説に、響はなんとなく気が付いた。
「あの……もしかして犯人は、「鴫と同様の存在」を作るつもり、なんでしょうか……」
おそるおそる訊ねた響を、アカツキは「ほう」を目を細めながら面白そうに見つめる。
「流石、解呪錬金術の錬成陣を難なく組んでしまえる長殿というべきか……その通りだ」
天司十星であれば、鴫の正体が星の核であること、そして多くの錬金術師が求める「賢者の石」の大元となった存在であることを知っているのは当然だろう。そしておそらく錬金術の知識にも明るいアカツキが立てた仮説。仮説ではあるが、犯人の思惑はほぼこれで間違いない。
「ただの賢者の石がほしいのであれば、これほどの力をもつヒト一人の血と自国の禁術書の知識があればそれで十分。なのに六人も犠牲にした上にデネブの禁術書を選んだ。デネブは、賢者の石が本来どういうものであるか理解しているヒトがいる、奪われた禁術書を書いたのはその類のヒトだね。だから内容は鴫くん寄りの賢者の石を錬成するためのものだ。……よくまあ、魔術で星を作るレベルの理論を立てられたものだよ」
ロキも思わず感嘆の混じったため息をつきながら語る。
「ひとまずわかったのは、犯人はデネブの情勢に詳しく、星を自由に行き来できる権限を持つ「ヒト」だ。だが……」
それだけ言うと、アカツキはシアンの方をちらりと見た。
シアンは机の上の書類の山から、自分がまとめたのであろう書類の束をひとつ引っ張り出す。
「俺が調べたのは、あの書庫に残っていた力の痕跡の詳細についてだ。俺達が知っている、ああいった密室の空間を自由に出入りできるのは、ロキみたいな純正の幻と鏡の力を持った奴だけだ。だがそれでも、星の中に少しでも姿を見せたり触れたりすれば、力の痕跡は残るし星の記憶にも存在が刻まれる。そうだな?ロキ」
「うん、そうだよ。僕が持つ幻と鏡の力で姿を消したり様々な場所へ通り抜けたりするのは、他人の目や僕の力に干渉する力を欺いているだけに過ぎない。星の核は正しいものを記録するようにできているから、それを欺くのは始祖の幻鏡の力を持つ僕であってもできないことだ」
だから鴫のような存在は、禁書庫のような特殊な場所に侵入者があった場合は星の記録にそれが記録されるため、すぐに気付くことができるのだ。だが、今回鴫は侵入者に気付くことができなかった。ということは、つまり……
「今回の犯人、俺達ですら知らない未知の力を持っている可能性がある」
「……!」
シアンの言葉に、鴫と響は息を呑んだ。
天司十星ですら知らない力を持つ者の存在。これはつまり、解決が難航するかもしれない可能性があるということ。そして対抗できる力がわからない限り、被害を食い止めることが難しいということだ。
「すぐに片付くレベルの任務だと思っていたんだがな……」
「僕もだよ、よくあるケースだと思っていたのだけれど、ここの禁書庫、そしてデネブという星の性質上、これらを強行突破できる力なんて、僕達の知ってる範囲では不可能なのだからね」
ロキも、シアンから調査結果を聞くまでは大したことのない事件だと思っていたらしい。天帝がこの三人しかここへ送り出さなかったことからしてみても、おそらく天帝自身も事態を軽く見ていたのだろう。
「僕は一度天宮に戻って、ユエを借りられないか天帝様に交渉してみるよ。いや、浅葱にも来てもらった方がいいか……魔力なのか呪力なのか全く見当がつかない」
そこまで話して、ロキはふと、何か思い当たることがあるのかはっと目を見開いた。「いや、まさか…」と自分にしか聞こえない程の小さな声で呟いてから
「とにかく二人とも、ここは任せたよ」
と言うが早いか杖を取り出し、すぐにその場から姿を消した。今回は昨晩のように幻術を使ったのではなく、転移術でこの星を出たのだろう。
残されたシアンは「困った」とでも言いたげに眉を寄せ、アカツキは書類を見つめ何やら小声でずっと何かをぶつぶつと呟いている。
「ええっと……そうだ!とりあえず、俺達に何かできることはありますか!?」
少し重くなった空気の中、鴫が思い切ったように声を張り上げシアンとアカツキに尋ねた。
突然の鴫の大声にシアンはぽかんとし、アカツキは余程驚いたのか目をまんまるに見開いて鴫を見つめている。そして響も鴫の隣で耳を塞ぎ、少し迷惑そうに顔を歪ませている。
「びっくりした…急に大声出さないの」
「あ、あはは、ごめん……でも、自分の星で起きた事件なんだし、星の精である俺も何かできないかと思ったらいてもたってもいられなくて……」
少ししょんぼりとしながらそう話す鴫をそれまでずっと驚いた顔で見つめていたアカツキが、急に顔を歪めた。そして方を震わせ何やら堪えていたようだが、ついに我慢ができなくなったのか声を上げ笑い始める。
「ふふ……ははは!」
「あ、アカツキ……?」
シアンは思わず面食らってしまう。だってこんなにも楽しそうに、心の底から笑っているアカツキを見るのは久しぶりだったからだ。それこそ、そう。「あの子」を失ったあの時から、まるで笑うことを忘れたかのようにこんな風に笑うことがアカツキはできなくなってしまっていたのだ。
暫くアカツキは笑い続け、ついに鴫がおろおろし始めるとようやくアカツキは一息つき、目尻に滲んだ涙を指で拭いながら
「いや、すまないな。私達に気を遣ってくれたのだろう?お陰で少し気持ちが楽になった」
と心配そうに顔を覗き込んできた鴫の頭を軽くなでた。
その瞬間、鴫はまた、初めてアカツキと出会った時と同じ懐かしさで満ち溢れた気持ちを呼び起こす。今回もその気持ちはアカツキが手を離したと同時に消えてしまったが、鴫はこれでなんとなくだが、自分の中で今まで思っていた憶測が確信に変わったのを感じた。
(やっぱり俺、この人のこと知ってるんだ……)
アカツキと過ごした記憶はない。それなのに、遥か昔、こうして同じように彼に頭を撫でてもらったことがあるような気がする。いや、あるのだ。間違いなく。
そうでなければこんなにも懐かしさと幸せに満ち足りた気持ちを、胸の石が呼び起こすはずがないだろう。
「シアン、この二人には何をしてもらう?ロキはいないがロキにこの場を任されたのだから、あいつが戻ってくるまでは私らの判断で動いても文句は言えんだろう」
「まあ、そうだな……今は少しでも多くの情報がほしいが、人手が足りないし……」
シアンは顎に手を当てて唸る。ロキであれば、次にどう動けばここから起こる被害を最小限に抑えられるかの策をすぐに導き出すことができるのだが、生憎それは司っている「知恵」の力を宇宙の演算器として使用することができるロキの特権であり、シアンとアカツキにはそんな力は備わっていない。
「……そういえば」
ふと、シアンは思い出した。それは、今回犠牲となった六人の共通点についてだ。
「この国にも、今回犠牲となったヒト達と同じ特異性を持つ者がいることがわかった。犯人が強い力を持つ者の血を集めているのなら、彼女も狙われるかもしれない。彼女の護衛を頼もう」
「え、そうなんですか?」
賢者の石を一つ錬成できるほどの魔力を持つ者なんて、星に一人いるかいないかの稀な存在である。とはいえ、前述の通りデネブで賢者の石の禁術書が保管してある禁書庫に入れる権限を持つ位のものであればまず、賢者の石を錬成しようとは思わない。鴫が賢者の石であることを知っているし、賢者の石の真実も知っているからだ。そして一般人は賢者の石の存在は認知しつつも、錬成法がわからないために何もすることができない。
だから今まで、自分の国にそんなに強力な変化と創造の力を持つ者がいるなんて鴫も響も知らなかったし、知っても何も思わなかっただろう。この星にとって力の強さなど、あくまで個性としか認識されないのだから。
「あ、でもそういえば昔、一人の女の子が他国の錬金術師に狙われるって記録があったかもしれない。珍しいステータスを持った問診票だったから、同一人物かも、俺の一つ前の星の精の時代だし……うーんと、ちょっと待って、今探してるから……」
そう言って鴫は目を閉じ、頭に手を当てて意識を集中させる。これは鴫が自身の石、つまり星の記録から特定の事象を検索している時の仕草だ。
それを見たアカツキが、また先程のように小さく声を上げて笑っている。
「はは、まるで一休がとんちを考えている時のようだな」
「一休…?ああ、地球のお伽噺のあれな……ってお前の笑いのツボよくわからないな……」
肩を震わせ鴫を指差して笑うアカツキに、シアンはわけがわからんとでも言いたげに首をひねり、そして響もそういわれると今まで見慣れていたその仕草もそうとしか見えなくなってしまって思わず吹き出してしまうのだった。
「ちょっ何笑ってんだよ、真剣に検索してるんだからな!えーと……あっこれだこれ……え?」
鴫は二人の謎の笑い声に気取られながらも、ようやく該当のデータベースを見つけ、すぐにそれを書類に錬成してみせた。
その書類に記載されている名と顔写真を見、鴫は思わず固まってしまう。そんな鴫の様子を不思議に思った響も、鴫の錬成した書類を覗き込んで思わず固まってしまった。
「う、泡沫さん……!?」
「母さん!?」
そしてシアンがマークしていた要護衛の人物をまとめた書類にも、しっかりと泡沫の情報が記されていたのである。
◆◆◆
「えぇ、あたしが変なのに狙われるかもしれないって?」
宮殿の厨房で樹と談笑しながら昼食の準備をしていた響の母――泡沫は、響達の話を聞いて驚いたように声を上げた。
「うん。それで、危ないから護衛してあげてってシアン様に言われたんだ」
勿論泡沫も長の母親としてだけではなく、重臣の一人として宮殿で働いているわけだから天司十星シアンの名もよく知っている。だが、まさか、自分が。宇宙の秩序を見出そうとする者に狙われるほどの力を持っていたなんて――
と、普通の人なら驚くであろう。しかし泡沫は大きなため息をつくと
「はあ……湊と結婚して以来そういうのはなかったんだけどねえ……久しぶりだよ」
と驚くべき発言をしたのである。
「えっちょっと待って母さん。母さんは自分の力のこと……」
「勿論知ってるさ。この力のせいで子供の頃から随分と苦労させられたからね」
「じ、じゃあこの事件も、間違いなく泡沫さんってこと……?」
そう言って鴫は先程錬成した書類を泡沫に見せる。泡沫は綺麗にまとめられている書類を少しだけ読んでから
「あたしだね」
と短く答えた。
「あたしは生まれつきとても大きな変化と創造の力を持っていてね。なんでか知らないけどこの力を欲しがった何人もの他国の錬金術師に幼い頃からよく狙われてたんだよ。この事件は、これがきっかけで親を亡くしたからよーく覚えてるよ」
その後は国立錬金術学校の寮で暮らすことになり、泡沫は国に守られるようにして生活をしていたのだという。
成長するにつれ自分の持つ強大な力をコントロールし身を守る術を身につけたため、襲われても強力な錬金術で追い払っていたから徐々に何者かに狙われることは減っていったらしい。
「だけど、あたしが研究所で働き始めて暫く経った頃だったかな……久しぶりにまた追いかけられてね、流石にその時は油断してて捕まっちゃったんだけど、湊が助けに来てくれたんだよ。それから湊があたしに何か魔術をかけてね、狙われることは全くなくなったんだけど……」
それまで幾度となく湊からのプロポーズを断っていた泡沫だったそうなのだが、これを機に仕方なく折れ、プロポーズを受け容れたのだという。
泡沫が湊から何度も求婚されていたという話は、かつて大学教授をしていた湊の教え子である樹と葉月から聞かされていたので、響はその時の湊の喜びっぷりを想像してしまい思わず苦笑いを浮かべてしまった。
「でも、犯人の狙いが泡沫さんみたいなタイプのヒトだってことなら、この星に侵入した時に泡沫さんはとっくに犯人の餌食になってたと思う。多分、湊さんがかけたらしい魔術の効果自体はまだ切れてないんじゃないか。実際俺も全然わからないし」
鴫はそう言いながら泡沫の周りを観察するようにぐるぐると回ってみるが、やはり彼女自身も自覚している「強力な変化と創造の力」は感知できない。変化と創造の力そのものを核としている鴫なのだから、そんなヒトが身近にいれば嫌でもその力の大きさに気付くはずだ。
「これ、相当強力な魔術だ。泡沫さん、湊さんがかけたその魔術のことは何か知ってる?」
「いやそれが全然わからないんだよねえ……あの人、自分でいろんな新しい錬金術や魔術をそれこそ新しい料理のレシピを作るみたいにポンポン考えてたから……近くで補佐はしてたけど、全部は把握しきれてないんだよ。魔術錬成のことも全然知らなかったしね」
確かに、泡沫は響が魔術錬成の研究を継ぐと言った際、詳細を聞いて「錬金術がそんなに便利になるのかい」と驚いていた。魔術錬成の危険性が判明したのは響が偶然他人に魔術錬成のやり方を教えてしまった際に起きた事故が初めてだったから。危険性があるから泡沫には教えなかった、というわけではなく単純に他に作り出した錬金術や魔術と同じく、湊にとってはただの新しい創作料理の一種にすぎなかったのだ。
「……ということは、父さんの研究書類の中に該当の魔術の研究記録があるかも。僕、錬金術の方は全部目を通したんだけど、魔術研究に関しては魔術錬成に関連する書類にしか目を通してなかったんだ」
というより、響自身湊が錬金術だけでなく魔術の研究開発をしていたことを知らなかったらしい。
自分が幼い頃から父親が熱心に研究をしていたのが錬金術だったから、父といえば錬金術、という公式が自分の中で出来上がってしまっていて、魔術が得意だったか否かはあまり記憶に残っていなかったのだ。実際、湊の自宅の書斎と研究室に置いてあった本や研究書は殆どといっていいほど錬金術に関係するものばかりだった。
「まあ、魔術より錬金術の方が大好きな錬金術オタクだったからね。錬金術の可能性を広げるために魔術を研究していたようなものだよ、あれは。それで、その魔術がどうかしたのかい?」
首を傾げる泡沫に、響は昨日起きた事件の内容と天司十星達が調べてわかったことの詳細を伝えた。
「だから母さんが保護対象になってたんだ。でも鴫でさえ感知できないのなら大丈夫かな。一応警戒を解くのは魔術の詳細を調べてからの方が良いと思うから、ちょっと調べたいんだけど……」
「ん。それでちょっと閃いたことがあってさ。その魔術、詳細がわかって俺達が使えるようなら、他の星の人達もその魔術で守れないかな」
鴫の提案に、響の表情がぱっと明るくなる。
「この事件、難航するかもしれないってロキ様達も言ってたから、解決するまでにまた被害が出てしまうかもしれない……だからできるだけそれを食い止められればって。ヒトを守るのが、俺達星の子の役目だしな」
泡沫もそれを聞いて「成程ねえ」と納得しているようだった。
だが、かつて湊達が暮らしていた家の彼の書斎に保管してあった本や研究書類はあまりにも膨大である。書斎だけでなく、響の部屋の四方を天井まで埋め尽くすように置いてあった本棚にも湊の研究術書が隙間なくしまってあったし、隠し研究室にも軽く小さな本屋でも開けるのではという量の本があった。それらは響が長として宮殿に移り住むことになった際に全て宮殿の書庫に移したのだが、それだけでなく、今は泡沫が湊の後任を務めている研究室にも、自宅には置ききれなかった本や研究書類が大量にあることが泡沫の証言でわかった。
「えーと……つまり、木を隠すならなんとやら、の逆バージョンてこと……」
「広大な森の中から特定の一本の木を見つけなきゃいけない、ってことだね……」
宮殿に運び込んだ書物の量を思い出し、鴫は思わず引きつった笑みを浮かべてしまう。心境は響も同じようで、鴫の隣で額に手をやっている。
そして一番厄介なのが、彼は己の研究したものに表題をつけてまとめるということをしないのである。
魔術錬成の研究書については表題こそついていなかったものの、危険性のある研究であったために外に持ち出されるのを懸念した湊が全てまとめて一箇所に隠していたが、他の研究についてはそうではない。研究室には彼の研究の補佐をしていた泡沫がまとめてファイリングしているものもあるそうなのだが、メモ魔だった彼は一枚のレポート用紙にメモをする感覚で研究内容をまとめ書き記していたりもする。そういったものが乱雑していてそのあたりのものはさすがの泡沫も手がつけられず、分類しきれないまま保管しているらしい。
「泡沫さんにかけてる魔術は相当レベルの高いものだからちゃんとまとめてるものだと思いたいけど、天才って常人の予想斜め上のことするからわかんないな……湊さんにとってはこのレベルの魔術も、メモ書き程度のものだったのかもしれないし」
「しらみつぶしに探してみるしかないね……」
二人は思わずため息をついてしまう。が、ここで折れてしまっては大切な人達を守ることはきっとできないだろう。今はとにかく一人でも多くの人を守るために、湊の遺したその名もない魔術に頼るしかない。
「それじゃあ、あたしも手伝うよ。特に研究所のものはあたしが整理してたからね、少しは力になれると思うし……あ!」
そう笑った直後、泡沫は何かいいことをひらめいたとでも言いたげに表情を明るくさせたが、すぐに腕を組んで「うーん……」と何やら考え込んでしまった。
「母さん?どうしたの?」
「……いや、湊の研究についてもう一人詳しい人がいるんだけど……」
「え、ほんとに!?誰ですか!?」
泡沫の言葉に鴫は食いつく。あれだけの量の書物の中からたった一つの魔術研究書を探し出さなければならないのだ。
湊はその人柄から交友関係は良好で多くの友人がいたのだが、彼の持つ知識についてこられた者は殆どおらず、故に研究の補佐の殆どは唯一彼についてこられた泡沫が請け負っていた。だからこそ、湊の研究を理解できる貴重な助っ人は多ければ多いほどありがたいもの。
しかし泡沫は顔を歪め、何やら言いにくそうにしている。が、おそらくダメ元で口を開いたのだろう。泡沫が口にしたのは、驚くべき人物の名だった。
「梧桐だよ」
◆◆◆
鴫と響を見送ったアカツキとシアンは、再び例の禁書庫で調査をすることにした。
自身も錬金術を使えることを彼らに打ち明けたアカツキが、鴫から禁書庫へ続く扉に施されている解呪錬金術のパスワードとなる錬金術を教えてもらい、自由に出入りできるようになったのだ。
「しかし、改めて見ると本当によくできた解呪錬金術だな。複雑な術式を繊細に組み込んでいる。少しでもパスワードとなる錬金術を違えればびくともしない、綻びも欠陥も何一つない完璧な錠前だ」
何やら少し楽しそうに扉に施された解呪錬金術を観察しているアカツキを、シアンが奇怪な目で見つめている。
「ヒトが作った魔術だぞ」
「そうだな。だが、私の力をこうして面白いことに利用するヒトはまた別だ。こういったヒトの子らが私の力を使ってどこまでやれるのか……その行く先に興味がある」
アカツキはそう言って目を細めて笑う。それはかつて、アカツキの傍にいた赤毛の彼に笑いかけている時と同じ笑顔だということにシアンはすぐに気付いた。
「……なあ」
「ん?」
「アカツキは、この任務を受けてよかったのか」
禁書庫の重い扉を開きながら、シアンは静かにアカツキに問う。
それは昨夜、気になっていながらも触れないほうが良いだろうと思っていた疑問だ。
案の定返事はすぐに返ってこない。だが背後の気配から感じる彼の感情は、負のものではない。
不思議に思いシアンが振り返ると、アカツキは何か考え込むように腕を組んでいた。そして一言、思わぬことを口にする。
「あの子にかけている私の術が、どうも綻びかけているようだ」
「え……?」
シアンは思わず呆然としてしまった。
何故なら、アカツキが彼にかけた術といえば、アカツキが天帝から授かった「記憶」の力から成る最上級の記憶術だからだ。精度の低い術なら劣化することもあるだろうが、アカツキの使う記憶術の力は天帝から授かった力であるから、強度はアカツキが消去した記憶の欠片を元に戻さない限り永続なはずである。
確かに、昨日の鴫の話を聞いてまさか、とシアンも勘付いていたが、そのまさかだったとは。
「先日あの子達に一度会ったと話しただろう。気付いたのはその時だ。はっきりとではないが……あの子、鴫の記憶の中にナユタの力の断片を感じた」
ナユタとはアカツキとかつて恋仲にあった星の子だ。そしてとある事件を起こし、アカツキ自ら手を下し、命を落とした。
勅命任務としてアカツキと同行しその場にいたシアンは、アカツキとナユタの死闘の一部始終を全てその場で見ていた。その後、自らの手で恋人を葬り去ったアカツキがひどく傷付いていたことも、全部見て、知っているのだ。
そしてシアンが一番心配しているのは、ナユタがデネブの星の精、鴫と大きく関係しているということ。故にナユタの死後、アカツキはデネブの地に足を踏み入れたことは一度だってない。
それ程までに、アカツキにとってナユタの存在は大切なものだった。
だからシアンは、天帝からの勅命とはいえこの任務を引き受けたアカツキの身を案じていたのだ。
しかしアカツキは、この任務を受ける前に図らずも鴫と対面することになり、そして違和感に気付き、悟った。
確か鴫はブレウスに捕らえられ、長い間ひたすら悪魔を錬成するための機械として酷使されていたとシリウスから聞かされていた。おそらくその時に、自分がかけた記憶術の効果が綻んでしまったのだろう。
そして舞い込んできたデネブでの勅命任務。
これはいい機会だと思った。もう、いつまでも彼のことを引きずったままではいられないのだと思った。
「多分、あの子達は本当のことを知りたがっている。デネブの生い立ち。歴史。創造主。全てが私の術によって消し去られたこの星。天帝様がこの任務に敢えて私を選出したのも、おそらく理由あってのことだろう。あの子達が全てを知らなければ……この事件は解決できないのかもしれない」
そう話すアカツキの横顔は、どこかふっきれたような表情だった。
「そして私も……多分、もっとあの子達に歩み寄りたいと思っていのだろうな」
「え?」
続いたアカツキの言葉にシアンは思わず目を見開いて彼を見たが、アカツキの表情は既に真剣に仕事をしている時の目つきになっていた。こうなってはもう、横から関係のないことで口を挟めば彼の機嫌を損ねてしまうだろう。
だがシアンは悟る、やはり、アカツキは永く続いた自分自身の問題と真剣に向き合い、解決しようという覚悟でこの任務を引き受けたのだ。もし、真実を話したことであの子達に背を向けられることになったとしても……それもきっと、覚悟の上だろう。
「おい、シアン。何を呆けている。お前もさっさと調査を手伝え。
「あ、ああ……」
いつもの調子でアカツキに叱られ、シアンもすぐに自分のやるべきことに手をつけ始めた。