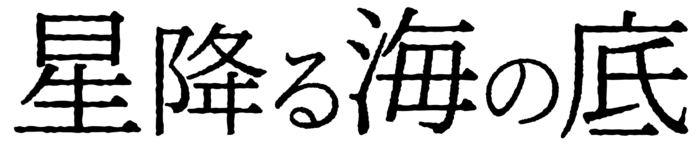第七章【鶲と七海】
謁見の間は静寂で満ちていた。
その静寂を切り裂くように、一人の少年の凛とした声が、かつてのお伽噺のその後を紡ぐ。
「そこで俺はずっと、体から魔力を奪われながらも七海の傍に添い続けた。七海が寂しくならないように……でも、とうとう限界が来て……丁度その時、馨が現れたんだ」
「お、俺が……?」
悠の言葉に、馨はきょとんとしながら返した。悠は静かに頷く。
「俺は七海を馨に託し、力尽きた。そこから先のことはわからない。七海が、どうなったのかも」
馨は思い出した。半年前、初めて奏の家に泊まった時に見たあの妙にリアルな夢のことを。
「あれはやっぱり夢じゃなかったのか……!七海は、お前……鶫が消えたのを見て、泣きながら結界に触れて……」
「消失、か……やはり、心を知ってしまった七海にあの封印は耐えられなかったのか」
最期は寂しそうに微笑みながら消えていった七海を、馨は思い出す。
自ら望んで受けた罰ではあれど、なかば永久の時を一人で過ごすなど、普通の心を持つ者からすれば気が狂ってしまうだろう。鶫という唯一の存在失った七海が耐えきれず、自ら消失し永遠の寂しさから解き放たれる道を選ぶのも無理はない。
きっと、奏が人から嫌われるのを極端に恐れるのも、七海のもつそういった過去が奏の心の奥底で眠っているからなのだろう。
嫌われれば、一人になってしまう。一人になれば、また寂しさと共に生きていくことになる。
そうなれば、奏の力は……──
七海は奏の知らないところで、奏の心が寂しさに染まってしまわないようにと、きっと何度も助けてくれていたのだろう。
「……と、まあ、我と悠の話をつなぎ合わせると過去の真相は大体こんなものだ。鶲の処遇、そして我が孫娘の最大の失態……あの頃の宇宙は今ほど体制が整っていなかったのでな、国民達の反感を買う可能性を回避するためアカツキに全ての記録を抹消してもらったのだ」
天帝は最後を締めくくるように話す。
何故、現在どのデータベースにも七海と鶲のことについて詳しい記録が残されていないのか。
それはクレス達が予想していた通り、天帝が二人に関する事件の記録を全て抹消していたからなのである。
アカツキとは、シリウスと同じく天帝の側に仕える「天司十星」という側近のうちの一人であり、天帝からこの宇宙のあらゆる仕組みに影響を与えることができる程の力を授かっている。彼が司る主な力は「記憶」であり、人々の記憶だけでなく、星の歴史や記録という根本的なところからデータを改ざんしたり、消去することができる。彼のその力を行使する権利を持つのは天帝のみであり、その力によって消された記録は他のどの力をもってしてもアカツキ自身の力でなければ戻すことは不可能という非常に強力な力なのだ。
ただ記録を消すだけなら天帝の力だけでも十分にできる。だがアカツキの力を借りる程、天帝は二人に起きた悲劇を人々に知られるのを恐れていたのだ。
「己の世間体の為ですか。本当に最低ですね」
天司十星が絡んでいると知った凪は吐き捨てるように言うが、天帝は苦笑をしながら弁明をする。
「おっと、相変わらず凪は我に手厳しいな。まあ、それも間違ってはおらぬな。だが、七海はベガの国民達にとても愛されていたからな……ベガの国民達の心には、いつまでも神聖な織女星である七海の記憶が残っていてほしかった……それは我の願いでもあったのだ」
確かに、現在ベガの国民達に伝わっている初代織女星の話といえば、彼女はとても美しく、星と民を愛し、国を幸せへと導いた立派な星の精であったと。あの時代の七海を知る者はもう存在していないが、世代を越え、長い時を経て彼女のことはそう伝えられてきたのだ。
そしてそれを語る人々の表情は、皆とても幸せそうなのである。
「……でも、これで俺もわかった。七海の名前を聞いた時の心のもやもやが。俺の中のアルタイルの意思が……七海のことを知っていたからだったんだ」
「今、私達が受け継いている蘇生術は、鶲が愛する人を助けるために作り出したものだったんですね……」
紅袮と蘇芳は、目を閉じて胸を押さえた。
─真の蘇生術─
一時はこの宇宙を滅ぼさんとする敵に利用されそうになった力だが、本来は鶲が七海の封印を解くために作り出した、良い力であったということ。
二人は、鶲の想いが自分の中で眠っている……そう思い、胸が熱くなるのを感じていた。
「それで、転生した七海と鶫が双子として奏と悠に……双子として生まれたのは、それまでの七海と鶲の二人を見てきた鶫の願いから、ということか?」
「そう。このまま奏が五行の力を持ったまま馨と結ばれ織女星として覚醒してしまえば、結局またあの時と同じ悲劇の繰り返しになってしまう。だから今度は俺が、奏の代わりに本当の織女星になる。それなら、奏と馨を邪魔するものはなくなる」
クレスの言葉に、悠は頷いてはっきりと返す。
先程の鶫の話を聞いた後であるから、悠のその決心がどれだけ固く、そして強いものなのかというのがよくわかる。
だが、それでも馨は納得がいかなそうに顔を歪めて悠を見ていた。
「でも……でも、そしたらお前は、どうするんだ?今度はお前の心が自由じゃなくなっちまうだろ?」
「俺はそれでいいんだ。今度こそちゃんと、織女星と牽牛星が結ばれてくれれば」
「……ん?それってどういう……」
何か引っかかるものを感じ、馨は首を傾げた。すると馨の背後から天帝が現れ、馨の頭を軽くぽん、と撫でる。
「今までの話でわからなかったか?馨、お前が次の牽牛星なのだ」
「……え……?ええええええええ!?」
「で、ですが馨に牽牛星としての権能と力はありません!だから今までアルタイルの星の精は顕現していないと……」
天帝の言葉に馨は勿論、馨を孤児として拾い今まで育ててきた凪も珍しく驚きを隠さずに話す。
だが確かに、馨が他の妖精達と違うということは凪も気付いてはいた。
妖精であれば必ず使える魔術──所謂、妖精術というものを馨は一切使うことができなかった。妖精術を得意としていなかった凪の妹、海ですら使うことができた簡単な術ですら会得できなかった。
しかし、天帝が言うように馨が妖精ではなく牽牛星──星の精なのであればそれも説明がつく。
妖精は魔術を使うが、星の精が使う呪術を使うことはできない。その逆もまた然り。
つまり馨は本来星の精であった為に、魔術を使うことができなかったのだ。
「……成程、つまり、今この世に残っている鶲の「念」の存在が、馨を牽牛星として覚醒させるのを妨げている、ということか」
「鶲はあの時、天帝様に消失させられたのかと思っていたんだけど、天帝様に対してとてつもない憎悪の感情を芽生えさせた。それが「念」として鶲をこの世に留まらせている。馨は次の牽牛星となる、今は器だけの存在。だから多分、今まで呪術も使えなかったでしょ」
シリウスの話に悠は再び頷くと、馨を見つめてそう話した。
言われてみれば、と馨は何やら腑に落ちた様子で、続けて
「だから悠も楸も……体乗っ取られるぞって言ってたのか……」
と、今まで気になっていた謎が解けすっきりとしているようだった。
「乗っ取られたら最後。馨という人格は消え、また鶲が復活する。それだけはどうあっても避けなければならなかったから。あの時はまだ真相を話す時ではなかったし、混乱させてごめん」
「いや、いいって!二人は俺を助けようとしてくれてたのに、俺の方こそ気付かなくて悪かった…」
しおらしく頭を垂れ謝罪する悠に、馨も慌てて謝罪を返した。
事情を知らなかったとはいえ、あの時の悠と楸の理解不能な言動に苛立ってしまった時もあったし、言うことを聞いていなければ自分は今ここにいなかったかもしれない。そう思うだけで背筋がゾッとし、馨は心から二人に感謝をした。
「今この世に残っている鶲の念は、我に対する憎しみの塊のようなものだ。復活すれば、すぐにでも我を消しに来るであろうな」
「でも、所詮は念だけ。念では、折角の蘇生術も大した威力を発揮できないはず……真の蘇生術で天帝様を消し去るなど、難しいと思いますが……」
天帝の言葉に響がそう話すが、何かに気付いたように紅袮が声を上げた。
「……奏の力……!?」
「!!」
「奏……織女星の五行の力は、感情の影響を受けて天帝様の力をも凌ぐ、全てを消し去る力となる。鶲はその為に奏を利用しようと考えてた。でも、俺がそれを阻止した。俺が代わりに五行の力を使って鶲の願いを叶えるから、奏のことは巻き込まないで欲しいと」
鶲の真の目的と、奏を攫った理由……それらの謎が全て一つに繋がった。
悠の本心は天帝を滅ぼすことではなく天帝に五行術と共に封印されることであるから、実際に鶲の願いを叶えることはできないのだが、それは話さず半分鶲を騙すような形で交渉を試みた。結果、互いの利害は一致し、だから二人は手を組んでいたのだ。
その話を聞いた凪は焦りを募らせる。
「ということは、今のこの状況は非常にまずいです。鶲からしてみれば、五行の力が使えれば奏くんでも悠でもどちらでもいい、ということなんですから。もし、今行方の分からない奏くんが仮に敵の手に捕らわれているのだとすれば……」
「!奏が危ない……!」
凪の言葉の意味を理解し、馨も慌てて椅子を立った。隣で話を聞いてた杏達の顔にも、焦りの色が滲み始める。
「殺される、ということはないと思うけど……奏が奏じゃなくなってしまう……そんな気がするわ」
「多分、奏の心は壊されてしまう。急がないと……」
比較的冷静に話を続けていた悠も、焦りのせいか少し早口になっている。
そんな周囲の感情を察知したシリウスは「ふむ」と小さく呟くと
「では、我々が全力で捜索にあたろう。セレス!カロン!テティス!」
「はい!」
手を叩いてそう叫んだ直後、誰もいなかった場所に三人の星の精が現れる。
先日、奏と杏をウォーターシティへ案内してくれた土星の星の精テティスと、その後攫われた奏の捜索に協力してくれた水星の星の精セレス、冥王星の星の精カロンだった。
「今回は奏の体の一部……髪があるから、以前よりは早く特定できると思うわ」
「セレスとカロンが捕らえた奏さんの足取りを、僕がセレスの水鏡に投影します。皆さん、場所に心当たりがあれば教えて下さい」
「わかった!」
テティスの言葉に、馨達は一斉に声を返した。その返事を聞いたセレスはすぐに宙に水鏡を展開し、カロンは意識を集中し始める。
「では、いきます!」
カロンのかけ声と共に、セレスが展開した水鏡に早くも映像が映し出された。
まず最初に映ったのは真っ暗な森の中で、先日奏が迷い込んだ死の森であると全員すぐに理解した。
それから間もなく奏は魔物に襲われ、襲いかかった一体の魔物を皆が見たこともないような力で倒す光景が映し出される。
馨達はそれを息を呑んで見つめていた。あの時自分達が見つけた魔物の死体は、やはり奏の力で絶命したものだったのだ。
その後奏は集まってきた魔物の群れに追いかけられる。必死で逃げるうちに森の奥に迷い込み、そして──映り込んだのは茨の谷。
「……っ!」
馨は思わず目を伏せてしまったが、水鏡から目を離さなかった悠は何かを見たようだった。
「……鶲……?」
「え……?」
その呟きを聞き逃さなかった馨は思わずもう一度水鏡に目線を戻すが、そこにはもう何も映っていなかった。星も首を傾げている。
「確かに今、誰かが映り込んだような気がしたけど……でも鶲って、今は念だけなんだろ?」
「でも、今のは間違いなく……何かあるのかも、続けて」
「は、はい!」
悠に促され、テティスは再び映像を水鏡に投影し始める。次に映し出されたのは、一面の花と泉で覆われた場所だった。
「この花は……!」
「ベガ、ですね……」
クレスと蘇芳がすぐに反応を示した。映し出されている花はクリスタルフラワーといい、ベガの泉にしか咲かない、半透明の花弁が虹色に光るとても特殊な花なのだ。
二人が詳しい場所を特定しようと映像をじっくり見つめていると、突然映像は途切れ、展開していた水鏡も霧散してしまう。
「あっ……ごめんなさい、ここで力を弾かれちゃった……」
セレスはしょんぼりと肩を落とした。どうやらセレスの力を弾くほどの強い力が干渉したらしい。
「流石に根城までは教えないという魂胆ですか……とりあえずベガ内だということは特定できました。そこからの足取りは、実際に行って調べてみましょう」
「そうだな、今すぐ出発しよう」
凪の言葉に、クレスや馨達も頷いた。
「皆ありがとう!お陰で奏を見つけられそうだ!」
馨が三人に礼を言うが、カロンは申し訳無さそうに
「完全特定はできませんでしたが……力が及ばず、すみません……」
と謝罪する。しかし馨は笑いながらカロンの肩を叩いた。
「いいって!どこの星に行ったかくらいわかれば、皆で探せばきっと見つかる!」
どこからその自信が出てくるのだろうか。しかし、馨のその笑顔につられ、力不足で肩を落としていたカロン達も自然と笑顔を取り戻していた。
皆の表情に笑顔が戻ったのを見て、天帝も安堵したように息をつく。
きっと彼らなら、そして馨であれば、あの鶲を救うことができるだろう。
「それでは皆、我からの命令だ。迷いし牽牛星の魂を浄化し、救済せよ」
「承知致しました!」
天帝から下された命に、一同が頭を垂れて了承する。
しかし凪だけは口を尖らせ
「ま、元は自分でまいた種みたいなものですけどね」
などと悪態をつくのであった。
これには思わずクレスも「こら!」と慌てて凪を叱るのだが、天帝は構わず大声を上げて笑う。
「はっはっは!その通りだからなんとも言い返せん。……凪がそうやって我に反抗的なのも、アルタイルの意思がその内に宿っているからなのであろうな」
「さあ、どうでしょうね」
凪はふふ、と意味ありげに笑って返すと、すぐに天帝に背を向けシリウス達の方へ行ってしまった。
「では、出発しましょう。転移術を使います」
テティスが皆を一箇所に集めると、すぐに詠唱を始める。そして一瞬のうちに全員その場から消え、静かになった謁見の間には天帝が一人残された。
「……我とて、二人を無理矢理引き離すなど、本当はしたくはなかったのだがな……。織女星の力……何故、そのような忌まわしい力が我が孫につきまとう運命なのか……」
天帝のその苦悩のような呟きは、静寂の中へ吸い込まれるように消えていった。
奏はゆっくりと目を開いた。
なんだかとても懐かしく、そして哀しい夢を見ていたような気がする。
ふかふかのベッドの中でぼんやりとしながら目線だけを動かすと、そこには自分のよく知る、大好きな人の姿があった。
──そうだ、彼は、大好きな、俺(わたし)の……
「……目が覚めたか」
鶲は目を覚ました奏に、優しく声をかける。すると奏はゆっくり体を起こすと鶲の首に両腕を回し、縋るように彼を抱きしめたのだ。
「……ひ、た……き……」
「!七海、もしや記憶が……!?」
掠れた声で名を呼ばれ、鶲は確かめるように奏の瞳を見つめる。しかし奏の意識はまだ朦朧としているようで、奏の紫の瞳は再びゆっくりと閉じ
「……かお、る……」
と、別の名を呼ぶ。「かおる」とは、確か悠達が気にかけていた妖精だったか。
「……記憶が混同しているのか……そういえばお前、怪我は……」
「……?」
楸が回復魔術をかけたものの完治させるまでには至らなかった顔の傷跡が、いつの間にか綺麗に無くなっていることに鶲は気付いた。巻かれていた頭の包帯を解き、酷かった頭の傷も確認するとすっかり完治しており、茨によって切られた髪も元の長さに戻っていた。
「自然治癒……なんて回復力だ……!」
おそらく、奏の持つ五行術の一つ、水の力だ。水の力が術者を守るために、強い治癒能力を持つ精霊を召喚し、奏の体の傷をたちどころに治してしまったのだろう。
「七海、もっと顔を見せてくれ。美しいお前の顔を……七海、今度こそ、お前は俺のものだ」
「……」
奏の両頬に手を添え、まるで口付けを交わすかのように鶲が顔を近付けたその時、奏の意識は瞬時に覚醒した。
「……!違う!」
「っ!?」
「違う、俺は……七海じゃ……俺は誰のものにもならない……!なっちゃいけないんだ!!」
奏に勢いよく突き飛ばされた鶲であったが、どうやらまだ「奏」としての心が七海の心と混ざり、非常に不安定な状態となっているらしい。奏であるのに「七海」として扱われたのが気に入らないのか、それともあの頃の「掟」とやらを七海はまだ覚えているのか……。
どちらにせよ、あともう少しだ、と鶲は内心喜んでいた。
そして再び奏を抱き寄せると、その耳元でまるで誘うかのように優しく囁きかける。
「……いいんだ、今度は。お前のその力を使って、俺達以外の全てを消してしまおう」
「え……」
「そうすれば、お前は永遠に俺のものになれる。もう、お前に寂しい思いなど絶対にさせない」
「……本当、に……?」
先程まではっきりとしていた「奏」の瞳が、少しずつ虚ろになっていくのがわかった。
あと少し。あと少しで、奏(七海)は自分の元に戻ってくる……。
「ああ……俺の敵を……天帝を倒すんだ。俺を助けてくれ。俺に……力を貸してくれ」
「……ひたきの……敵……鶲の為に……俺の、力を……」
奏は鶲に連れられ、神殿からベガの外が見渡せる広い窓の傍に立たされた。
そして奏の虚ろな瞳に映ったのは、遥か遠方、奏を探しにベガへ到着したばかりの馨達の姿だった。
ベガに降り立った馨達は、ひとまずどのようにして奏を探すか作戦を練っていた。
ベガにいる、というところまで特定はしたものの、ベガも大きな星であるし、クリスタルフラワーが咲いている泉はベガではよく見る光景である。実際、今馨達が立っている場所にもクリスタルフラワーが足元に所狭しと咲き誇っている。
ひとまず悠が奏の力の気配を探ろうとしてくれているようだが、かなり遠くにいるようで気配はまだ小さく、どの方角にいるかも特定が困難な状態らしい。
「ではまず、手分けして探すのはどうだろうか。見つかったらテティスには悪いが皆を一箇所に召喚してもらうというのは」
にっちもさっちもいかない状態の中、クレスが一つ提案を出した。その提案に凪とテティスも頷く。
「それが効率いいかもしれませんね」
「僕は構いません。シリウス様はどうでしょう」
「うん、いい案だと思う。では、四手に分かれ、それぞれに星の精をつけよう。私達は離れたところでも意思疎通が取れるから、それで連絡を取り合えばいい」
「よし、じゃあそうしよう!急ぐぞ!」
チーム分けも決まり、馨が走り出そうとしたその時、すぐ隣にいた紅袮が何かを察知した。
「……!待って、危ない!」
「へ……?」
紅袮の叫び声と同時、馨の目の前を大きな影が覆った。それが馨のすぐ横に建てられている柱だということに気付いた時には、柱は馨の目の前に大きな音と水飛沫を立てて倒れていた。
「な……一体何が起きたんだ……!?」
「危なかった……今一歩気付くのが遅ければ、皆柱の下敷きになっていたぞ」
皆が気が付くと、柱は粉々になって泉の底に沈んでいた。どうやら間一髪のところでシリウスが結界を張り、皆を守ってくれていたらしい。柱はシリウスの結界にぶつかり、その衝撃で砕け散ったようだった。
皆が口々にシリウスへ礼を言う中、蘇芳は不思議そうに砕けた柱を眺めていた。
「しかし、どうして突然……ベガの建築物は全て特殊な技術で作られているから、ちょっとやそっとの攻撃魔術では壊れないようになっているはずなのですが……」
ベガはかつて地球のディレイス皇国と交流があった際、そこでの文化や文明を多く取り入れそれが現在までこの国に伝わっている。今ある建築物の多くも古くから残る所謂イオニア式の建物が多いのだが、それが国の誇れる景観の一つでもある為、定期的に国の建築士達が特殊な魔術を施しメンテナンスを行っている。それ故に多少の老朽化が進んでいても自然と崩れたりすることは滅多にない。
「この柱が倒れる直前、ものすごく強い力を感じた……一瞬だったから、よくわからないんだけど……」
紅袮も蘇芳の隣で粉々になった柱を見つめている。そんな二人が気になったのか、杏も様子を見にこちらへやってきた。そしてすぐに何かに気付く。
「待って、これ……微かだけど、奏の力を感じる……!」
杏の声を聞きつけ、馨や悠達も集まってきた。
「本当か!?」
「……これは、砕けるというより、消す、力だ。奏だと思う」
悠の言う通り、残骸の一部がまるで腐蝕しているかのように変色しており、そこから砂のように崩れ消えようとしていた。明らかに普通の攻撃魔術ではないのがわかる。
「……攻撃が飛んできた方角は……崩れ方を見るとどうやら西の方角のようですね」
かろうじて残っている土台を観察し、凪は呟いた。
「じゃあ、とりあえず西へ進んでみよう」
馨が歩みを進めようとしたその時、悠が珍しく大きな声で皆を制止した。
「待って」
「……どうした、悠」
星が不思議そうに首を傾げるが、悠は構わず足元の消えかけている柱の残骸を手に取った。
虚空に消えていくそれを見つめながら、悠は静かに話し始める。
「この奏の力……多分、俺達を狙って攻撃したのだと思う」
「な、なんだって……!?」
馨は勿論、その場にいる全員が驚き、そして言葉を失くした。
「俺も信じたくないけど……街ではなく、敢えて人気のないこんな場所をこんな威力で狙ってきたんだ。それにこの力の気配……もう、織女星の力が覚醒してしまっている可能性が高い」
「そ、それじゃあ、もし奏を見つけたとしても……」
「敵とみなして、僕達を攻撃してくる可能性が高い……ということだね」
紅袮と響の言葉に、悠はゆっくりと頷いた。
「もし……奏が織女星として覚醒してしまっていた場合……今の奏の不安定な五行術は天帝様をも凌ぐ力となっている可能性がある。そうなれば、私とクレス達三国の長の力でなんとかするしかない」
シリウスは苦い顔をした。負の力に染まった五行術を相手にするのはシリウスも初めてであるし、正直、自分やクレス達の力をもってしても敵うかどうかはわからない。何せ天帝の力をも凌ぐと言われている力なのだ。
これはかなりまずい状況かもしれない、とシリウスは唇を噛んだ。
その横で、皆の話を聞いていた馨は呆然とその場に立ち尽くしている。
「なんで……なんで奏と戦わなくちゃいけないんだよ……」
「そうなってしまった場合、だ。まだ決まったわけではない」
「とにかく急ぎましょう!もう悠長なことを言っていられる場合ではないのかもしれません!」
いまだ悠の言葉を受け入れられずにいる馨の背を押し、クレスと凪は走り出した。続けて他の皆も二人の後を追う。
「向こうには確か森があります。森の奥に神殿があると言い伝えられてますが……」
西の方角へ走りながら、蘇芳が叫んだ。その言葉で悠が何かに気付いたようにはっとした表情を見せる。
「!神殿……そうか、七海が封印された神殿だ……!」
「あの神殿に……!?そんな伝承、聞かされたことがないぞ!あそこは近づくと妙な磁場が発生する場所でな、気が付くと森の入り口に戻されてしまっているんだ」
街外れの森の中に隠された神殿がある、という話はこのベガに住む妖精であれば誰もが知っている都市伝説であった。実際は誰もそこへ辿り着けたことはなく、それに関する文献もない。噂だけがこの世に残り、その神殿がどんな神殿なのかクレスも全く知らないという。
「天帝が七海に施した封印の一部がまだ生きているのか……」
悠は呟いた。その磁場というのも、おそらく天帝が七海に二度目の封印術を施した時の一部で、外部から何者かが侵入できないようにしたのだろう。
「紅袮君、磁場は僕達の力で消しましょう」
「うん……!」
蘇芳の提案に、紅袮も頷く。蘇芳と紅袮が力を合わせた「真の蘇生術」であれば、天帝が施した磁場くらいなら簡単に消し去ることができるだろう。
「奏……奏……!今、皆でお前を迎えに行くからな……!」
まだ遠くにいるであろう奏に語りかけるように、馨は呟いた。
「……」
奏は手を翳したまま、虚ろな眼差しでその先を見つめていた。
窓から見える、ここより遥か遠くの森の向こうで大きな何かが壊れる音と水飛沫の音を聞いた気がした。
それが自分の放った力によるものだと気付いたのは、隣にいる鶲がそれを見て嬉しそうに声を上げた時だった。
「……素晴らしい……!!これがお前の力なのか……!この力さえあれば、この宇宙だって全て手に入れることができてしまいそうだ……なあ、そう思わないか、七海」
奏は自分の背筋にゾクリと冷たいものが走るのを感じる。力を放った時の記憶が、奏には残っていなかった。自分の意識が戻ったのは、遠くで大きな音が響いた時。
きっと、七海だ。鶲の声に応えるように、七海が奏の力を使ったのだ。
このままでは、七海に自分の心を、体を、取られてしまう……。
そう危惧した奏だったが、気付いた時にはもう遅かった。奏の体は既にほとんど奏の意思で動かすことができなくなってしまっていたのである。
「ちょお、今外ですごい音したんやけど、何しよったん!?」
先程の音を聞いたらしい楸が慌てて二人の元にやってきた。そんな楸の声も、奏の耳にはもう微かにしか届かない。
「奏が織女星……七海として覚醒した。これで七海も、七海の力も俺のものだ」
「はあ……喜ぶのはええですけど、あんまり奏に無茶させへんようにしてくださいよ。まだ体も精神も……心も、不安定な状態なんですから……このまま無茶されはったら、奏が壊れてまう」
「……わかっているさ。なあ、七海……愛しい、俺の七海……」
鶲は奏の肩を抱き寄せる。少し前まではすぐに奏が抵抗していたはずだが、今はもう鶲のされるがまま抱きしめられ、奏は虚ろな瞳で窓の外を見つめていた。
それを見た楸は、もう奏の体はほとんど七海に支配されてしまっていることに気付いた。
(まずい、このままやとほんまに奏の心が壊れてまう……悠、はよ戻ってきてくれ……!)
「織女星の消す力、ってなんなんだ?」
森へ向かって足を進めている最中、ふと疑問に思った星が紅袮に尋ねた。
「ん……?」
「だって、五行の力は木、土、水、火、金の五つの力だろ?自然の力だ。それがどうして、自然を壊すような……「消去」の力になってしまうんだろうなって」
訊かれた紅袮もよくわからないようで、うーん、と首を捻っているようだった。そんな二人の様子を見ていた響が二人に話し始める。
「光の三原色って知ってるかい?」
「え?」
響の問いかけに二人が再び首を傾げていると、
「響のそのたとえ、わかりやすい」
と言いながら悠が話にまざる。
「赤と緑と青……その三色の光が一箇所に集まると、無色になる。織女星の消去の力はその原理にとても近い」
「五行の力が一つに合わさることで、自然の力が無色…まあ、この場合は全てを拒絶する「消去」の力になる……それは、悲しみや憎しみ等で心が乱れた時、元々引かれ合う性質にある織女星の五行の力のバランスが取れなくなってしまう為に起こる。そうだね?悠」
「そう……だから、今の奏の心は……とても不安定で、悲しんでいる。でも、心があっても織女星としての意思……七海の記憶。それが目覚めなければ、特に問題はないのだけど、何がきかっけで思い出してしまうかわからなかったし、何より鶲の存在があったから……悲劇は避けようがない、と俺は思った。多分、奏はもうブロックされてしまっていた七海としての記憶を、鶲の存在の影響で思い出してしまって、完全に織女星として目覚めてしまっている」
悠はそう言って目を伏せた。
自分も、奏がそうなってしまったきっかけを作った一人でもある。それを悠は後ろめたく思っていた。
あの時、自分が急いて奏を追い詰めなければ……奏があの森に迷い込んで、魔物の命を奪うこともなかっただろう。そして、それによって心を傷つけることも……。
「心、かあ……そういや、俺が最初に奏をあの森で見つけた時は、今よりめちゃくちゃ無表情で、何話すにも淡々としてたな。まるで本当に心が無いみたいな……」
悠の話を聞いて、初めて奏を見つけた時のことを星は思い出す。
紅袮と共に感じた最初の奏の印象はといえば「人形のような子」だった。
そんな印象を抱くくらい、あの頃の奏には感情というものがなかった。何度か会話を交わし、共に遊んだりすることですぐに人間らしさを見せてくれるようにはなったのだが。
その頃の奏をよく知っているクレスも頷いた。
「以前に比べて、奏の心に変化があったのは間違いないな。天帝様に聞いたところ、七海が生まれた時は元々心が無かったのが、奏に転生した時は既に存在していたそうだから。本来であれば奏も心を持たずに生まれてくるはずだったのが、七海の心が芽生えてしまったばかりに……転生しても、心を手放すことができなかったのだろう」
「七海の過去を考えると、生まれた時から悲運が決まっていたようなものだったわけですね、奏くんは……」
あまりに気の毒すぎる奏の未来に、凪は言葉を詰まらせる。
「それで織女星の本来の業務から遠ざけ、事情を知っている重臣に義理の親として……あのような森の奥に家を用意してひっそりと育てさせたわけか……できるだけ、他人との関わりを避けるように」
「!あの家、天帝様が作ったのか!?どうりで広すぎると思ってた!」
シリウスの話を聞いた馨は、また一つ気になっていたことがわかって思わず声を上げてしまう。シリウスはおかしそうに笑うと
「あの御方は生まれた時からあの巨大な天宮に住まわれているからな、少人数が暮らすための家の規模など、わからなかったのかもしれん」
と続けた。
しかし、あの家が広すぎたお陰でこうして半年間、奏と生活を共にできて、馨達は奏のことをたくさん知ることができた。故に奏の心が以前よりも豊かになるきっかけを作ってしまったわけでもあるのだが、天帝はおそらくそのようなことになるなど全く想像していなかったのだろう。
そうこうしているうちに、一同は突如現れた森の前に到着した。今までの場所とは比べ物にならない程のクリスタルフラワーが群生し、星明かりを浴びてまるで何かを守るかのように七色に光る花弁を輝かせている。
「ここが例の森ですか……」
ただならぬ力を察知し、テティスは顔をしかめる。その隣で凪も同じように顔を歪め、森の様子を眺めていた。目の前に鬱蒼と生い茂るその森は、森であるはずなのに生き物の気配が全く感じられなかった。
「確かに……なんだか変わった力を感じます。普通の妖精や生き物が近づいたら、心も体も正常を保てなくなる程の強い磁場……とても、危険な場所です」
「前に一度俺が調査に入ったことがあるんだが、結局神殿に辿り着けずじまいだったよ。だから奥に本当に神殿があるのか……何があるのかもわからない」
クレス程の力を持つ者でさえ、この森の磁場に方向感覚を狂わされてしまうらしい。
「慎重に進みましょう。紅袮君、手を」
「うん」
蘇芳が差し出した手を紅袮が取る。そして二人が空いた方の手を目の前に翳すと、現れた光がその場に風を起こした。その風はただの風ではなく、二人の「真の蘇生術」の力が空気の中に混ざっている磁場を「磁場が発生する前の状態に蘇らせて」消しているのだ。一時的ではあるが、こうすることで磁場の影響を受けることなく目的地へたどり着くことができる。
「……なんか、ブレウス星に突入した時のことを思い出すな。あの時もこうやって、蘇芳と紅袮が手をつないで、瘴気を無にして……」
星は、かつての戦いの時のことを思い出していた。
以前自分達の敵であったブレウスが根城としていた星はとても濃い悪性の瘴気が外部を覆っていて、中に侵入するにはその瘴気を突破する必要があった。その瘴気の中を進む為に、蘇芳と紅袮が力を合わせることで発動できる「真の蘇生術」の力を使い、一同はクリスタルの英雄達と共にブレウス星内へ侵入することができたのである。
「まさかまた、天帝様を狙う敵が現れるなんてね」
響がぽつりと呟いた。
あの時のブレウスの真の目的は、天帝が封印した黒帝を蘇らせ、天帝を排除するというものであった。その目論見は勿論、クリスタルの英雄達の活躍によって打ち砕かれてしまったのだが。
響の呟きを聞いた凪は真顔で、冷たく言い放った。
「神は人の心がわからない……ああいう神ですから、敵を作りやすいんですよ。まだまだどこかに天帝の命を狙ってる輩がいるかもしれませんよ。私とか。ふふ」
「お前が言うと冗談に聞こえないからやめてくれ」
最後の凪の意味深な笑みにゾクリとし、クレスは思わず凪を叱った。
そこから少し離れた森の中心部。
かつて七海が封印されていた神殿の中に、奏はいた。
既に奏の意識は七海によって抑え込まれてしまっているのか、大人しく鶲に身を委ね、鶲が髪を撫でると気持ちよさそうに目を閉じている。
ふと、鶲は何かの気配に気付いて顔を上げた。
「……」
「……?どないしました?」
少し離れたところで二人の様子を見ていた楸が、鶲の行動に首を傾げる。
「……どうやら、お客さんが来てくれたみたいだな」
「へ……?まさか悠達か……!」
楸は慌てて窓から外を見渡してみる。確かに、何か強い力の気配がこちらに近づいてくるのを微かに感じた。
「アルタイルの……俺の作った力が、あの森の磁場を消しているみたいだな。楸、丁重にもてなしてやってくれ」
そう言うと、鶲は奏を連れて奥の部屋へ入っていく。
「悠はともかく、悠以外も迎え入れてもうてええんですか」
「ダメだ、といったところで奴らは諦めないだろう。俺のものになった七海の姿でも見てもらったらお引取り願おうか」
不敵な笑みを残し、鶲は部屋の扉を閉めた。
扉の閉まる音と共にその場に取り残された楸は、焦っていた。鶲が何を企んでいるのか、何をしようとしているのか。楸は自分が視た鶲の念を通じて、全てわかってしまったのである。
(あかん……あの人、七海の力使うて全員消すつもりや……もう、どないしたら……)
完全に覚醒した七海の力を止めることは、最早容易ではないだろう。その力は天帝の力をも凌ぐのだから。
天帝、あるいは三神星が力を合わせれば、とも考えたが、三神星のうちシリウスはともかく、他二人は他銀河を統括している神だ。今から協力してもらうのも難しいだろう。
楸はとにかく、祈ることしかできなかった。
第七章 【鶲と七海】 完