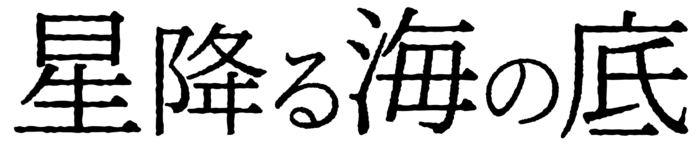第六章【真相】
昔々、遥か上空の宇宙の世界で、天帝様の孫娘、織女星がベガ星の精霊として誕生しました。
名は「七海」
七海はとても美しく成長し、生まれ持った力で人々を癒やし、ベガに繁栄をもたらしていました。
しかし、七海の持つ力には秘密がありました。
「五行術は主の心の影響を受けやすい。七海、それ故にお前は心を持たぬのだ。この先、何があろうとも決して己を誰かに預けてはいけない。心を開いてはいけない。そして、お前は誰のものにもなってはいけない。……もし、お前の心が目覚め、負の感情に蝕まれることがあれば……お前の五行の力はお前の手を離れ、全てを消滅させるだろう」
天帝様の言いつけを守り、七海は毎日、ただベガの繁栄を祈るためだけに力を使いました。
しかしある日、七海は運命の人と巡り合ってしまったのです……──
すこん!
「……?」
小気味良い音を立て、七海の頭上に何かが落ちてきた。
じわりと痛む頭をさすりながら足元を見ると、そこには一個の大きく真っ赤な林檎が転がっている。
その林檎を拾い、七海はじっくりとそれを見つめていた。
するとほどなくして、頭上から今度は林檎ではなく人の声が降ってくる。
「うわ、下に人がいたのか!悪かったな、林檎、頭に直撃しただろ」
七海が上を見上げると、すぐ隣に生えていた大きな林檎の木の上に一人の青年がいた。両手にたくさんの林檎を抱えていて、この林檎を落としたのも彼なのだろう。
彼は慣れたように木から降りてくると、心配そうに七海を見つめた。
「……大丈夫……」
「いや、ほんとに大丈夫か?結構高いところから落としたし、音がしたの聞こえたし……」
「……」
七海は彼の話を聞いてはいたが、どこか虚ろな眼差しで首を傾げる。
七海のそのなんとも言えない反応に困ったその青年は頬をポリポリと掻きながら
「そうだ、あんた、名前は?」
と問いかけた。
それでも七海は先程の無表情を全く崩すことなく
「七海……」
と、淡々と自分の名を口にする。
「七海っていうのか、いい名前だな!俺は鶲。アルタイルの星の精なんだけど、ちょっと用があってベガに来てて」
「……ひたき……」
鶲も続けて自己紹介をすると、七海はぽつりと彼の名前を復唱した。反応はやはり薄い。
アルタイルの星の精と聞けば多少は驚いたり何かしらのリアクションを見せてくれると考えていたのだが、七海はそれでも無表情のまま、鶲をじっと見つめている。
調子が狂うな……と思いながらも、七海が自分の名を呼んでくれたのが、鶲はなぜだか嬉しかった。
「七海、一人なのか?よかったらベガを案内してほしいんだけど……七海の好きなところとか、楽しい場所とか」
「……すき……?たの、しい……?」
鶲の言葉に、七海は再び首を傾げる。
「ん?よくわからないのか?うーん……まあいいや、とにかく一緒に行こう!一人より二人の方が寂しくないし、楽しいからな」
「寂しく、ない……二人なら……?」
「そうさ、一人ぼっちより、誰かと一緒の方が楽しいから俺は好きだな。だから一緒に行こうぜ!ああ、あとその林檎もやる」
そう言って、鶲は七海がずっと持っていた、自分が先程落としてしまった林檎を指差した。
「?」
「こうやって丸かじりして食べるとうまいぞ。食ったことないのか?」
首を傾げて林檎を見つめている七海の眼の前で、鶲は豪快に林檎に齧り付いてみせた。それを見た七海も、鶲の真似をしてゆっくりと林檎に歯を立ててみる。
「……おいしい……」
その時、無表情だった七海の顔に少しだけ笑顔が宿ったような気がした。たった一瞬の出来事で、笑顔はすぐに先程までの無表情に塗り替えられてしまったが。
それでも、ほんの少しでも七海の笑顔を見ることができた鶲は、それが嬉しくてたまらないのだった。
「よし、じゃあ街へ行こう!」
鶲は七海の手を引き、ベガの街へ向かって走り出した。
ベガの街はとても活気に溢れていた。
泉の水はとても綺麗で、作物もよく育つのだと街の人々は嬉しそうに語り、笑顔が絶えない。
ベガには「クリスタル」という星の力の源である結晶が存在しているというのだが、そのクリスタルにベガの星の精である織女星が自らの力を送り込むことで、ベガの国は栄えているのだという。
ふうん、と店で買った花びらの砂糖漬けを食べながら、鶲は店主の話を聞いていた。すると店主は、鶲の後ろに立ってじっと商品を見つめている七海の姿に気付き、慌てて頭を下げた。
「こ、これは七海様……!もう、いらしてたなら言ってくださいな!七海様のお友達でしたら特別にサービスしてあげちゃいますからね!」
「え、ほんと?ありがとう!」
様々なお菓子を色々とつけてもらい、鶲は礼を言って七海と共にその店を出る。
その後も様々な店を覗いたが、皆七海の姿を見るや深々と頭を下げ、中には拝むものまでいた。店内だけでなく、街を歩いているだけですれ違う人達から頭を下げられる。これではまるで大名行列か何かのようだ。
「え、何?どういうこと……?」
流石に鶲が不思議に思っていると、一人の子供が七海に手を振りながら
「織女星さまー!いつもありがとーー!!」
と叫んだのである。
鶲はここでようやく七海の正体に気付いたのだった。
街から元いた場所へ戻ってくると、そこはベガの宮殿から少し離れた裏庭だったということを鶲は知った。七海はおそらくこの裏庭で散歩でもしていたのだろう。
鶲はといえば、仕事の為にベガへ来たもののもっとベガを見て回りたい!という欲求から、付き人の目を盗んであの林檎の木の上に隠れていたのだ。
「びっくりした……街の人達が皆頭下げてくるから何かと思ったら、お前実は天帝様の孫娘の織女星様だったのか」
鶲の言葉に、七海は静かに頷いた。
天帝が創ったベガ星から生まれた星の精。
この宇宙にはたくさんの星が存在しているが、その多くは天帝直属の部下である天星達が創ったものであり、天帝の手で直接創られた星はほんのわずかしかない。
その星から生まれた星の精である織女星、七海は天帝から見れば孫娘にあたり、その立場は同じ星の精とはいえ鶲に比べれば遥かに上だ。
とんでもない人を連れ回してしまった……と鶲は頭を抱えた。
「知らなかったとはいえ、なんか馴れ馴れしくしちまった……その、ごめんな」
鶲は謝罪するが、七海は相変わらずの無表情で首を横に振る。七海自身は全く気に留めていないのだろう。
そのことに少しホッとした鶲は、改めて時刻を確認し「ギャッ」と声を上げた。会議の時間が目前に迫っていたのである。このままでは付き人に雷を落とされてしまうだろう。
「あ、じゃあ俺、今日はもう行くな!」
「……あ……」
鶲が慌ててその場から立ち去ろうとすると、七海が鶲の服の裾を掴んだ。
「ん?」
思わず振り返ると、七海は何故このような行動をしてしまったのか自分でも理解出来ていない様子で、鶲の服を掴んだまま目を瞬かせていた。
「どうしたんだ、七海」
鶲が訊ねると、七海は何かを言いかけて口を開くが「これは違う」とでも言いたげに首を振るのを何度か繰り返した後、ようやく
「……たのし、かった……」
という言葉を口にした。
その時、鶲は自分の胸が大きく高鳴るのを感じた。同時、七海のことは何故か放っておけないという庇護欲が湧いてくる。
尚も何か言いかけようとしてうまく言葉に出来ず首を傾げている七海の頭を、鶲は軽く撫でてやる。
「七海。あのさ、明日もまた来ていいか?」
そう言うと、七海は先程見せた微かな笑顔とは比べ物にならないほど、はっきりとした笑顔を浮かべて頷いたのだ。
「俺も仕事があるから明日は少し遅くなっちまうかもだけど……待っててくれな」
「……うん」
こうして二人は逢瀬を重ね、二人の間には少しずつ特別な感情が芽生えていきました。
そしてそれは、心を持たなかった七海にも少しずつ変化をもたらしていったのです。
「今年は豊作だ!これも全て七海様のお陰だな!」
「ええ、水も土も空気もとても綺麗になって作物がよく育つし、本当にありがたいわ!」
ベガの街は更に活気で溢れかえっていた。
街は常に祭りでも開催されているかのように賑やかに人が行き交い、商売人達の声が高らかに響く。
久しぶりに孫娘の様子を見に来た天帝は、そんなベガの街を横目に眺めながらベガの宮殿に足を運んだ。
「お爺さま」
天帝が宮殿に姿を見せると、真っ先に七海が出迎えてくれた。その時、天帝は既に七海に異変が起きていることに気付いていた。
「……最近ベガの街が栄えているようだな。これも皆、お前がよく働いてくれているからだ。誇ってもいいのだぞ」
天帝に褒められ、七海は嬉しそうに、そして照れくさそうに笑った。
「いいえ、これは全部、鶲のお陰だから……」
「鶲……?アルタイルの牽牛星か?」
天帝が訊き返すと、七海は「しまった」といったように口を両手で塞いだが時すでに遅し。そのまま指先をもじもじとさせると、頬を僅かに赤く染めながら
「仲良くなったの。鶲と一緒に過ごす時間がとてもたのしくて……力も、それに応えてくれているみたい」
と告白した。
そう語る七海の表情は、今までに見たことがないほどの幸せそうな笑顔で、天帝は思わず目を見開いた。まさか、愛する孫娘のこのような表情を見られる時が来るとは思ってもいなかったのだ。
だが同時に、天帝は心の中で危機を察知する。それはいつもの笑顔で隠し、天帝は七海の頭を優しく撫でた。
「……そうか、それはよかった。クリスタルの様子を見に行ってくる。またあとでゆっくりと話を聞こう」
「はい、お爺さま」
七海に笑顔で見送られ、天帝はその場を後にした。
先程まで七海に向けていた笑顔から何かを思案するような表情へ変えると、深刻そうに、そして自分にしか聞こえないくらいの小さな声で天帝は呟く。
「まずい、七海の心が、感情が……目覚めてしまっている……。今はまだ問題はないようだが、はたしてこのまま、吉と出るか凶と出るか……。アルタイルの星の精、鶲、か……十分警戒しておかなくては」
どうか、七海のあの笑顔をずっと見守ってあげられるようにと、天帝はそう願わずにはいられなかった。
それから数ヶ月の時が経った。
ベガは相変わらず問題なく栄えていたが、一方でアルタイルには僅かな異変が起きていた。
元々アルタイルには魔力と相性の悪い動植物が多く存在しており、変質して凶暴化した魔物が現れることが多かった。昔からのことなので鶲も国民たちも駆除には慣れているのだが、それがここ最近頻繁になってきたのだ。
鶲はその処理に追われ、ベガへ足を運べる機会が少なくなっていた。
「七海、元気してたか?」
久方ぶりにベガへ顔を出した鶲の姿を見た瞬間、七海は思わず鶲に抱きついた。
「鶲……!最近来ないから、心配してた……」
「ごめん、ちょっと今国がごたついててさ、一応星の精だから俺もなんとかしなきゃいけなくて、忙しかったんだ」
抱きついてきた七海の髪を撫で、鶲も申し訳なさそうに答える。
「鶲……」
「寂しかったか?」
「うん……」
星の精として、やらなければいけないことがたくさんあるのは同じ星の精でもある七海にもよくわかっている。勿論、そちらを優先しなければいけないということも。
自分達は星の精。何よりも自分の星と、その星に住む人々を大切にしなければいけない。ただの人のように、ここで私情を持ち込むわけにはいかないのだ。
それでも……──
「……なあ、七海」
鶲の声に顔をあげると、そこにはいつになく真剣な鶲の顔があった。
「俺、お前が好きだ」
「……!」
「会えない間、ずっと七海のことばかり考えてた……それで俺、お前への気持ちに気付いて……ずっと、一緒にいたいって思ったんだ」
鶲の告白に七海は驚いて目を見開いた。そしてそれは、七海もずっと鶲に伝えたくて胸に秘めていた想いだったのだ。
「私……私も!鶲が好き。鶲と一緒にいると胸のあたりがあったかくなって……多分、これが好きってことなんだと思う……私もずっと、鶲の傍にいたい……」
七海は自分の想いを、全てを言葉にして鶲に伝えた。
それを聞いた鶲は、感極まって七海を強く抱きしめてしまう。少し苦しそうに呻いた七海に慌てて
「ご、ごめん」と謝ると
「七海、お前は俺のものだからな……いつか、夫婦になろう」
と続けた。鶲の言葉に、七海も嬉しさで涙を滲ませながら応えた。
「……うん……」
こうして二人は結ばれ、幸せになるかと思われたのですが。が、ここから少しずつ、二人の悲劇へのカウントダウンは始まっていったのでした……──
あれだけ栄えていたベガに、暗雲がかかりはじめたのはそれから少し後のことだった。
空気が悪くなり、泉の水も濁り始め、草木は枯れる。
「最近作物の育ちが悪いなあ……」
「治安も悪くなってきたし……七海様も最近はあまりお姿をお見せにならない……何かあったのかしらねえ」
国の人々の表情からは活気が失われ、皆心配そうに宮殿を見つめるのだった。
その頃、七海は宮殿の一番奥の庭園で鶲と会っていた。
この庭園は人があまり来ないためひっそりと静まり返っている。二人はいつもこの場所で逢瀬を重ねていたのだ。
「鶲……今日も少ししか一緒にいられないの……?」
七海は悲しそうに顔を歪め、鶲を見つめた。鶲はやはり申し訳なさそうに目を閉じ、七海の肩を抱き寄せてやる。
「ごめんな、最近アルタイル国内がとても荒れてて、それを治めるのに忙しいんだ。できることなら俺ももっと七海の傍にいてやりたいんだけど……」
星の精として、国と国民の危機は見過ごす訳にはいかない。鶲は責任感の強い人物であったから、毎日寝る間も惜しんで脅威の要因を取り除こうと働いていた。
鶲がそういった努力を重ねていることも七海にはよくわかっている。だが、一度「幸せ」を知ってしまった七海にとって、今のこの感情はとても苦しいものだった。
「ベガも最近治安が悪くなってるって聞いてるぞ。お前の力で皆を元気にしてやれ」
「……でも、私……鶲と逢えないと寂しくて……」
鶲は笑顔で話すが、七海は憂いを帯びた表情で俯いてしまった。
「寂しい」「悲しい」──鶲と出逢って「楽しい」「幸せ」という感情を知るまでは、七海には無縁の感情だった。七海には心がなかったからだ。心がなかったから、一人でも平気だった。心がなかったから、涙を流すことも知らなかった。
鶲と出逢ったことで、七海は少しずつ感情というものを知り、いつの間にか完全に心が芽生えてしまっていたのだ。
そしてその幸せの反対にある感情は、七海の心を強く蝕んでいった。
最近、七海の元気が無いことに鶲は気付いていた。勿論それは自分のせいでもあるし、なんとかしてやりたいと思っているのだが。
「七海は、俺と一緒だと元気が出るのか?」
「うん。鶲が傍にいると、とても幸せな気持ちになれるから」
その時、鶲の脳裏に一つの考えが思い浮かんだ。
「そうだ!それじゃあ俺に力を貸して欲しい!七海のその力で、俺の星を助ける手伝いをしてくれないか?」
七海はきょとんとした。自分の力といえば、クリスタルに自分の力を与え、国全体に自然のエネルギーを行き渡らせること。クリスタルに分け与えるという用途以外では、草木や動物達を癒やしたり、水を綺麗にしたり、浄化したりすることができる。完全なる自然の力だった。
「私の……この力で……」
「ああ。アルタイルの今の現状が少しでも収まってくれれば、俺も今より時間が取れるようになると思うし……そうすれば、また七海にもたくさん逢いに行けるだろ?」
「……わかった。私の力、鶲の為に使う」
鶲に頼られ、七海は嬉しそうに強く頷いた。自分の力が愛する人の為になるのなら、自分は迷うことなくこの力を使おう。そしてアルタイルにも、自分達にも平和が戻ってくれれば──
七海はそう強く願うあまり、生まれたばかりの時に天帝から強く言い聞かせられていた「掟」を失念してしまっていた。
「ありがとう!七海!」
鶲は七海を強く抱きしめる。
それが最悪な悲劇の始まりであることも知らずに……──
「これが、今のアルタイル……」
アルタイルを訪れた七海は、その惨状を見て息を呑んだ。
街を埋め尽くすように伸びきった巨大な茨。危険植物の類と、変質した魔物達。
国民達は魔物相手に武器を振るったり魔術で追い払ったり様々な方法を試みているが、完全に追い詰められているようである。
「原因不明の茨が成長して、少しずつ駆除してたんだけどみるみるうちに増えていってしまってな……こいつが厄介なことに、危険な植物や魔物を大量に生み出す。そのせいで今、アルタイルの国民達は怯えきってしまってる。俺もなんとかしようと頑張ってるんだけど……」
アルタイルの魔力で変質し、凶暴化してしまった動植物達。元凶であるあの巨大な茨が持つ悪に変質した魔力を、七海の力で浄化できないかということであった。
「私の力で……あの茨を浄化する……」
「ああ、頼む、七海。皆、大丈夫か!」
鶲は国民達が対峙している魔物達を呪術で焼き払って助けると、その場に降り立った。
鶲に助けられた彼らは鶲の姿を見、安堵しきった表情で鶲の下に集まってくる。
「鶲様!ありがとうございます……!」
「鶲様~!もうこの星は限界です!このままわけわからん植物に覆われてアルタイルは滅亡しちまうんだ……!」
「馬鹿言うな!俺が俺の星を、皆を、そうやすやすと滅ぼさせたりはしない!今日は救世主を連れてきたんだ!」
そう言うと鶲は自分の後ろに控えていた七海を紹介した。
七海の姿を見、人々は次々と驚いたように目を見開き、頭を垂れた。
「!あ、ああ……!七海様……!」
「天帝様の孫娘の……あの七海様だ……!」
やはり、七海の存在はとても強い。何せあの天帝の孫娘だ。となれば相当強い力を持っているだろうと皆思うし、彼女であればこの状況を打破できるだろうという希望が見えてくる。実際、七海の持つ力は底知れないのだから。
七海を目の前に出しただけで、あれだけ疲弊しきっていた国民達の表情が少しだけ明るくなった。
「七海の力で、このアルタイルに巣食う悪しき生命体を全部浄化してもらうんだ。七海にはそれをできるだけの力がある」
「ほ、本当ですか……!?七海様、是非、是非ともよろしくお願いします……!この星を……私達を救ってください……!」
アルタイルの民達は、七海に向かって深々と頭を下げた。
「七海、いけるか?」
「うん……やってみる」
鶲や、彼の民達にこれだけ期待をされているのだ。やらないわけにはいかない。
七海は気を集中させた。いつものように、いつものとおりに、優しい気持ちで、生命と向き合うように……精霊に呼びかける。力を貸してほしいと。
(鶲の為に……鶲が愛する星の為に……!)
その瞬間、七海の指先がまるで電撃を受けたかのようにバチッ!と音を立てて弾かれた。
「……っえ?あ……!」
「!何……っ!?」
七海と鶲が声を上げたと同時、周囲は騒然となった。
七海の発動した呪術が浄化の力ではなく、周りのもの全てを無差別に傷つける力となって国民達に襲いかかったのである。
「うわああああ!!!」
「きゃあああ!!!」
「い、一体何が……これ、七海の力……なのか!?」
鶲が見れば、七海は懸命に力を抑えようとしていた。どうやら七海の意思とは関係なく力が溢れ出てしまう状態になっているようだ。
「ど、どうして……いつもは優しい力なのに……」
なんとか力を抑え込んだ七海は、自分の力が引き起こしてしまった目の前の現実を受けとめきれずにいた。
それは国民達も同じだった。
あの、天帝様の孫娘が、織女星様が、ヒトに刃を向けるなんてこれっぽっちも思っていなかった。
七海の力をまともに受け血を流して倒れる数人の人達を前に、一人の女性が呆然とした表情でぽつりと呟く。
「……ば……化け物……」
「なっ……!」
「ち、違っ……私は、こんなつもりじゃ……」
鶲は勿論その一言を聞き逃さなかった。なんとか七海を助けようとするが、その女性の言葉を皮切りに他の民達も騒ぎ始める。
「そんなこと言って、実は俺達の星を滅ぼすのが目的なんだろう!?鶲様まで誑かして……!」
「何言ってるんだ!違う!七海は本当に皆を、この星を救いたい一心で……」
「ベガに帰れ!化け物!!」
「こらっやめろ!七海を攻撃するな!その前に怪我人の手当てが先だろ!?」
国民達は激昂し、その場に落ちていた石や木の枝等を七海目掛けて投げつける。鶲は七海を守るように前に立ちはだかり、傷つきながらもなんとか説得を試みようとしていたが、国民達の怒りは収まらなかった。
無理もないだろう。ようやく現れた救世主が、助けてくれるどころか自分達に刃を向けてきたのだから。
「やめて……悪いのは私……鶲を傷つけないで、鶲を……」
鶲の背後で、七海は涙を流しながら懇願する。国民達の攻撃の手はやむ気配はなく、鶲は七海を庇いどんどん傷ついていく。
その時、七海の中で何か光が弾けたような気がした。
(私の力は、鶲の為に──!)
「!?」
「ぎゃああああああ!!!!」
一瞬、自分の声が頭の中で痛いほど響いた。その瞬間七海の中から溢れるように出てきた真っ白な光を纏った力は、いまだ鶲を攻撃し続ける国民達目掛けて襲いかかる。まるで風のように具現化されたその力は、炎とも刃ともつかない。国民達の体に触れた瞬間次々とその箇所を壊死させていき、すぐに砂のように消えていく。まともに力を食らった者は跡形もなくその場から消えていた。
「な、七海!?嘘だろ、七海の力が、こんな……」
目の前で起きている出来事を、鶲も信じられないといったような表情で見ていた。
国民達は次々と悲鳴を上げ、その場から散り散りに逃げていく。しかし七海の力は本人の意思とは関係なく七海の体から溢れ出し、逃げようとする国民達を追いかけようとしていた。
「やめて!もうやめて!!私は……!!」
「……全く」
「!」
ふと、静かな声が聞こえた。鶲の耳がその声を捉えたと同時、七海の力はぴたりと動きを止める。二人が声のした方を見ると、七海の後方、少し離れたところに天帝が立っていた。手を翳しそこから溢れている光は、どうやら七海と七海の力を押さえつけているようだ。
「お、じい……さま……」
天帝の姿を確認した七海はすぐに気を失いその場に倒れ込んでしまった。同時に、七海から溢れていた力も全て霧散して消えていく。
天帝は呆然と立ち尽くしている鶲には目もくれず、倒れた七海の様子を確認した。微かに息をしているのがわかると、安堵したように溜息をつく。
「危ない危ない。あともう少しで我でも手を付けられなくなるところであった」
軽い口調でいいながら、天帝は七海を抱き上げる。鶲はそこでやっと我に返った。
「て、天帝様……今のは、一体……」
鶲が訊ねるが、天帝は鶲を一瞥すると
「お前が鶲か……すまぬが、七海には今後一切関わらないでもらいたい」
と冷たく投げかけた。天帝の言葉に、鶲は思わず絶句してしまう。
「お前の存在が、七海の心を惑わす。吉と出ればよかったのだが、どうやら凶となってしまったようだな」
「っど、どうしてですか……!俺達は将来を誓い合ったのに……!」
「……」
鶲は叫ぶが、天帝は何も答えない。自分の腕の中で眠り続ける七海を慈しむように見つめている。
「お願いです、天帝様……七海は何も悪くない、悪いのは俺なんです……だから……だから……!」
「……此度起きたこと、そしてアルタイルのこの惨状は我がなんとかしよう。七海のことは……忘れてくれ。それがお前の為にも、七海の為にもなるのだ」
懇願する鶲に天帝はそう言い放つと、そのままその場から姿を消してしまった。
「天帝様……!そんな……忘れるなんてそんなこと……うわあああああああ!!!!!」
誰もいなくなったアルタイルの街に、鶲の悲痛な叫び声がこだました。
「鶲様、失礼致します」
扉を叩く音が響いた後、開いた扉から青年が入ってくる。
彼の名は「鶫(つぐみ)」。このアルタイルの宮殿で、鶲の世話係として身の回りのことや仕事の手伝い等をしていた。鶲が七海以外で、唯一全てを曝け出すことができるほど、鶲が全信頼を置いている人物である。
あれから鶲は宮殿へ戻ってきていた。事件の事後処理の為机へ向かっていたのだが、どうにも集中できずにいた。脳裏に浮かび上がるのは七海のことと、そして天帝の言葉が何度も繰り返し再生される。
鶲はぼーっと虚空を見つめ、鶫が部屋に入ってきたことにも気付いていないようだった。
「鶲様」
「うわっ!?な、なんだ、鶫か……」
耳元で名を呼ばれ、鶲はようやく鶫の存在に気付く。驚きのあまり飛び上がって椅子ごと後ろへひっくり返りそうになった鶲を、鶫は表情一つ変えず腕を掴んで助けた。それから淡々と、外で集めてきた情報を鶲に伝える。
「アルタイルの惨状は、天帝様の手助けにより沈静化しました。今はあの場所に結界が張られています。あの場所に封じ込めるつもりのようです」
「……そうか……」
「それから……国民達の、七海様に関する記憶も消去したようです。アルタイルの民達は誰一人として、今日起きた惨劇を覚えていません」
「……それでいい。七海は化け物なんかじゃない。神聖な、ベガの織女星……それでいいんだ」
鶲はどこか寂しげにそう呟いた。
鶲自身の為にも、七海の為にも、七海のことは忘れてくれと天帝は言っていた。鶲の存在が、七海の心を惑わす、とも。
再び天帝の言葉の意味を考えていると、鶫が静かに語りだした。
「鶲様……少し、調べたのですが。七海様の持っている力は、心にとても影響されやすいのだそうです。嬉しい時は良い力に、悲しい時は悪い力に……その負の力は、天帝様の力を凌ぐとも」
鶫の話を聞いた鶲はハッとなった。
「待て……ということは、七海の力が暴走したのは……俺が、七海を寂しがらせてしまっていたせい、か……?」
「……仕方ありません。鶲様は七海様の恋人である前に、アルタイルの星の精。七海様を優先してあのような状態になってしまっているアルタイルを放置するなど、できるはずはなかったのですから」
ゆっくりと頷きながら話す鶫の言葉の意味は、勿論鶲もよくわかっていた。
アルタイルの星の精である以上、己の星の危機を見過ごすわけにはいかない。それは、同じ星の精である七海にもわかっていたはずだ。
それでも──七海は捕らわれてしまった。「寂しさ」という感情に。
自分は七海を大切にすると言ったくせに、彼女のその寂しさにちゃんと向き合うことができていなかったのだ。
「……全部俺のせいじゃないか……俺が七海を……ああ、俺はなんて馬鹿なんだ……」
「……鶲様……」
顔を伏せ、嗚咽を漏らす鶲の姿を、鶫はただ見守ることしか出来なかった。
こうなってしまうのがわかっていたら……それならあの時、どうしていればよかったのだろう。
今考えてもどうにもならないことを考えてしまう。
だが、アルタイルという星を統治できるのはアルタイルの星の精たった一人。鶫はそれを補佐することしかできない。自分にもっと、星の精に成り代われる力があれば、こうして目の前にいる大切な人を後悔で泣かせることもなかったのだろうか。
「……皆の記憶から七海のことが消えたとしても……俺は、俺の判断で自分の星を危機に曝してしまったこと……そして七海を悲しませてしまったこと……俺は全部覚えてる……俺は愚かな星の主だ……俺は……」
「鶲様……!鶲様は立派な星の主です。国民達の誇れる、アルタイルのたった一人の星の精なのです。どうか……どうか、お気を落とさぬよう……」
朧げに呟く鶲を、鶫は懸命に励まし、そして抱きしめた。今の自分にできることは、とにかく彼の傍にいてあげることくらいだ。今、この人を一人にしてはいけない、と鶫は思っていた。泣き続ける鶲を抱きしめ、子供をあやすように優しく頭を撫でる。
「それでも、鶲様は一人ではありません。私がいます。ずっと、お傍におります」
鶫の胸の中で、鶲はようやく落ち着いたらしい。泣き声は啜り泣く声に変わり、そして小さく鶲は呟いた。
「鶫、ごめん……暫くこのままで……」
そう言って鶲は鶫を強く抱きしめる。鶫は一瞬驚いて目を見開いたが、すぐに鶲に身を委ねた。
「はい……鶲様の、お好きなように……」
「……」
ぼんやりと目を開けば、映ったのは遥か昔に見たことのある天井だった。
知らない場所ではない。だけど、どこだったろうか。
そんなことをぼんやりと考えていると、横から聞き覚えのある声が聞こえてくる。
「目を覚ましたか、七海」
横に立っていたのは天帝だった。七海の眠っていたベッドの横に置いてある花瓶に水を差し、綺麗に咲く花の香りを嗅いでいる。
「フローが見舞いにと持ってきてくれてな、南斗六星のタウ星で咲く花だそうだ、良い香りだろう」
そう言って橙に輝く花を一輪七海に手渡すが、七海はまだ状況を理解できないでいるのか、花を受け取りながらもぽかんとしていた。
「……調子はどうだ」
「……ここ、は……天宮……?」
混濁とした意識で、天帝の言っていることはとりあえず理解ができた。見覚えのあるこの天井は、自分が幼い頃何度も眺めた、天宮の星空の天井だ。
「そう、天宮だ。お前はここで一週間も眠っておったのだぞ」
一週間。そんなに長い間、自分は眠り続けていたのだ。
何故。一体、何故、何があって……──
「……!鶲!鶲は!?アルタイルは……!」
「アルタイルは我がなんとかしておいた。今は原因不明の森も封印してある。暫くは問題ないだろう」
自分が眠り続ける直前の出来事を思い出し七海はベッドから飛び起きるが、すぐに激しい目眩に襲われ、再びベッドに沈み込んだ。一週間も眠り続けていたのだ、体がまだ本調子を取り戻せずにいるのだろう。
天帝は溜息をつくと、七海に優しく布団をかけてやりながらそう話した。
ひとまず、アルタイルの危機は去ったということである。
「……よかった……」
七海もベッドの中で、安堵の息をついた。
しかし、安心した七海に天帝は、今七海が一番気になっているであろう問題を口にする。
「……それで、鶲の件なのだが」
七海は再びベッドから飛び起きる。そして今度は天帝に縋るように懇願をするのだ。
「っ鶲は悪くないの!全部私が、私がしたことだから……鶲には何もしないで……!」
「落ち着くのだ。鶲には特に罰などは与えてはおらぬ。だが……今後、お前の心に害をなす存在になる可能性が高い故、お前には今後一切関わるなと伝えておいた」
「!」
それはつまり、鶲とはもう二度と会うことができなくなるということだ。
「お前が織女星としてベガを治めることになった時に、言ったはずだ。お前は誰のものもなってはならない、と。お前の心は、もう完全に目覚めてしまっている……あのアルタイルの星の精、鶲のお蔭でな。こうするしかないのだ。辛いだろうが……鶲のことは忘れてくれ」
七海は思い出した。自分が織女星としてベガから力を授かった時、天帝から言われた言葉を。
そうだ、元々自分には心というものがなかった。それは、自分の心が誰か一人に捕らわれてしまうことがないようにと。捕らわれてしまうことで、この力が乱れぬようにと、ベガ星がそう祈って心を持たない星の精、七海を創りこの力を与えた。
ベガから与えられた自然の力は全ての五行の力の結集であり、強力な繁栄の力でありながら少しでもバランスを崩せば危険なものに変質する力でもあった。
天帝はそれを危惧していた。だから、七海に強く言い聞かせていた。
しかし七海は出逢ってしまった。鶲に。そして、幸せという感情に。
鶲がくれたものは、全て七海の心となっていった。そうして芽生えた七海の心は、知らぬうちに鶲のものになってしまっていたのだ。
「……お爺様。お願いがあります」
「なんだ」
七海は固く目を閉じる。暫くそうしていた後、意を決したように目を開き、天帝の目を見つめて言った。
「私を封印してください」
「……なんだと……?」
七海の願いは、天帝さえも予想していなかったものだった。
てっきり鶲に一度逢わせてほしいとでも言うのかと思っていたし、一度くらいであれば、と天帝も考えていた。
しかし七海は、もう覚悟は決めたとでもいうような瞳で天帝を見つめ、そう願ったのだ。
「私の心は、もう様々なものに染まってしまった……楽しいこと。悲しいこと。つらいこと……愛し、愛されること……。鶲の為にと思えば思うほどあの人を傷つけてしまった。私はただ、この力であの人を助けたかっただけなのに……」
「……」
「楽しいことも、悲しいことも、誰かを愛することも……全部、何も知らなかった頃のまっさらな私に戻して……封印してください。この力は、もう私のものではなくなってしまった……私が、鶲のものになってしまったから……」
まるで懺悔をするように手を組み、涙を流しながら七海は話す。
心が芽生えてから気付いたことではあるが、七海はとても意志の強い子であった。己が一度決めたことは、決して曲げることはないのだ。
この願いも、天帝が彼女をどう説得したとしても、彼女は決して取り下げることはしないだろう。
天帝はやれやれ、と大きく溜息をついた。
「わかった。お前がそこまで言うのなら。だが、目覚めてしまった心を元のまっさらな状態に戻すのは難しい。お前は我の封印の中で、永遠に嘆き続けることになる……それでも……」
「構いません。私は掟を破ったのだから……それだけの罪を背負わなくては……」
やはり七海の意志は固い。真っ直ぐに天帝を見つめるその瞳は、どうあっても引き下がることはない、と。そう言っているようだ。
「……全く、お前は本当に……我の自慢の孫娘よ」
こうして七海は天帝の手によって自ら封印され、永遠の罰を受けることになったのだ。
「七海が封印された?」
アルタイル国の星の精の宮殿。自室で今日の分の事務仕事をこなしながら、鶲は鶫の報告を受け思わず筆を止めた。
「はい。天帝様の手によって封印されたようです。力の暴走を危惧した上でのことでしょうか……詳細は不明ですが」
鶫は耳にした情報を淡々と話した。
話を聞いた鶲は、何かを考えるように顎に手を当て、低く唸っている。
「天帝様は何を考えているんだ……?七海を封印したら、ベガはどうなる」
「代わりに国民の中から一人、一番強い力を持つ者を国の長とし、その者に国を統治させるようにするそうです。いずれはこのアルタイルと、他のヒトが住む星国もそのようにすると……今の状況では、星の精一人だけで国の統治を行うには人手不足ですから」
確かに、鶫の言うとおりだ。
先日のアルタイルを侵食していた危険植物の件もそうであったし、昔と比べて国に起きる問題は徐々に増えつつある。それはこの国が昔と比べて大きく育ったという良い結果から起きる問題なのだが、もう星の精一人で国をどうこうできる時代ではなくなってしまっているのである。
そう思いながら、鶲はもう一つ別のことを考えていた。
「……」
「……鶲様?」
鶫が訝しげに鶲を呼ぶと、鶲は急いで机の上を片付け始めた。
「七海はどこに封印されたんだ?」
「え……ベガの宮殿から遠く離れた……街のはずれにある森の神殿の中だと聞きましたが……」
「お前は情報通で本当に助かる」
そう言って部屋を飛び出そうとした鶲を、鶫は慌てて呼び止めた。
「!どこへ行かれるのです!」
「ベガだ。七海に会う」
鶲の返事は、鶫が想像していた通りのものだった。
いっそのこと、七海の件は鶲には話さないでおけばよかっただろうか、と鶫は一瞬思ったが、いずれ噂好きの国民達の口から聞かされることになるだろう。
「おやめください!天帝様にも、七海様に会うなと釘を刺されたのでしょう!そんなことがばれたら……」
「消されるかもな。でもいいんだ。ひと目、七海と会えればそれで……」
「……どうして貴方は、そこまで……」
鶫は、自分が泣きそうな声を上げてしまっていることに気付いていた。鶲も勿論それに気付いている。鶫が、自分の身を案じて必死に止めようとしてくれていることを。
それでも、鶲には七海のところへ行かなければならないという理由があった。
「元はといえば、俺が七海を寂しがらせたからこんなことになってしまったんだ。今更、もう遅いけど……また寂しがってると思うと、いてもたってもいられなくてさ」
それは、自分が七海に辛い思いをさせてしまったという後悔と贖罪の為だった。
心を持たなかった七海に心が芽生えてしまったのは自分のせい。
そんな七海が様々な感情を知ってしまったのも自分のせい。
そして最後は、それ故に封印されることになってしまった、愛しい人。
全ての責任は自分にある。鶲はそう思っていた。
「……これ以上止めても、もう無駄でしょうね……」
こうなってしまっては鶲を止めることなどできないと判断した鶫は、俯いて小さく呟いた。それからすぐにぱっと顔を上げると、祈るような眼差しで鶲を見つめる。
「絶対に、帰ってきて下さい」
「……はは、鶫のそういうところが、俺は好きなんだ。ありがとう。行ってくる」
静かに閉められた部屋の扉を見つめ、鶫はとにかく、彼が無事に戻ってきてくれることを強く祈るのだった。
七海は青白く輝く光のカーテンの中で眠っていた。
少し眠って、ふと目を覚まし、また眠る。その繰り返しだった。それでもその目から溢れる涙が止まることはない。何度も夢に見る、彼のことを思い出して……
(あれから、どれくらいの時が経ったのだろう……。この結界、私をただ封印するだけでなく、触れる者、近づく者の呪力や魔力を奪うようにできている、私に干渉しようとする者を少しでも減らす為に……)
勿論、自分が触れても呪力をあっという間に奪われ、自分は消失するだろう。
消失、という道を選択するのもいいと考えた。しかし、それでは自分の犯した罪を償うことはできないと思ったのだ。
消失して、また新たな「私」として生まれ変わる。それではだめだ。心を手に入れてはいけない自分が心を手に入れてしまった罪。知ってはいけなかった様々な感情。それらの罪を全て、なかったことにはできない。罪から逃れることはできない。
(これは私の罪……幸せを手に入れてはいけなかった、私自身への、罰……)
「七海!」
ふと、遠くから声が聞こえた。久しぶりに耳に響いた人の声だ。
それに、とても聞き覚えのある声。
「……!この声……まさか……!」
七海を呼ぶ声は次第に近づいてくる。そして声の主は結界が放つ青白い光に釣られ、この部屋に入ってきた。
「!七海!やっと見つけた……!」
「ひ、鶲……!どうしてここへ……」
声の主は、やはり鶲だった。この広い神殿を散々走り回ってここへ辿り着いたのだろう。ふー、と息を整えると、七海の姿を見て嬉しそうに笑った。
しかし、七海は心中穏やかではなかった。彼は、天帝から自分に会うなときつく言われていたはず。
「お前が封印されたって聞いたから、ひと目だけでも逢いたいって思ってな……」
「どうして……私のせいで、鶲が辛い目に遭ったのに……」
「べ、別に俺は何も辛くなんてなかったぞ!寧ろ俺の方がずっと、七海に寂しい思いをさせてたんだ……ごめん……」
そう言って結界に触れようとする鶲を、七海は慌てて止めた。
「近づいたらだめ!」
「!?」
「この結界は触れた物や近づいた者の呪力、魔力、生命力……あらゆる力を奪うの。これ以上近付いたら、鶲の力が奪われて消失してしまう……!」
七海の声で鶲は慌てて手を引っ込めたが、そういえばこの部屋に入った時から、何故か体がピリピリするのを感じていた。七海の言うように、おそらくこの青白い光の結界のせいだろう。すぐに体に影響があるわけではないようだが、先程走ってきた時の疲労がいつまで経っても取れない。長時間ここに居座っているのは危険だということを鶲も察知した。
「成程、どうしても七海を一人にしたいってわけか……」
この神殿は、織女星が特別な行事がある時にしか使わない神殿だとベガの国民から教えてもらった。織女星である七海がここに封印されているのであれば、七海以外の者がここを訪れることはほぼない。
更にそれを知らない誰かがここへ迷い込んできたとしても、七海の封印結界に生命力を奪う力を施し、七海との接触を困難にする。
七海がもう二度と、誰かと心を通わすことがないように……。
しかし、七海は泣きながら
「違うの……!私が、私がお爺様に頼んでこうしてもらったの……私が掟を破ったから……もう、誰も傷つけないようにと……」
こうした封印を施すように自ら頼んだのだ、と、そう訴える。これが心を手に入れてしまった自分自身への罰なのだと。
だが、七海のその訴えに鶲は我慢できず叫んだのだ。
「だめだ!お前、さっきからずっと泣いてるじゃないか……そんな顔の七海見てるの、俺、辛い……だから」
「……?」
「俺がお前をそこから出してやる!そしたら二人で……どこか別の星まで逃げて、一緒に暮らそう!」
「鶲……」
鶲の提案はとんでもないものだった。七海は思わず目を見開いて呆然としてしまう。
しかし当の本人は本気のようで、七海に施された封印結界をどのようにして壊すかを考え、一人ブツブツと何かを呟いている。
「……うーん、とは言ったものの、具体的にどうするか……つまりはこの結界の効力を無力化してしまえば……あーでもきつそうだな、天帝様の封印だしな……いやでも……」
「鶲、もういいから……私はもう、この罰を受けることを決めたのだから……」
「いいや!だってお前は何も悪いことしてないだろ!今日のところは帰るけど、絶対そこから出してやるから、約束だぞ!待ってろよ七海!」
そう言って鶲は急いでその場を後にしていった。何かいい案でも思いついたのだろうか、足音はすぐに小さくなり、やがて先程までの静寂が再び戻ってくる。
「……どうして……どうしてこんなに、私のことなんて……」
しかし七海の涙は止まることなく、彼女の頬を濡らし続けるのだった。
まるで、先程の約束など全て塗りつぶしてしまうかのように……
鶲はアルタイルに戻った後、すぐに研究を始めた。
鶲が無事に戻ってきたことに一度は喜んだ鶫であったが、鶲がとんでもない計画を立てているということを知り、必死で止めた。しかし鶲の決心は固く、それは勿論聞き入れてもらうことはできなかった。仕方なく折れた鶫も、密かにその計画に協力することにしたのである。
それから何ヶ月か経ったある日、鶲は再び、七海が封印されている神殿を訪れていた。
「鶲……」
「七海。今日はお前をここから出すために来たぞ」
心配そうに見つめる七海の瞳には、絶対に七海をここから連れ出すという強い意志を胸に佇む鶲の姿が映っていた。
最早、彼を止めることは誰も出来はしないだろう。
「でも、どうやって……」
七海は不思議そうに訪ねた。自分に施されているのは、この宇宙の創造主であり最高神、天帝の封印術なのだ。生半可な解呪術では歯が立たないだろう。
それでも鶲がここへやってきたということは、何か勝算があるということだ。案の定、七海の問いに鶲は得意そうに笑って見せた。
「アルタイルの星の力は特殊な蘇生術なんだがな、それをうまく応用できないと思って色々研究して改良してみたんだ。この「真の蘇生術」を使って、お前のその結界を、結界が作られる前の状態……つまり”無の状態に蘇らせる”」
「そんなことが……」
七海は息を呑んだ。それはつまり、時の力に触れる禁術となってしまう。
そう思っていると、自分と鶲の他にもうひとり、青年が部屋に入ってきた。
「ただし博打です。真の蘇生術はとてつもない量の呪力を消費する上に時の力に触れてしまう。大量の呪力消費と規律への違反……鶲様の体が、持ちこたえられるかどうか……」
入ってきたのは鶫だった。鶲のことが心配でついてきたのだろう。
そんな鶫の言葉にも、鶲は自身に満ちた笑顔で返すのだ。
「俺を誰だと思っている?アルタイルの星の精だぞ。好きな奴一人助けられないでどうするんだ」
「でも、でも……もし、それで私が助かっても、鶲が消えてしまったら嫌……」
七海は涙を流して訴える。自分の身はどうなってもいい。でも、鶲が消えるのだけは、七海にとってそれが一番辛いことなのだ。
それでも鶲は七海を安心させるかのように笑って言う。
「大丈夫、俺は消えない。信じてくれ、七海」
鶲のその笑顔を見て、七海は何も言えなくなってしまった。これ以上彼を止めようとすれば、彼のその言葉に込められた決意を全て否定することになってしまう。自分の為に、彼はここまでしてくれている……それを無下にすることはできない。
七海はただ、無事に事が終わるようにと祈ることしかできなかった。
「よし。それじゃあ、やるぞ」
そう言うと鶲は七海の封印結界の前に両手を翳す。
「決して、無理だけはしないでください」
「……わかってる」
鶫の心配する声に短く返事をし、鶲は深呼吸をした後、巨大な魔法陣を七海の足元に展開させた。妖精術を元に組まれた魔法陣の中を、アルタイルの星の力である強い蘇生の力が流れ込んでいく。その力は七海の足元を綺麗な緑の色に輝かせた。
やがて、七海の周囲を覆っていた青白い封印結界が砂のようにさらさらと音を立てて崩れ始める。
目の前で起きている信じられない光景を七海はただ呆然と見つめ、そして小さく呟いた。
「結界が砂のようになって……空へ消えていく……まるで全て下に落ちた砂時計の砂が元に戻っていくみたいに……」
崩れる速度はとてもゆっくりだが、確実に封印結界は「無」へと戻っていく。
半分ほど崩れた頃、鶲が苦しそうに呻き声を上げるのが聞こえた。
「う、うう……」
「!鶲様、やはり危険です……!この結界は生命の力を奪っていくもの……このままでは、結界を全て消す前に呪力が足りなくなってしまう可能性が……!」
鶫が慌てて鶲を止めようとするが、鶲は「大丈夫だ」と絞り出すような声で返しつつも笑って鶫を制止し
「っ俺は、それも計算に入れてんだ……絶対、に……七海を、ここから連れ出す……!」
と、呪力を注ぎ込む力を止めることなく、結界を消すために集中し続けた。
「鶲……」
心配そうに七海と鶫が見守る中、やがて結界は全て光の砂となり虚空へ消えていく。部屋の中は完全に、織女星が星に祈りを捧げるための、ただの儀式の間に戻ったのだ。
「結界が……」
あの天帝が施した強力な封印を、鶲の力はそれを上回ったというのだ。鶫は思わず呆然と呟いた。
「消えた……やった、やったぞ七海……!」
「鶲……鶲……!」
その横で、鶲と七海が再会を果たそうとしていたその時だった。
「そこまでだ」
「え……うわあっ!」
「鶲様!?」
突如、二人の逢瀬を引き裂くかのように風のような力が素早く通り抜けた。二人は咄嗟に避けたが、その力は先程まで七海の封印結界に施されていたものと同じ、相手の生命力を奪う呪術だと鶲はすぐにわかった。攻撃を掠めた腕が力を失い、麻痺したように動かなくなってしまったからだ。
「お、お爺様……」
七海は攻撃を放った人物の姿を確認し、言葉を失う。
部屋の出入り口に佇んでいたのは天帝だった。その表情は怒りをはらんでいるのが明らかで、金色の冷たい瞳が鶲を睨みつけている。
「シアンから秩序の乱れを察知したと報告を受けたのでな、まさかと思い来てみれば……我の結界を破るとは、その力は素晴らしい。素直に評価しよう。だが……七海をここから連れ出すなど、お前はこの宇宙を滅ぼすつもりか?」
「七海は俺がこれから幸せにするんだ!そうすれば、七海はもう寂しくない……負の力を使うことだってなくなるだろう!」
天帝の言葉に負けじと鶲は反論する。しかし、そんな鶲の主張にも天帝は顔をしかめるだけだった。
「詭弁を弄するか……」
全てはもう、取り返しの付かないところまで来てしまっている。鶲にはそれがわからないのだ。
「物事はそう簡単にはゆかぬのだ。お前との関わりによって、七海の心は大きく支配されすぎてしまった……いや、これは「依存」と言うべきか……こなってはもう、七海の力はベガを繁栄に導くことはできぬ。ベガは衰退していくだけだろう……最早、お前にどうこうできる問題ではないのだ」
「っそれでも……それでも、俺は七海を……!」
尚も諦めようとしない鶲に、天帝は呆れたように溜息をついた。これ以上言い聞かせても無駄だ、と判断したのだろう。
「……全く、我の言いつけを守って七海に関わることをやめれば、年に一度くらいならば逢瀬を許そうと思っていたのだが……」
「!お爺様!だめ、やめて……!」
天帝が翳す手に、とてつもない密度のエネルギーが集まっていく。
何かが来る、というのをその場にいる全員がすぐに察知した。
「!七海、鶫!逃げろ!!
咄嗟に鶲が二人に叫ぶ。天帝の狙いは確実に自分だ、と鶲は理解していた。
「鶲。お前にはそれ相応の罰を受けて貰わねばならん。呪術を限界まで消耗したその体では最早持ちこたえるのは無理だろうが……許せ」
「ぐ……っうわああああああああああああ!!!」
「鶲!鶲ーーーーーーーー!!!」
天帝の攻撃をまともに喰らい、鶲はその場に崩れるように倒れる。それを見ていた七海は、鶫に押さえられながら悲鳴のような叫び声を上げた。
相手の呪力源をシャットダウンし、半永久的に封印するという強力かつ特殊な呪術。体力のある者なら命の危機とまではいかないだろうが、鶲は七海を助けるために既に満身創痍の状態であった。最早、鶲には立ち上がる力さえ残されていない。
「……な、なみ……おれ……本当に、お前を……あい、し……て……──」
そして掠れた声でそう言い残すと、鶲の体はそのまま光の粒になって消えてしまった。
「……いや……いや、鶲……いやああああああ!!!」
「鶲……様……そんな……」
大切な人を目の前で失った二人は、ただただ、涙を流すことしかできなかった。
七海は泣き叫び、鶫は呆然とその場に立ち尽くしている。
そんな二人を一瞥し、天帝は一度目を伏せた。それから顔を覆い泣き続ける七海の元に近付いていく。
「どうして……どうして鶲が……消えるのは私でよかったのに……」
「……つらいところを見せてすまなかった。だが、鶲は禁忌に触れた。これはもう仕方のないことだったのだ」
天帝がいつものように七海の頭を撫でようと手を伸ばすと、その手はまるで何かに弾かれたかのようにバチッと音を立て、天帝の手に傷を付けた。
「!」
「……う、うう……」
「……そうか、やはりお前の力はもう……今一度封印する。鶲のことは……忘れるのだ。お前の持つ記憶、我の力の全てをもって、限りなく消去に近い、封印(ブロック)を……」
天帝は手を翳し、再び以前と同じ青白い光の封印結界を展開する。七海はあっという間に幾重もの光のカーテンの中に包まれていった。
七海は自分の瞼が急激に重くなるのを感じる。深い眠りにつくのだろう。そのまま眠りに身を委ねようとした時、頭の中に誰かの声が聞こえたような気がした。
──……対に……絶対に許さない……天帝……貴様だけは……!
「……ひ……た……──」
七海が眠りについたのを見届け、天帝は目を閉じ静かに息をついた。そして、いまだに背後で立ち尽くしている鶫に声をかける。
「……鶫」
「……はい」
鶫は静かに返事をした。
鶲に協力をした自分にも沙汰が下るのだろうか。であれば、自分はとっくに覚悟はできている。もとよりそのつもりで彼に力を貸していたのだから。
そう思いながら目を閉じると、天帝はまるで鶫の考えていることを見透かしたかのようにふ、と笑い
「お前には何もせぬ。お前は鶲を止めようとしたのだろう。だが、奴はそれを聞き入れなかった……結果、ああなったのだ。お前は何も悪くはない。だが……」
そこまで話し、天帝は一呼吸おいてから声を少し低くして話を続けた。
「今見ていたこと、決して他言はするな。星の精が消えたことがすぐに知られれば、アルタイルは大混乱に陥る」
「……承知致しました」
「鶲消失の件は我が後日国民に伝える。次の牽牛星が顕現するまで、急いで長を立てねばな」
そう言い残すと、天帝は鶫を残しその場から急ぐように去っていった。星の精がいなくなれば、国を統治する者がいなくなる。星に力を与えることができる者もいなくなる。それに成り代わる長を、急いで探すつもりなのだろう。それはまだいい。
(……今回のこの件……全て隠蔽するつもりなのか、あの男は……)
確かに、今回の事件は天帝が自ら創った数少ない星、ベガが生み出した星の精の七海を発端に起きた問題であり、一時はこの宇宙の危機であったのだから、それが人々に知られれば天帝の立場も危うくなる。更に実質二人の星の精を、七海は仕方がないことだとはいえ天帝が手にかけ、そして鶲は消失した。
鶲が消失するに至った経緯も何もかも、人々を不安に陥れるようなことばかりだ。
この宇宙には天帝のことをよく思わない者も少なからず存在している。そういった者達の反乱を防ぐ為にも、この事件は外部に漏らしてはいけないものである、と天帝は判断したのだ。
鶫は溜息をついた。つまり、この宇宙でこの事件の真相を知っているのは、天帝と自分だけだということ。
この真相を質に取ることで鶲の仇を取ることもできようが、そんなことをしたら今度こそ、自分も消されるだろう。
「……七海様」
鶫は、再び封印され深い眠りについた七海を見上げた。
「……私は決めました。これからはずっと、鶲に代わって私がお傍にいます。この身が朽ちるまで、少しでも貴女の寂しさを紛らわすことができたら……そう思うのです」
結界にはやはり、前回と同じように少しずつ人の生命力を奪う為の術が施されていた。勿論鶫はそれに気付いていたが、それにも構わずその場に座り込んだ。
「鶲のいない世界に、最早意味など無い……次の、新たな牽牛星の心を……ここで共に待ちましょう。それはもう……鶲ではないだろうけど……」
そして、鶫もそのまま静かに目を閉じるのだった。
深く愛し合った織女星と牽牛星は、定められた運命に抗うことができず、無残にも永遠に引き裂かれてしまったのでした。
取り残された鵲は封印された織女星に寄り添い、そして祈り続けました。
この人が新たな道を歩むことがあれば、今度こそ幸せでありますように、と……──
第六章 【真相】 完