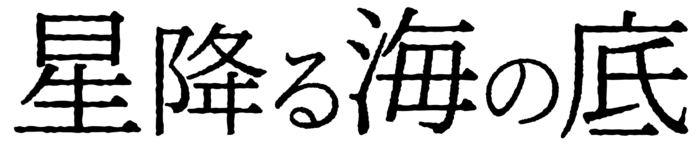第三章【織女星と牽牛星】
その事件は、なんの前触れもなく起きたのだ。
奏の家でのシェアハウスが始まってから、半年が経とうとしていたある日のこと。
物語は唐突に急展開を迎えようとしていた。
「へぇっくし!!」
いつもの朝の食卓に、馨の大きなくしゃみが響き渡った。
「ちょっ、汚いわね~」
「朝から鼻啜ってるけど、大丈夫?風邪?」
今日の食事当番である紅袮が温かい茶を淹れたカップを持ってキッチンから現れ、馨に手渡した。馨は礼を言いながらそれを受け取ると、息を何度も吹きかけて冷ましちびちびと飲み始める。
「うーん、そうなのかな……あんまり風邪とかひかないからよくわかんないや……」
「馬鹿は風邪ひかないって言うし、あんた昔から丈夫だったもんね」
「なんだと!?……うあ、やべえふらふらする……」
杏の挑発するような言葉に馨が軽率に載ってしまうのも最早いつものことなのだが、威勢よく杏につっかかろうとしたものの、この時ばかりはさすがに体の不調の方が勝った。馨は頭をふらつかせると、すぐに力が抜けたように椅子にもたれ座り込んでしまった。
「ちょっと、これはまずいんじゃないの?奏、体温計どこ?」
紅袮が奏に尋ねるが、奏は体温計を探すより先に、何を思ったのか徐ろに馨の額に自分の額を押し付けた。
「へ!?」
「あらまあ」
突然の出来事に馨の顔はますます赤くなり、杏や紅袮も固まってしまう。
一方奏はそんな馨の反応にも気にすることなく「うーん……?」と首を傾げた後
「なんかすごく熱いね」
と紅袮に告げるのだった。
その横で馨は頭から湯気を出し、今にも倒れそうな勢いである。
「か、奏に……おでこっつん……」
「そうなるでしょうよ!馨は早く寝て!もう、どこでそんなこと覚えてきたんだよ!」
倒れそうな馨を担いで馨の部屋に向かいながら紅袮が叫ぶと、奏は再び首を傾げてからのんびりと答えた。
「凪が、熱を測る時はこうするといいよって……」
「何教えてんだあのおっさんは!!」
馨が倒れたことを紅袮がクレスに伝えると、クレスはすぐに奏の家に蘇芳を向かわせた。
蘇生術から治癒術まで幅広く使うことができる蘇芳は医術にも明るく、力になれるとクレスは判断したのだろう。
奏の家に到着した蘇芳は、早速馨の様子を診てくれた。
「これは妖精風邪ですね。今流行ってるみたいだから」
「妖精風邪かぁ……」
馨の病気の正体が判明し、紅袮達もひとまずは安心したようである。
妖精風邪は人間界でいうよくある風邪の一種である。一つ違うのは、妖精達が皆持っている魔力が一時的に激しく低下するということ。とはいえ一時的であれば特に後遺症も残ることはないため、とにかく薬を飲んで安静にしていればすぐに完治する病気だ。
「大した病気ではないけどこじらせると危険ですから、しっかり栄養摂って休んでくださいね」
「はい……」
いつもはとにかくテンションの高い馨も、流石におとなしく布団の中で小さく返事をした。
「それじゃ、感染るとよくないですから皆部屋から出て。私がお粥作ってきますから」
蘇芳は紅袮達の背中を押して部屋から出ると、料理の支度を始めた。しかし、奏だけはいつまでも馨の部屋の前から動かず、心配そうに扉を見つめているのである。
「あの……馨は、大丈夫……?」
そう蘇芳に問いかける奏の表情はとても暗く、彼が人の為にこんな表情をするのも珍しい、と蘇芳は思った。いつもの奏であれば、誰かを心配することはあってもその表情だけはいつもと変わらない、無の表情のままであるからだ。
「一週間くらい安静にしていれば大丈夫ですよ。とはいえ今流行りですから、薬が手に入れにくいのが……困りましたね」
「あたし達で買ってこようと思ってたんだけど、そんなことになってるのね」
杏は途方に暮れたようにため息をついた。しかし紅袮も最近蘇芳に倣って医術に興味を持っているらしく、メモ帳を取り出して何やらページをめくり始めた。
「妖精風邪の薬の原料って、確か……」
「ええ、ナクレ草とコウヨウチュウ、それからアカリ草ですね」
「ナクレ草とコウヨウチュウなら確かこの森で見たことあるから何とかなりそうだ。問題は……」
メモを眺めながら、紅袮は唸った。蘇芳も困ったように頷く。
「そう、アカリ草はもうベガのものは薬として使える花が全て取り尽くされてしまってます。後は、地球のウォーターシティまで行かなくては……」
「ウォーターシティって、水の都って言われてる……?」
その時、杏が蘇芳の言葉に勢いよく食いついた。
「そうです。よくご存知ですね」
蘇芳が微笑むと、杏はまるで夢を見ているかのようにうっとりと語り始めた。
「広い砂漠の中に突然現れる広大なオアシス……そこには聖水と呼ばれる泉の水が滾々と湧き出て街を潤し、人々の暮らしを支えている……って本で読んだの!一度行ってみたくて……」
すると、馨の部屋の前から動かなかった奏もこちらにやってきて、真剣な眼差しで蘇芳に懇願する。
「あの、俺も……馨の為に何かできるなら、薬草、取りに行きたい」
蘇芳は暫く考えていたが、すぐにふう、と息をついて「そうですね」と頷いた。
「ウォーターシティならディレイスから近いですし、何より琥珀君達がいます。あの子達がいれば大丈夫でしょう。お願いしましょうか」
ウォーターシティはディレイス皇国より東の方角にある広大なユパ砂漠……その中心に存在する巨大なオアシスが都市になったものだ。
街は五つの巨大な泉が密集しており、その泉から流れる膨大な量の水は街の中で多くの水路を作り、舟の上で商いや生活する者もいる。まさに水の都なのである。
この街には、クリスタルの英雄である琥珀と蒼が暮らしていた。奏達が街を訪れると蒼は不在であったが、丁度泉の神への祈祷の儀を終えたばかりの琥珀が快く奏達を迎えてくれた。
琥珀は先祖代々、この街の泉に祈りを捧げる巫女の家系の者だった。現在は本来の巫女である琥珀の姉、レプレナがベガにいるため、姉に代わって弟の琥珀が巫女の仕事を務めているのだ。
「アカリ草、ですか。確かに泉の周りの森にたくさん生息している草ですけれど、妖精界ではそれが薬になるんですね」
琥珀は驚いたように言う。アカリ草は妖精にとっては大事な薬となる植物であるが、人間にとっては特にどの用途にも使われることはない、ただの雑草のようなものだからだ。
「神聖な水の周りで育つ、元々は妖精界でのみ生息していた草だけど、ここは、空気も水もとても澄んでいて……まるで神様に守られているみたい……」
森の中に入った奏は気持ちよさそうに深呼吸をする。その横で奏の様子を見ていた一人の青年が微笑みながら
「ここの泉は神のご加護を受けていますからね。だからアカリ草も自然と育つようになったんでしょう」
と話した。
「ところでテティス、久しぶりだね」
「あはは、ディレイスからここは距離が近いとはいえ、砂漠が過酷だから連れて行ってやってくれって、駆り出されちゃいました」
琥珀に「テティス」と呼ばれた青年は、苦笑を浮かべながら答えた。
テティスは土星の星の精である。かつてのブレウスとの戦いでは、ブレウス側へ寝返り一時は敵対していたが、それはブレウスに心を操られていたからであった。琥珀や妖精長達の活躍でテティスはブレウスの魔の手から解き放たれ、最終的にはクリスタルの英雄達と共にブレウスを討つために協力したのである。
彼は転移術を得意としていた。
転移術とは、離れた場所と場所を瞬時に移動する、テレポートのような術である。星の精が広い宇宙の中で星と星をすばやく行き来する為に作り出したという、星の精であれば誰でも使える基本的な呪術である。
とはいえ移動できる範囲は星の精の持つ呪力の強さが影響し、ある程度限りがある。テティスは太陽系の星の精の中で一番長距離を移動することができる星の精なのだ。
「ベガもアルタイルも基本的に涼しいから、あんなうだるような暑さのとこ歩いたら流石に死んじゃうかも……」
先程ユパ砂漠へ一歩足を踏み入れた時のことを思い出し、杏はぐったりと呟いた。妖精国はどこも太陽のような恒星が近くに存在していない星が多いため、妖精は暑さにめっぽう弱いのだ。
「ふふ、ここは水のお陰でとても快適ですけど、それでも気温は高めですから……気分が悪くなったらすぐに言ってくださいね。では、行きましょうか」
一同は琥珀に案内され、森の更に奥へ足を踏み入れるのであった。
「成程……あの時の七夕祭りで、そんなことが……」
「馨ってば本当に昔からおっちょこちょいで、今回の件もああやっぱりやらかしたわね、って感じ!」
道中、琥珀とテティスは杏から馨の話を聞かされていた。
琥珀とテティスも七夕祭りの当日はベガにいたのだが、ゆうじ達に街中の屋台へ引きずり回され、そのような出来事があったなど全く知らなかったのだ。
「確かに、昔凪さんのところにお邪魔した時に、よくお茶をこぼしたりお皿割ったりしてるところを見かけたことがありますよ。あの男の子が、もう七夕祭りに参加できる歳になっていたんですね……」
昔の記憶を呼び起こし、テティスは感慨深そうに呟いた。
すると、今まで皆の話を聞いているだけだった奏が突然鼻をくんくんと動かし始める。
「水の匂いがする……とても清らかな、穢れのない水の匂い……」
「まだ泉まで結構距離ありますけど、もうわかるんですか」
琥珀が不思議そうに尋ねると、奏はゆっくりと頷く。
「水とか、花とか、木とか……植物、動物達の気配とか、気持ちがわかる気がするんだ、昔から。そこの花は、妖精さんこんにちは、って言ってる。気がする」
「えっそんなことがわかるの?奏すごいわね!」
普段から植物や動物相手に何やら話しかけているところはよく見かけていたが、あれは本当に彼らと会話を交わしていたということなのだろう。杏ははしゃぎながら「あの花はなんて言ってるの?」と次々に奏に尋ねている。
そんな二人の様子を、テティスは訝しげに見つめていた。
「どうしたの、テティス」
「!あっ、いえ、なんでもないです」
琥珀に声をかけられ、テティスはすぐに笑顔で誤魔化した。不思議に思った琥珀が問い詰める間もなく、少し前を歩いていた杏が声を上げたのが聞こえた。
「あっ!あれ、アカリ草じゃない?」
杏が指を差した先にはとても大きな泉と、その泉を囲むように一面を埋め尽くして黄色の花が揺れていた。あれこそが薬の原材料となるアカリ草の花である。
「たくさん咲いてる」
「これだけあれば困らないわね。たくさん摘んで帰りましょ」
奏はアカリ草の花の近くまで足を進めると、その場にしゃがみこんだ。そして優しく、友達に語りかけるように声をかける。
「馨を助けるためなんだ、摘ませて下さい。……いいよって言ってる、と思う」
奏は顔を上げると、小さな笑顔を浮かべて皆にそう伝えた。
「ふふ、それはよかった。私も手伝いましょう」
「僕も!」
皆で一斉に花を詰み始め、蘇芳に持たされた籠の中はすぐにアカリ草の花でいっぱいになった。
暫く花を摘んだ後、一同はすぐ近くの泉で休憩を取っていた。泉に足を浸しながら、杏が気持ちよさそうに息をつく。
「綺麗な泉……この水が街へ流れて、水の都を作り出しているのね。本当に、ここが砂漠のど真ん中にあるなんて忘れちゃうくらいだわ」
「ウォーターシティへ観光に来る方は皆そう言いますよ。そう感じられるのも、この泉の加護のお陰です……感謝しなければ」
杏達と他愛ない会話を交わしていた琥珀であったが、ふと、奏の様子がおかしいことに気付いた。
泉の上──虚空をきょろきょろと見回し、何やら不安そうな表情をしているのである。
「どうしました、奏君」
不思議に思った琥珀が奏に声をかけると、奏は声を潜めて
「……水の精霊が、たくさんいる……」
と答えた。
「え、そうなの!?」
奏の言葉に杏は目を輝かせた。
精霊は主に地球等の自然が存在する場所の力を守護するものであり、例えば水場であれば水の精霊、森であれば緑の精霊など、種類は様々だ。
自然を住処とし、自然を守る存在……そして、妖精達にとっては、精霊が守る自然のエネルギーを借りて妖精術を使うため、非常に大切な存在でもある。
しかし目視することは困難であり、人間は勿論、妖精であっても余程の強い自然の力を持っていなければ彼らを視ることはできないのだ。
そんな精霊を、奏は今視ているというのである。
「でも、なんだか変……何かに怯えているみたい……」
「……!」
奏の言葉に、三人は息を呑んだ。と同時、異様な気配に気付き、三人はその場に身構える。
「……何か……いますね……」
「奏、あたしの後ろに隠れてて」
「……!!」
杏が奏を自身の背後に庇ったと同時、杏の前方を何かの攻撃が掠めたように見えた。あまりの速さに、琥珀は思わず声を上げる。
「は、速い……!?」
「スロウグラビティ!!」
しかしテティスの攻撃が僅かに当たったのか、姿の見えない「何か」が近くの茂みに落ちる音がした。
スロウグラビティは相手の動きを重力で封じ込める呪術である。直撃とまではいかなかったものの、掠めた程度でも多少は相手の動きを抑えられるはずだ。
「姿を現しなさい!ブルーミングミラージュ!!」
今が好機と言わんばかりに、続けて杏が茂みに向かって術を放つ。大量の花弁に包まれたそれは、やがて少しずつ、人の姿となって一同の前に姿を現した。
「……」
ダークブルーの長い髪を首の後で一つに結わえ、少女のような風貌をしているが、おそらく少年だ。どことなく奏と雰囲気が似ている、と杏達は思った。
彼は輝くような紫の瞳で、一同を睨みつけるでもなく淡々と、無表情に見つめていた。
「……君は……少なくとも、人間ではないね……?」
琥珀が尋ねる。先程のような身体能力は、普通の人間であればまず持たないだろう。
琥珀の問いにすぐ答えることはせず、彼はゆっくりと立ち上がった。先程の掠めたテティスの術の効果を既に無効化したらしい。三人は内心驚愕しつつも再び身構えた。
そして彼は、とんでもないことを口にしたのである。
「……私は牽牛星、悠。奏を渡してもらおう」
「!牽牛星ですって……!?」
信じられない、といったように目を見開いて悠を見つめているテティスをよそに、杏は奏の前に庇うように立つとすかさず詠唱を始めた。
「とうとう現れたわね!奏を渡すわけにはいかないわ!」
「……ならば力づくで奪うのみ」
悠は自分に向かって放たれた杏の攻撃を素早くかわすと、奏の背後に回り込もうとする。
「くっ……ソード!!」
奏に悠の手が伸びようとしたその瞬間、琥珀がタロットから召喚した剣の英霊が悠を弾き飛ばす。しかし悠はすぐに受け身を取り、その流れのまま英霊に光の杭のようなものを打ち込み、消してしまった。
「つ、強い……っ!」
「せめてクリスタルがあれば、もう少しまともに戦えるんだけど……」
奏をかばいながらの上、琥珀達はブレウスとの戦いの後、既にクリスタルをベガに返還してしまっている。自前の妖精術でなんとか応戦してはいるが、相手はテティスでさえ追い込まれる程の力の持ち主である。その差は歴然で、あっという間に追い詰められてしまう。
それでも、杏だけは力強い眼差しで悠を睨みつけ、決して奏を渡すまいと攻撃の手を止めることはなかった。
「絶対、奏は渡さない……!!!」
しかし、そんな杏の力も悠の力には僅かに及ばないようで、少しずつ彼女が傷付いていくのに奏は気付いていた。
(待って……どうして、俺の為に皆が傷付くの……そんなの嫌だ……!)
悠の攻撃が杏の膝に当たる。思わずバランスを崩し、杏はその場に膝をついてしまう。その隙を悠が見逃さないわけがなかった。
もうだめだ、と杏が思ったその瞬間、目の前に杏を庇う影が現れた。
「危ない、杏!」
「!奏!?」
「!?」
杏の目の前に奏が立ち塞がったことで、悠はすぐに攻撃の手を止めた。
奏は悠の目をしっかりと見つめる。その表情は、普段の奏からは想像ができない程の、怒りと悲しみが入り混じった、とても真剣なものだった。
「俺、皆が傷付くなんて嫌だ。だったら俺は、悠の言うとおりにする」
奏がそう話した瞬間、悠から放たれていた殺気があっという間に消えていくのがわかった。
「聞き分けのいい子だ。では、来てもらおうか」
悠は奏を抱き寄せると、目の前に手を翳す。すると何もなかったその場所に異空間への入り口を作り出した。
「だめよ、奏!奏ーーーーーーー!!!」
「蘇芳にちゃんと、アカリ草渡して馨のこと治してもらって。俺は大丈夫だから!」
必死に呼び止める杏に奏は微笑みかけると、そのまま悠に連れられ異空間の中へ消えていった。そしてその場にはまるで何事もなかったかのように、流れる泉の音が静かに響き渡っている。その音の中で、取り残された三人は呆然と立ち尽くしていた。
「まさか……狭間をあんなに難なく開いてしまうなんて……」
「……こうしてはいられません!すぐにクレス様と凪様のところへ……!」
テティスの言葉に頷き、三人はすぐにベガへと向かった。
「奏が……連れ去られた……!?」
テティス達から話を聞かされたクレスと凪は、一瞬何を聞かされたのか理解できなかった。
どう考えてもおかしなことが一度にたくさん起きたのである。
「彼は牽牛星、悠と名乗っていました。戦ってみたところ人間ではなく、おそらく妖精か星の精の類だと思いますが……」
「悠だって!?」
「おかしい……色々とおかしすぎます……」
理解に苦しんでいるクレスと凪に同調するように、テティスも大きく頷いた。
「はい……現在牽牛星……アルタイルの星の精は、遥か昔に初代が消失してから一度も顕現していないはず……」
「それに悠は、ベガの星の精様だ。ブレウスの襲撃で封印されてしまって以来姿を見せなかったのだが……一体、何がどうなっているんだ……?」
クレスは腕を組んで考え込む。
ベガの星の精であるはずの悠が、アルタイルの星の精である牽牛星を名乗る。それに、彼が奏を連れ去る理由も、全く見当がつかない。
しかし、杏が心底申し訳なさそうに震えた声で
「……ごめんなさい。折角あたしが奏と契約したのに、奏を守れなかった……」
と謝罪をしたことで、二人は彼女が何かを知っているということを察した。
「……杏、もしかして貴女は、何か事情を知っているのでは?」
「……」
「知っていること、全部話してくれないか?」
杏は暫く黙っていたが、もう隠し通すことはできないと判断したのだろう。ぽつりぽつりと、自分が奏と契約を交わすに至った理由を話し始めた。
「……あたしが奏と契約したこと……これは、天帝様の勅命だったの」
「なんですって……!?」
「そして、天帝様の孫娘、織女星……奏の正体よ」
杏から聞かされた真相に、その場にいた全員が言葉を失ってしまう。これはベガにとって非常に衝撃的な事実だ。そういうことであれば、今までこの星を守っていたベガの星の精、悠は確かに織女星ではなかった、ということになる。
「いや、待ってくれ……織女星といえばベガの星の精、悠ということになっている……何故、奏が……」
クレスは頭を抱えながら杏に問うが、杏は静かに首を横に振った。
「そこまでは私も事情をよく知らされていないの。ただ、織女星の持つ力を手に入れようとしている者がいる。その存在から守る為に奏と契約せよ、と……本当は馨が奏を契約できれば馨に守ってもらうはずだったんだけど、まあ、こういうことになっちゃったからね」
「織女星の持つ力……というのは……」
琥珀の疑問に、テティスの表情が今まで感じていた違和感の謎がようやく解けた、というようにハッとなる。
「そうか……!確かに、おかしいと思っていたんです。現在、妖精で自然などの五行の力をまとめて操れるのは浅葱さんだけのはず……奏さんは草木の気持ちを読み取り、水の気配を感じ、精霊を視ることもできる……確か……」
「伝承では、過去に消失した織女星も同じく五行の力を持っていたと聞きます。まさか……奏君が……」
にわかには信じられない、といったような顔で凪が続けると、隣で聞いていたクレスも静かに頷く。
「奏の、今はもう亡くなった両親は義理の両親だった。奏は知らないが……出生についても詳しくはわからない。しかし、現にこうして織女星として攫われたということ。そして、杏が天帝様から勅命を受けた、ということは……そういうことなのだろう……」
奏の義理の父親は、天帝の重臣だったと聞いている。
天帝は執務の為に訪れた星で、孤児を拾ってくることが珍しくなかった。
現にクレスも自分の親が、天帝が拾ってきた孤児を預かり育てていたことがあるのを知っている。
奏の義理の父親もそのような経緯で孤児であった奏を預かり、天帝に用意されたあの森の奥の一軒家で奏を育てているのだと思っていたのだ。
その時、背後で物音がした。一同が音のした方を見ると、そこには部屋の出入り口で呆然と立ち尽くす馨の姿があった。
「奏が……攫われた……!?」
「!馨……!」
風邪を引いて最初は奏の家で療養していた馨であったが、やはり看病の為に奏の家で寝かせておくのは不便であること、感染の恐れもあるということから、蘇芳の判断で一時的にクレスの宮殿に帰されていたのだ。
「どういうことだよ……なんだよ織女星って……」
「先程の話、聞いていたのですね……」
「今すぐ奏を助けに行かなきゃ……!」
慌ててふらふらとどこかへ走り去ろうとする馨の腕を、蘇芳が素早く掴み引き留めた。
「待ちなさい!こんな熱では、外出は許可できません!」
馨の風邪による高熱はまだ続いていた。蘇芳は今にも倒れそうな馨を支えながら、馨に部屋に戻るように促す。しかし、馨は一歩も引かない。好きな人が名も知らない誰かに攫われたのだ。そんな話を聞かされれば、おとなしくしていられないのは当然のことだろう。
「それでも俺は、奏を守らなきゃ……守らなきゃいけないんだ……!」
「助けに行くにしても、どこへ行くというのですか」
「……っ」
うわごとのように呟く馨に、凪はぴしゃりと言い放つ。勿論奏がどこへ攫われたかなど馨は知るはずもなく、凪の言葉に何も返すことができなかった。
そんな馨を宥めるように、クレスは優しく声を掛ける。
「まだ手がかりが何も掴めていない。すぐに調べさせるから、馨はまず風邪を治しなさい。折角奏達が薬草を摘んできてくれたんだ」
「……」
尚も俯いてその場から動こうとしない馨の前に、杏が悔しそうな表情で立つ。そして頭を下げ、己の力不足を謝罪した。
「ごめん、馨……あんたの代わりに、あたしが奏を守らなきゃいけなかったのに……」
天帝から受けた勅命を遂行することができなかったというのもそうだが、契約を結んだ以上、奏は自分が守らなくてはいけなかった。馨の為にも。そしてそれが失敗したことを、杏はひどく悔いているようだった。
だが、馨はそんな杏を責めることはしなかった。
「……いいんだ。杏だって本当は、ちゃんとした自分が望むパートナーを見つけて契約を結ぶはずだったのに、俺のせいで……」
馨は馨で、自分の最初の失態がこのような結果を招いてしまったことに責任を感じているようであった。無論、馨であってもあの悠の力に敵うかどうかは難しかったかもしれない。
それでも──
「……あたしは天帝様の重臣だから、天帝様の命に従っただけよ」
「……ごめん……」
いつの間にか、馨の後ろに紅袮が立っていた。奏と杏が採ってきた薬草で薬を煎じてきたようだ。
ふらふらの馨を支えてやりながら
「薬。これ飲んで、今はしっかり休みなよ」
紅袮の言葉に、馨は静かに頷いた。
「悠の気配や感情……雰囲気からして、すぐに奏さんをどうこうしようという気はないように見受けられました。多少の猶予はあるかと。それから……相手は異空間へ逃げていきましたから、その影響で杏さんと奏さんの契約の力も一時的に働かなくなっている状態のようです」
テティスがそう話す。つまり、番の契約の力によって離れることができない、という力を逆手に取り、杏が奏の居場所を察知するという方法は現在取れないということである。
「そうか……テティス、星の精様達にご協力を願いたい。いいだろうか」
「勿論構いません。シリウス様に伝えてきます!」
クレスの頼みを、テティスは快く了承した。そして転移術でその場から瞬時に姿を消す。
「……」
その光景を、馨は朦朧とした意識の中でじっと見つめていた。そしてどうか、どうか奏が無事であるようにと強く願い続けるのであった。
奏は見知らぬところにいた。
辺り一面、光の世界。眩しくはないが、光のせいで周りに何があるのか何もわからない。
──ここは……どこ……?確か悠って人に連れられて……なんかふわふわする。夢の中、なのかな……
ひとまず前へ進んでみようと、奏は一歩足を踏み出した。するとどこからか、聞き覚えのある声が聞こえてくる。
「七海!」
……?馨の声……?
声は確かに、あの馨の声だ。人の特徴はおろか名前ですら覚えるのは苦手だが、馨とは、もう共に生活をして半年になるのだ。この声を忘れないわけがない。いつも自分に優しく話しかけてくれる、あの声だ。
しかし、馨の声が呼ぶのは奏の名前ではなかった。それでもその時奏は、そのことに違和感を全く感じていなかった。
「七海、探したぞ。ほら、こっちに来い」
……だめだ
「どうした、七海……?ほら、早く」
本能的に、奏はその声の誘いを断ってしまった。声は不思議そうに、それでも再び奏を誘う。
だが、奏の中の何かが、だめだと警告しているように、奏は一歩もそこから動けなくなった。
だめ、行けない、俺は……
──誰のものにもなってはいけない──
ゴン!と激しく何かにぶつかる音がした。と同時に自分の頭に伝わる衝撃。
奏は思わずゆっくり目を開けた。
「……?はれ、部屋が逆さまだ……」
目の前に飛び込んできたのは、全てが逆さまになった見知らぬ部屋だった。そのまま状況を理解しようとしていると
「君が逆さまなんだよ」
と、もう一人の声が聞こえ、奏は目だけを声のした方へ向けた。そこには人が立っていた。そしてようやく、奏は自分がベッドから落ちて逆さまの姿勢になっているということに気付く。
「あ、ほんとだ……ええと」
「悠だ」
起き上がると、頭に血が上っていたのかはたまた頭をぶつけたせいなのか、少しくらくらとした。
そうだ、自分は確かこの、悠という人に連れてこられて、この部屋で待っているように言われて、そしていつの間にか眠ってしまっていたのだ。
「よく眠れた?」
悠の問いに奏は頷いた。悠は「そう」と短く呟くと、奏のいるベッドに腰掛ける。奏はずっと、悠を追いかけるように見つめていた。
「……何?」
流石に悠もその視線が気になるようで、訝しげに尋ねる。
「……俺を連れて行った時と、雰囲気が違う」
「ああ……あの時は鶲に体を使われていたから」
「ひたき……?」
「いいよ、思い出さなくて。思い出さない方がいいから」
初めて聞く名前に奏は更に問うが、悠はそれ以上、鶲に関しては何も言わなかった。しかし悠の言う「思い出さない方がいい」という言葉に、何かが引っかかる。
つまり、自分はその「鶲」を知っているということなのだが、奏自身はその名前に全く心当たりがない。
「どういうこと?つまり俺は、悠じゃなくて、ひたき、にここに連れてこられたということ……だよね。ひたきって、誰?」
「……悪いけど、今は答えられない。わかって」
それ以降、悠は口を閉ざしてしまった。部屋に沈黙が広がる。
普段は空気を読めない奏だが、この時ばかりはさすがに、鶲に関してそれ以上のことは何も訊けなくなってしまった。
しかし、今度は別の疑問が湧いてくる。
「……俺はここで、何をすればいいの?」
「……」
悠は何も言わない。機嫌を損ねてしまったのだろうか。しかしそれには構わず奏はベッドを降りると、扉へ向かう。
「早く帰らないと……馨と、みんなも待ってるから……」
扉には勿論鍵がかかっていた。それでも何度かガチャガチャとドアノブをいじっていると、背後から再び悠の声が聞こえてきた。
「奏は皆のところに帰りたいのか」
「うん」
奏は頷くと、次の瞬間、悠はとんでもないことを口にしたのだ。
「それなら……その五行の力、全て俺に渡して」
「……え?」
奏は一瞬、何を言われたのかわからなかった。
五行の力──聞いたことがないが、五行、といえば代表的な自然の力だ。自分はその力を使うことができるから、おそらく五行の力とは自分が持っている力の正式名称なのだろう。
しかし問題は、何故悠がこの力を欲しがるのか、だ。
それを問う前に、悠は話を続けた。
「その力を持っている限り、奏は運命から逃れられない。また同じことの繰り返しになってしまう」
奏には、悠が何を言っているのかが理解できなかった。しかし悠のこの口ぶりから察するに、おそらく……
「俺、皆のところに帰れないの……?」
「……その力を渡すまでは、帰すつもりはないよ。奏がここに連れてこられたのは、俺が君の力を受け取るため」
悠の返答は、奏の予想していたとおりであった。
「君に渡したら……その力を何に使うの?」
奏の問いに、悠は少し考えるように沈黙した後、
「それは……全て鶲に任せる」
と答えた。
また「鶲」だ。悠はまるで奏を助ける体で力を寄越すように話しているが、最終的にその力を鶲に委ねるのだという。奏にとって「鶲」が何者であるのか、そしてその目的はなんなのかわからない以上、自分の大切にしてきたこの力を渡すのは、だめだ、と感じた。
「……よくないことに使うのなら、渡せない」
奏の答えに、悠は肯定も否定もしなかった。ただ、今はこれ以上何を言っても無駄だと判断したのか大きくため息をつくと、ベッドから立ち上がり、奏の元へ歩み寄る。そしてまるで何もかも知っているかのような瞳で、奏を見つめる。睨みつけるでも、哀れむでもなく、ただ「無」の瞳で。
「……よく考えて。君はまた悲劇を選ぶのか、それとも今度はハッピーエンドを選ぶのか」
それだけ言い残すと、悠は部屋の扉の鍵を開け、一人で外へ出ていってしまった。
悠が出ていった後、扉はガチャリと音を立てたのを奏は聞いた。おそらくこの部屋の扉は再び施錠されてしまったのだろう。
「……」
奏は悠の言い残した言葉の意味を理解できないまま、じっと扉を見つめていた。
「なんや、もっとちゃんと説明してやればええんに」
悠が部屋を出て暫く廊下を歩いていると、悠にとってよく知る人物が声をかけてきた。
「楸……」
長い髪を三つ編みで一つにまとめ前に垂らしている青年、楸は、歩みを止めない悠を追いかけながら飄々とした口調で話を続けた。
「悠はちっとばかし言葉が足りへんとこあるさかい、あれだといらん誤解生んで警戒されてまうで」
「だけど……過去を思い出してしまったら、彼はきっとまた同じ道を選ぶのだと思う」
悠は唇を噛んだ。まさか奏があそこまで頑固だったとは。
常に無表情で、何を考えているかわからない。そして機械のように会話をする。きっと「あの人」も、鶲と出逢う前はあのような感じだったのだろう。
しかし、実際に話をしてみれば彼の中には間違いなく奏自身の意思が──「心」があった。
それもとても強いもので、だが今はまだ無垢な状態だ。きっとあの夫婦は、奏を”ああいう人間に”なるように育てたのだろう。天帝の命をしっかりと守って……。
しかしあの無垢で強い心が強い感情に支配されてしまえば……悠は固く目を閉じた。
「強すぎる五行の力……天帝様の血ぃ引いてはるんなら当たり前やけど、感情がトリガーになって天帝様の力凌ぐんはあかんよなあ……」
悠の思っていたことを代弁するかのように、楸は呟いた。
果たして、自分の計画はうまくいくのだろうか。悠の胸中はぐるぐると不安で渦巻いていく。
けれど、やるしかない。
「鶲は?」
その不安を拭い去るように、悠は話題を変えた。
「今はおらへんよ。器を持たへんから、長時間起きてるんは辛い言うとった」
「そう……」
悠は息をついた。
それ以上は何も語らない悠の横顔には、わずかにだが焦りが滲んでいるように見えた。
奏の説得に思った以上に苦戦をしたことが原因だろう。結局、先程は奏の首を縦に振らせることができなかったのだ。
しかし楸は、悠のこの計画に協力するふりをして内心はよしとしていなかった。
「なあ、悠……ほんまにあの子助けるん?」
「……俺が織女星として転生した今なら、五行の力を受け取れる。もう二度と、あんな悲劇を生み出したくないんだ」
「せやけど、そないなことしたら今度は悠が……」
心配する楸の言葉に、悠は目を閉じて静かに首を横に振った。そして再び開いたその瞳には、確かな覚悟の光が宿っている。
「俺はいいんだ。せめて彼がこの運命から逃れることができれば……俺は天帝に封印されようが消されようが構わない。もう、覚悟は決めている」
そして悠は再び、止めていた足を前に進める。
少しずつ離れていく悠の後ろ姿を見つめ楸は小さく呟いた。
「……そうは言っても、悲しむ人がここにおるんやけどな……」
「何か言った?」
聞こえないように呟いたつもりだったが、悠には聞こえていたらしい。だがはっきりとは聞き取れなかったようで、後ろを振り返って首を傾げている。楸は慌てて
「な、なんでもあらへん!」
と誤魔化した。
「そう」
悠はすぐに楸に背を向けると、再び歩き始める。自身の目的へ、一歩一歩、確実に進んでいくかのように。
「鶲は天帝を恨んでいる。彼の悲願を叶えて、早く転生させてあげるべきなんだ。そうでないと運命は終わらない……俺が、終わらせなきゃ……」
部屋に取り残された奏は、再びベッドに戻って部屋の天井を見つめていた。頭の中は先程悠と話した内容のことばかり、ぐるぐると巡り続ける。
(織女星って、織姫のこと……?でも、どうして俺が?悲劇ってなんのことだろう、よくわからないや……悠からもっとちゃんと話を聞いた方がいいかな……)
奏は力尽きるように、腰掛けていたベッドの上に倒れる。ベッドがぎしり、と軋んだ音を立てた。
「七夕のお話は、本当はハッピーエンドで終わらなかったということを俺は知っている、けど、そんな結末はどの本にも書かれていない。俺だけが知ってる……それと何か関係があるんだろうか……」
実際に奏が何冊か読んだ七夕の伝承はどれも全て、七月七日の晴れた夜にだけ二人は逢うことが許される、という結末。
しかし奏が覚えているのはそれよりももっと悲劇的な結末だが、そんな七夕の伝承はどの書物にも載っていないし、人から聞いたこともない。奏自身、具体的にその悲劇の内容を思い出すこともできない。
ただ漠然と「この物語はバッドエンドだった」ということを知っている、というだけなのだ。
「うーん……とりあえず、まずはここから出ないと……でも鍵がかかってるし……どうやっ……て………………」
奏にしては珍しく、立て続けに色々と考えを巡らせていたせいでいつの間にか疲労が蓄積していたらしい。
静かに寝息を立て、奏は再び眠りに堕ちていくのであった。
第三章 【織女星と牽牛星】 完