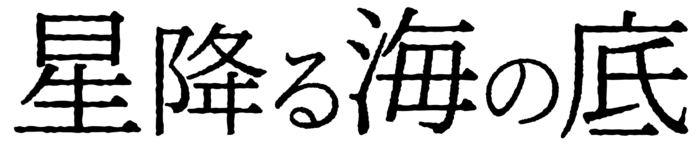アヌビスとフローライトの話
遥か、遥か昔の出来事。
黒帝に討ち勝った天帝は、自分だけになった広大な空間に「宇宙」という名前を付けた。
そして、闇しかないその空間に、いくつかの星とその星に宿る精霊を創り出した。
天帝は、創り出した星の精のうち3人に重大な役割を与えた。
「時」を司る力。これは最初に創った、太陽の精霊に。
「生」を司る力。これは二番目に創った、南の精霊に。
「死」を司る力。これは三番目に創った、北の精霊に。
この3つの力は、どれか一つでも欠ければこの宇宙の均衡が崩れてしまう、とても重大で大きな力である。
――これから賑やかになるであろうこの宇宙を、3人で支え合い、我と共に守って欲しい。
役割と共に神格を授けられたまだ小さな3人の星の精は、天帝の言葉にゆっくりと頷いた。
「あの子、また失敗したらしいのよ」
「天帝様から神格まで授けられたっていうのにこの体たらく……役割をお返しした方がいいんじゃないのかしら」
「……」
こちらを見ながらヒソヒソと小声で話す、あまり見慣れない精霊達を一瞥し、フローライトは足早にその場を去る。
あれから天帝は更にたくさんの星の精を創った。彼女達はきっとその中の精霊達なのだろう。
そして彼女達が話していたことは、概ね事実だ。
フローは、天帝にこの世で二番目に創り出された星の精であり、同時に「生」の役割と神格を賜った。
「生」の力の役割とは、この宇宙に誕生する星達、そしてその星に誕生する小さな生命体まで、全ての「生まれゆくもの」の生命エネルギーを管理し、この世に「誕生」まで導くこと。そして、その誕生した命に寿命を与えること。
話だけ聞けば簡単そうなのだが、これが実はとても、厄介な力なのであった。
「はあ……」
フローは大きくため息をつきながら、天宮より少し離れた森へと足を向けていた。
「元気してたか?このところ天気があまりよくないね。きみ達はちゃんと食事は摂れているか?」
森の木々や、その枝に止まる小鳥達に話しかける。ここの森の木々も、自分の力で誕生まで導いたものだ。故なのか、木々や動物達が何を話しかけているのか、フローにはわかるのである。
フローはこの森で過ごすことが多い。陰口ばかりの天宮に比べたら、周りは皆優しくて窮屈さも忘れてのんびり過ごせるからだ。
「大体、わかったような口ばかりきいて、どれだけ私が苦労しているか皆これっぽっちも知らないんだ」
集まってきた動物達に、フローは思いの丈を吐露する。
フローが周りに陰口を叩かれるのにはわけがあった。
それは、ここ最近いくつかの銀河を創るよう天帝から勅命を受けたのだが、これがどうにもうまくいかない。
銀河とは、数々の星の集合体である。とはいえ、その銀河の星全てをフローが創るのではなく、あくまで銀河の中心核――星を「誕生」へと導くための生命エネルギーを凝縮させた核を創るのだ。
これがあれば、星の精がその銀河系の統括者となった時、天帝やフローでなくても新たな星を創り出すことができるのである。
しかし、フローはその勅命を受けてからここ数ヶ月、失敗続きであった。
「そんなに言うなら、お前がやってみろって話だよ……神格とか知らないし、どうでもいいし」
要は、天帝に大きな力と神格まで賜っておきながら、失敗続きでろくに役割を果たしきれていないというのが、普段からフローをよく思っていない人達に燃料を注いでしまったのである。
こんな思いをすることになるなら、神格も役割もいらないのに……。
思わず涙が溢れそうになったその瞬間、後ろの茂みが大きな音を立てた。人の気配がする。
フローは慌てて溢れかけた涙を拭うと、音のした方を振り返った。
「……フローか、何してるんだ、こんなところで」
「あ、アヌビス……」
茂みから現れたのは、フローと同じく天帝から神格と役割を授けられた星の精、アヌビスであった。彼はフローの次――三番目に創られた星の精である。
「アヌビスこそ、どうしてこんなところに……」
「別に……天宮が窮屈だから、抜け出してきただけだ。この森にいた方がゆっくり休めるからな。ちょうど良さそうな木陰を探していたところだ」
「そう」
アヌビスもまた、自身の持つ役割で他者から陰口を叩かれたり避けられたりしている。とはいえ、フローとはまた別の意味でよく思われていないのだ。
彼に与えられた役割は「死」その「死」の力を恐れ、他の精霊達はアヌビスに近付こうとしない。
実際、アヌビスが与えられた「死」の力は、「時」の力と干渉しなければ働かない。ただ「生」を受けた者が正しき「死」を迎えられるよう、監視するためのもの。アヌビス自身が誰かの命を奪うだとか、そういったことはしない。それは禁忌となる。
だが、アヌビスの力を誤解するものは多かった。いい加減アヌビスも慣れたのか、こうして一人で休憩をしていたりふらふらしていたりすることが多い。他人と関わるということを、諦めたかのように。
それでも一応、生まれた時期がほぼ同時なのと共に神格と役割を与えられた者同士ということもあってか、アヌビスはフローと、もう一人……シリウスには心を許しているようだった。
「……泣いてたのか?」
アヌビスはフローの隣に腰を下ろすと、空を眺めながら訪ねた。
「!?な、泣いてない!まだ……!」
「目が赤いのに」
「泣きそうにはなってたけど、泣いてない!!」
図星を突かれ、フローは片手で顔を覆うともう片方の手でアヌビスの体をど突く。突然の衝撃によろめきながら「可愛くない奴だな」などとつぶやき、アヌビスはため息をついた。
「フローが気にすることはない。あいつらはただ、フローの力を羨み、妬んでいるだけだ」
フローが先程まで何に対して落ち込んでいたのかをまるで全て見透かしているかのように、アヌビスは言う。
アヌビスは、他人に対して基本気遣いをするタイプではない。寧ろ人の気持ちなどお構いなしに空気を読まず、自分の思ったことをそのまま口にするタイプだ。アヌビスが力のこと以外で他人から距離を置かれてしまう理由の一つでもあるのだが、当人は全く気にしていないらしい。
それなのに、フローやシリウスに対してだけ、このように相手を思いやるような声をかけてくれるのだ。おそらく、「心を許した者限定」というやつだろう。
「きみのその人を思う気持ち……もっと他の人にも向けてやればいいのに」
そうお節介を言うとアヌビスはすぐにむっと唇を尖らせ
「他の奴らはくだらないことで俺を恐れる。フロー達のことも妬む。そんな奴らに気を遣ってやる道理などない」と言い放つのだった。その性格が、いつか大きな災いとならなければいいのだけど……と思いながら、フローはため息をついた。
「天帝様は何故、私に「生」という役割をくださったのだろう」
「それは……フローがその力を与えられるに相応しい素質があったから、じゃないのか」
「そうなのかな」
フローは自分の両手をじっと見つめる。この手は、今まで数々の命を「誕生」へと導いてきた。この森もそうだ。フローの力で、今ではたくさんの生き物が住まう楽園のような場所になっている。
「フローでなければ、こんな素晴らしい森を創れやしないだろう」
傍に寄ってきた人懐こいリスを撫でると、アヌビスは愛おしげに呟いた。
「それは買いかぶりすぎだ。森はとても創りやすいものだから。なんといったって、植物は星や生物と違って生命力が強い。私の力は最初のほんのすこしだけ。あとは植物達が自らの「本能」をもって成長していく。勿論、例外もあるが」
フローは、自分が今まで悩んでいたことをぽつりぽつりと語りだした。
「私の「生」の力は、実のところとても弱い力なんだ。弱い、というか、命を与えることはできるけれど、その生命をこの世に「誕生」させ、命をこの世に「繋ぎ留める」というのがとても難しい。植物は意思を持たないから「本能」のみで生きてくれるからいいけれど、私達のような精霊や生物はこれがとても厄介なんだ」
「厄介……?」
アヌビスが首を傾げ尋ねると、フローは苦笑した。
「例えば、私達のような精霊。ヒト。生物。彼らは私の力でこの世に「誕生」することまではできても「生きる」という本能が最初はとても弱い。これでは生命を維持し続けることができない。彼らが本能で「生きたい」と強く思ってくれなければ、私は彼らに寿命を与えることができず……私が灯した命の炎はあっという間に燃え尽きてしまうんだ。だから、私の力は皆が思っているよりとても弱く、そして難しい」
星も同じなのだそうだ。その星を管理する星の精の命をこの世に繋ぎ留める。フローに灯してもらった命の炎を維持し続けるために「生きたい」と強く思う心。それが弱いと、炎は燃料を失うようにすぐに燃え尽きてしまい、星は死へ向かう。
「どうしたらいいんだろう。私だって、好きで失敗しているわけじゃないんだ。頑張って、命を繋ぎ留めようとしているのに……星はすぐに消滅してしまうんだ。どうして……」
フローは項垂れ、沈黙してしまった。
まさか、フローの力がそこまで複雑だったとはアヌビスも知らなかった。
――人が決して抗うことができない力――
自分たちが天帝から授けられた力は、全てそういった力だからだ。人の意志が、本能が、何を思ったところで生まれる者は生まれるし、老いる者は老いるし、死ぬ者は死ぬ。そして百の巡りに戻り、フローの生命エネルギーが再び命に炎を灯す。人はただ、自分達の力の輪廻から決して逃れることができず、流されていくだけのものだと思っていたのだ。
(……だけど、そんなの……)
アヌビスはふと、疑問に思った。フローがやるべきことは、自身の生命エネルギーで命に炎を灯し、それを誕生へ導くこと。そしてその生命に寿命を与えること。
フローは自分に与えられた役割はしっかりとこなしているのだ。問題は、フローに命を与えられ誕生までさせてもらった者が「生きたい」という意思を持たない為に、せっかく与えられた命を棄ててしまっているということだ。
「それは……フローは悪くないんじゃないのか」
「えっ……」
「悪いのは、折角フローに命を与えてもらったのに生きようとしない者達だ。フローが責任を感じる必要はないだろ。フローは優しすぎるんだ。奴らの意思なんて関係なく寿命を押し付けろ。無理矢理この世に繋ぎ留めてしまえばいい」
アヌビスの言い分はとても強引だった。強引だがでも、確実な方法だった。人の気持ちに無関心なアヌビスだからこそできる方法だろう。
フローは空気を読んでしまう。命を与えた者が、この先どういった人生を歩んでいくのか。そういった覚悟がこの者にあるのか、意思があるのか、判断を命に委ねてしまう。
「人が決して抗うことができない力」に、人の意思が干渉できる隙を与えてしまっているのだ。だが、それがフローの優しさ故だろう。
「だが、私は……矛盾しているかもしれないが、生きる覚悟や意思のない者をこの世に繋ぎ留めることがとても酷なことのように思えてしまうんだ……」
命の一生は様々だ。楽な生を送れる者もいれば、苦しいだけの生を送る者もいる。命を誕生へ導くことのできるフローではあるが、その与えた命がどのような未来を迎えるかまではコントロールできない。もし命を与えた者が苦の道を歩むことになった時に「生まれてこなければよかった」と思われるのが、フローにとってとてもつらいことなのだろう。
アヌビスは、フローの言い分にため息をついた。全く、どこまでも優しくて甘い奴だと。
そういう男だから、天帝はきっとフローに「生」の力を授けたのだろう。
「わかった。そういうことなら、俺がフローを支えてやる」
「……?どういうこと……?」
「俺の力は「死」だ。死の恐怖が迫る時、生物は本能的に「生きたい」と強く思うらしい。だから……俺が、お前の役割の手助けをしてやる。もうひとりで悩むことなんてない」
アヌビスの言葉に、フローは一瞬目を大きく見開いた。それからすぐにクスクスと笑い始め、アヌビスは面食らってしまった。
「なんだ、俺、何かおかしなことを言ったか?」
「いや、そうではないよ。あれだけ自分の力のせいで他人に恐れられてしまっているきみが、逆にその力を使って私を助けようとしてくれるなんて……きみの方こそ優しいよ」
「……他人のことなんてどうでもいいし……俺のこの力が……恐れられる力が、フローの役に立つのであれば、それでいい」
「ふふ……ありがとう」
「ああ、二人共ここにいたのか」
再びフローがころころと笑っていると、もう一人、聞き慣れた声が間に割って入ってきた。木陰でひんやりとしていた風が、少し暖かくなったのを感じる。
「シリウス」
やってきたのは、シリウスであった。シリウスは、天帝が最初に創った星の精であり、フロー達と同じく神格と「時」の力を授かっている。太陽という星を管理し、既に天帝から与えられた天の川銀河の統括者となっていた。
「どうしたんだ、こんなところに」
「いや、天宮は窮屈だからな、少し外でくつろごうと思ったんだ。フローが創ってくれたこの森はとても心が安らぐから」
フローの問いかけに、シリウスは先程アヌビスが答えたこととほぼ同じような回答をした。それを聞いてフローは再び声を上げて笑う。
「私達、森に来た理由が皆同じだな」
「なんだ、二人もそうだったのか。それで随分と楽しそうだったが、二人は何を話していたんだ?」
フローは自分の役割のこと、そしてそんな自分の力を支えてくれると言ったアヌビスの提案のことをシリウスに離した。
「なるほど……たしかに、生命というのは誕生の瞬間が非常にデリケートで扱うのが難しい。生を受けてはいるが、死はすぐ隣にある。その、隣にある死を遠ざけるために必要なのは、本能からの「死」への「恐怖」と「拒絶」だ。アヌビスの力を借りるのは、私は悪くないことだと思う。なんといったって、「死」があるから「生」は輝くのだから」
「死があるから……」
「生は輝く……」
フローとアヌビスは顔を見合わせた。
「アヌビスの力は「死」ではあるが……その力が人々の生命力を輝かせるのは間違いないことだと思うよ、私は。アヌビスが太陽の光となり、月であるフローを輝かせてやればいい」
「死」はただ、人々に刻一刻と迫る恐ろしいもの、というわけではないのだ。「死」というものがなくなれば、この世に誕生する生者は全員、ただ生かされるだけの生きた屍のようになってしまうだろう。
「……ということだそうだ、アヌビス」
シリウスの意見は、自分の提案に対して肯定的であったが、改めて他人に解説されると少し気恥ずかしさがある。そうでなくても、アヌビスがフローに言いたくても言えなかったことを、シリウスがそれも全て理解して話してしまったのだから。
――アヌビスが太陽となり、月であるフローを輝かす……
(それでは、なんだか、まるで……)
尚も俯いたまま黙っているアヌビスを不思議に思ったのか、フローが彼の顔を覗き込む。
「!?」
突然フローの顔が目の前に現れ、アヌビスは驚きのあまり猫のように凄まじい勢いで飛び退いた。そのアヌビスの動きにフローも驚いたのか目を丸くして彼を見ていたが、彼の顔がまるで茹蛸のように真っ赤になっているのを見て「なんだ、照れ臭かったのか?」とからかうように笑った。
シリウスも先程のアヌビスの動きが余程面白かったのか、笑いが止まらないといった様子で腹を抱えながら
「まあ、そういうわけだ。私の「時」の力はフローの力にはあまり協力することができないが、何かあれば相談に乗るさ。気軽に頼るといい」
そう言ってフローの頭を優しく撫でるのだった。
「うん……うん、ありがとう、シリウス」
そうだ、自分は一人ではない。
時をほぼ同じくして生まれ、同じくそれぞれの役割と神格を与えられ、周りからの羨望、妬みの声を浴びながらも、己の役割を全うしている仲間がいる。その仲間の存在が、自分を支えてくれるのだ。
頼り、頼られ、支え合う。
元々天帝が持っていた宇宙の秩序の力をわざわざ3つに分け、自分達にそれぞれ譲り渡したのは、きっとこんな風に仲間と支え合いながら絆の力で世界を守って欲しいという願いが込められていたのだろう。
フローは役割と神格を授けられた、あの時の天帝の言葉を思い出してようやく理解した。
そしてまだ照れているのか、離れたままこちらに近付こうとしないアヌビスの元に歩み寄り、彼の手を優しく握るのだった。
「アヌビスも、ありがとう。それから……これからもよろしく」
フローは微睡みの中で目を覚ました。
随分と懐かしい夢を見ていた気がする。
そんなことをぼんやりと考えながら、フローの混濁とした意識は少しずつ鮮明に覚醒していく。
「……!」
意識がはっきりした瞬間、フローは勢い良く体を起こした。すると同時フローの頭に激痛が走り、思わず呻き声を上げ頭を抱え込んでしまう。
「起きたか、フロー」
聞き覚えのある淡々とした声がかけられ、フローはゆっくりと声のした方を見た。
そこにはアヌビスがおり、机に向かって何やら巻物のようなものを眺めていた。
そうだ、ここは天宮の、彼の部屋だ。シリウスの力が消える気配を感じて、フローは慌ててアヌビスのもとを訪れたのだ。
アヌビスも同じ気配を感じていたようで、フローを出迎えたアヌビスはもうフローが何をするために自分の部屋を訪れたのかを察していた。
ここから少し離れた天の川銀河で、シリウスは天帝の勅命を受け、天の川銀河に突如現れた「ブレウス」という敵と戦っていた。戦況は時折天帝から聞かされるのみで、フローとアヌビスの二人には彼を救援するための勅命は下らなかった。二人はシリウスを心配していた、その最中の出来事であった。
フローがアヌビスの部屋を訪れる前に天帝から預かった書状。それには特例が書かれていた。
――蘇芳の寿命を延ばせ、と。
蘇芳とは、天の川銀河に住む、特殊な蘇生術を使える妖精であった。
彼は消失しかけたシリウスを助ける為、蘇生の禁術を使ってシリウスを回復させたというのだ。本来であれば、禁術を使った者はその規律に則り魂ごとこの世から消えることになるのだが、天帝は決死の覚悟でシリウスを助けた蘇芳を称賛し「特例」で彼を助けたいと思ったのだという。
シリウスはこの世にいなくてはならない存在。そんな彼を救ったということは、この世界を救ったも同義。一つくらい、我から褒美を与えてやってもいいだろう、ということだった。
フローとアヌビスは、二人で力を合わせることで人の寿命を延ばすことができる。
とはいえ、対象は禁術を使った者。規律に倣い、死へと向かっていく者。そのような者にただ寿命を新たに与えるだけでは、生命はその者の身体に留まることはできない。まるで底に穴が空いたバケツに水を注ぐようなものであり、意味を成さないのだ。
そこでフローは「今の蘇芳」ではなく「過去の蘇芳」の寿命を延ばした。それは、アヌビスの管理する「人の一生」が綴られている巻物の内容を強引に改変するということ。本来ならそれも禁術であるのだが、天帝の特例の力が働いていたから気を失うだけで済んだらしい。
「蘇芳は……助かったのか……?」
目を覚ましたフローはすぐに蘇芳の安否を尋ねた。蘇芳の巻物を確認していたアヌビスは目を閉じて息をつくと
「問題ない。蘇芳の未来は安定している」
と、巻物をもとに戻しながら答えた。それを聞いてフローも安堵したように大きく息をついた。しかしまだ頭はくらくらするのか、フローは再び寝かされていたアヌビスのベッドに横たわる。
そんなフローの様子を見たアヌビスは半ば呆れたような口調で、しかし心配そうな表情でフローの身を案じた。
「全く、無茶をする」
「……天帝様の特例なら、必ずやり遂げなくてはいけないだろう。あれしか方法がなかった……」
「しかし、一歩間違えればお前も死んでいた」
「……そうだな。でも、今回は天帝様がそれを考慮して力を与えてくれていたから」
特例に関わる自体であれば、禁術を使っても規律に触れることはない。わかってはいたことだがそれでも、フローが禁術を開放して倒れた瞬間は肝が冷えた。天帝が創り出した星の精達は、アヌビスであってもその死の気配を窺い知ることはできない。このままフローが目を覚まさなかったら……と、内心とても不安だったのである。
「……アヌビス。さっき、とても懐かしい夢をみていたよ」
ふと、フローが懐かしそうに夢の話をし始めた。
遥か昔の、自分達がまだ小さかった頃。天帝から役割と神格を賜ったのに、うまく役割を果たせず、悩んでいたあの頃のこと。
「私の力は……きみのお陰で、ここまで大きくなることができたんだ」
フローは自分の手を見つめ、呟いた。
アヌビスの持つ、人の一生の巻物を強引に書き換えるのは、禁術なだけあって相当の呪力と強い意志が要求される。それこそ、銀河の核となる生命エネルギーを創り出す以上の。
アヌビスもあの頃のことを思い出したのか、珍しく僅かに笑みを浮かべていた。
「俺は何もしていない。フロー、お前が地道に努力して、力をつけてきたからだ」
「そんなことはないさ。私は何度もきみに助けられてきたよ。……シリウスも言っていただろう、きみが太陽となって、月である私を輝かせればいいと」
フローは嬉しそうに笑っていた。
あの時は大口を叩いて色々言ってしまったが、実際のところアヌビスはフローの力になれているのかどうかわからなかった。しかし、こんな風に嬉しそうに話すフローを見て、間違いなく自分は太陽になれていたのだと少し安堵した。
「それは……それなら、よかった」
アヌビスも自然と笑みがこぼれた。
「俺も、何度もフローに助けられてきた」
フローの存在と、その笑顔に。他人に対して無関心なのは今も変わらない。人とあまり関わろうとしないのも変わらない。それでも、こうして他人の命を救うために寿命を延ばす、なんて力が使えるようになったのも……ひとえに、フローの存在が傍にあったからだとアヌビスは思っていた。
「え、私、アヌビスに何かしたかな」
心当たりがない、といったように首を傾げるフローを一瞥し、アヌビスはふ、と笑いながら
「内緒だ」
と答えるのだった。
「意地悪だなあ、アヌビスは……あ、そういえば」
「なんだ」
「いや……シリウスが言っていたその、太陽と月の比喩表現……昔は気づかなかったが、今思うとまるで私達が夫婦のようだな、と思って」
「!!!」
瞬間、アヌビスはあの時のように真っ赤になってしまった。
アヌビスは当時もそれに気付いていた。シリウスはおそらく特に深い意味もなくその例え話をしたのだろうが、当時からフローに密かに片想いをしていたアヌビスには心臓に悪い表現だった。
一瞬のうちに真っ赤になってしまったアヌビスを見て、フローはおかしそうに笑う。からかわれたのだろう。アヌビスは笑うフローに向け「もう少し寝てろ」とソファの上のクッションを投げつけた。
飛んできたクッションを顔面に受けたフローは「もう、酷いなあ」と漏らすが、すぐにそれを抱き枕のように抱えて布団の中に潜り込んだ。
「お言葉に甘えて、もう少し眠るよ。今日はなんだかとても疲れたし……」
「そうしろ。俺はこれから天帝様のところへ報告に行ってくる」
「シリウスの近況……わかったら起こして」
アヌビスは無言で頷くと、机の上にまとめておいた書類を持って部屋を出ていこうとした。
「アヌビス」
ドアノブに手をかけたと同時、背後からフローの呼び声が聞こえた。どうした、と返す間もなく、フローは言葉を続ける。
「さっきの話……私はアヌビスとなら、夫婦でも構わないと思っているよ」
「……っ!?」
驚いてフローの方を見ると、フローはもう既にクッションを大事そうに抱きかかえ安らかな寝息を立てていた。寝言だったのだろうか。いや、そうだとしても……
「馬鹿……こんな顔じゃ、天帝様のところになんかいけないだろうが……」
部屋を出れば、すっかり夜の世界になっていた廊下の窓ガラスが、耳まで真っ赤になった自分の顔をはっきりと映していたのだった。
終